気功法に意義あり
いま、気功法がブームであるらしい。たしかに、テレビや雑誌などあちこちで気功師が登場しては、摩訶不思議なパフォーマンスを披露している。中国の気功師が、手から発射する氣によって他人の手足を操ったり、あるいは日本の気功師たちもがんばって、数メートル離れた男たちを「エイッ」などと掛け声かけるだけで吹っ飛ばしたり、まるでマンガの世界のようだ。合氣道十段、世界中で演武を行い、プロレスラーや大男たちを投げ飛ばしてきた私でもそんなことはできない。読者の皆さんはできますか?客観的にはっきり確かめられたなら、そうした超能力みたいなものを信用してもいいが、自分の目で確かめもしないですぐに鵜呑みにするのは愚かなことだ。ある人が大金を出してフィリピンの有名な心霊手術者に胆石を取ってもらい、喜んで帰国したのだが、検査を受けたら胆のうには相変わらず石が残っていたというかわいそうな話もある。やはり、ありえないことはありえないし、不可能なことは不可能なのである。氣を商売にする人にとっては、氣は何か特別なもの、神秘的なもの、不思議なものであってほしいのだろうが、残念ながら氣ほどありふれたものはないのだ。私は氣が誰にでも出せることは何十年も教えてきたし、誰でも使えるからこそ、教える価値もある。だいたい、走っている車のタイヤを超能力で「エイッ」とやってパンクさせるといっても、驚くべき話ではあるが、それが何の役に立つというのか。そんなことより、パンクしたタイヤを「エイッ」とやって直すことができたら、どれほど社会の役に立つことだろう。
気功法ブームに巻き込まれている人たちにいっておきたいのは、中国の気功師たちの氣についての理解が、実は不足しているということである。中国の考え方では氣は使ったら減ってしまうから、気功師たちは氣をためておいて、めったなことでは使わないという。だから、実際に気功師たちによる治療(外気治療)が大病院で行なわれているが、何日か通って効果のない人はもう彼らの治療は受けられない。氣を無駄には使えないというわけだ。氣は使えば使うほど消耗するのは事実で、気功治療師に以外と病人が多いのも、患者に氣を取られてしまうからだ。しかし、天地の氣と耐えず交流している人間は別である。こういう人は氣を使えば使うほどまた氣が入ってくるから、ますます健康になる。気功師たちはそのことを知らないのである。使ったら減るような氣は氣ではない。それは「気」だ。すでに氣づかれた方もいると思うが、私は氣を「気」とは絶対に書かない。漢字は表形文字であり、「気」では天地のエネルギー、パワーを表してはいないからだ。もともと、この氣という字体は中国から来た文字である。昔、文字のなかった日本は、中国から文字が入ってきたときに、その便利さゆえにさっそくそれを取り入れた。中国では文字の形に意味があるが、日本語には音に意味がある。これはどういうことかといえば、天地のとらえ方が違うのだ。だから、日本では中国語の読みと日本語の音を両方生かしておいた。つまり音と訓である。ところが、氣という字には音も訓もない。ただ「き」と読むだけだ。しかも、この「き」は、中国語の音ではなくて日本語の音なのである。
中国では氣を「ち」と読み、「き」とは読まない。「き」というのはあくまでも日本語の音であり、古代日本では天地の、あるいは大地の力をさして「き」といっていた。そして、これが合いそうだというので当て字をしたのが氣という文字だったのだ。この氣という文字は、もともとは雲の形からできたのではないかと私は考えている。学者諸氏は、米を主食にしていたから中に米という字を書いたと説明しているが、そうではない。上の「气」という部分は天体をかたどっており、下もまた米ではなく、八方に開いている姿をかたどっている。つまり、てんたいの下で生命エネルギーを四方八方に放出していく状態を表したのが、もともとの「氣」という文字の意味で、氣とは出すものなのである。しかし、最近のように「米」ではなく「メ」(締める)と書いてしまっては、氣を内側に閉じ込めるという意味になってしまう。これは、古代中国では氣が一方に出れば他方が少なくなる、だから出口を締めてできるだけ氣をため込んでおくほうがいいと考えていたので、その影響を受けてのものだ。氣はもともとためるものではない。氣は出すから入ってくるのである。天地の氣と人間の氣が交流することを「息」というが、息が一時的にとだえれば氣絶する。永久にとだえてしまえば死ぬ。つまり、天地の氣と人間の氣の交流が止まったときが死なのである。氣を出していればこそ、生き生きとした健康な生活が送れるのである。
いま、気功法がブームであるらしい。たしかに、テレビや雑誌などあちこちで気功師が登場しては、摩訶不思議なパフォーマンスを披露している。中国の気功師が、手から発射する氣によって他人の手足を操ったり、あるいは日本の気功師たちもがんばって、数メートル離れた男たちを「エイッ」などと掛け声かけるだけで吹っ飛ばしたり、まるでマンガの世界のようだ。合氣道十段、世界中で演武を行い、プロレスラーや大男たちを投げ飛ばしてきた私でもそんなことはできない。読者の皆さんはできますか?客観的にはっきり確かめられたなら、そうした超能力みたいなものを信用してもいいが、自分の目で確かめもしないですぐに鵜呑みにするのは愚かなことだ。ある人が大金を出してフィリピンの有名な心霊手術者に胆石を取ってもらい、喜んで帰国したのだが、検査を受けたら胆のうには相変わらず石が残っていたというかわいそうな話もある。やはり、ありえないことはありえないし、不可能なことは不可能なのである。氣を商売にする人にとっては、氣は何か特別なもの、神秘的なもの、不思議なものであってほしいのだろうが、残念ながら氣ほどありふれたものはないのだ。私は氣が誰にでも出せることは何十年も教えてきたし、誰でも使えるからこそ、教える価値もある。だいたい、走っている車のタイヤを超能力で「エイッ」とやってパンクさせるといっても、驚くべき話ではあるが、それが何の役に立つというのか。そんなことより、パンクしたタイヤを「エイッ」とやって直すことができたら、どれほど社会の役に立つことだろう。
気功法ブームに巻き込まれている人たちにいっておきたいのは、中国の気功師たちの氣についての理解が、実は不足しているということである。中国の考え方では氣は使ったら減ってしまうから、気功師たちは氣をためておいて、めったなことでは使わないという。だから、実際に気功師たちによる治療(外気治療)が大病院で行なわれているが、何日か通って効果のない人はもう彼らの治療は受けられない。氣を無駄には使えないというわけだ。氣は使えば使うほど消耗するのは事実で、気功治療師に以外と病人が多いのも、患者に氣を取られてしまうからだ。しかし、天地の氣と耐えず交流している人間は別である。こういう人は氣を使えば使うほどまた氣が入ってくるから、ますます健康になる。気功師たちはそのことを知らないのである。使ったら減るような氣は氣ではない。それは「気」だ。すでに氣づかれた方もいると思うが、私は氣を「気」とは絶対に書かない。漢字は表形文字であり、「気」では天地のエネルギー、パワーを表してはいないからだ。もともと、この氣という字体は中国から来た文字である。昔、文字のなかった日本は、中国から文字が入ってきたときに、その便利さゆえにさっそくそれを取り入れた。中国では文字の形に意味があるが、日本語には音に意味がある。これはどういうことかといえば、天地のとらえ方が違うのだ。だから、日本では中国語の読みと日本語の音を両方生かしておいた。つまり音と訓である。ところが、氣という字には音も訓もない。ただ「き」と読むだけだ。しかも、この「き」は、中国語の音ではなくて日本語の音なのである。
中国では氣を「ち」と読み、「き」とは読まない。「き」というのはあくまでも日本語の音であり、古代日本では天地の、あるいは大地の力をさして「き」といっていた。そして、これが合いそうだというので当て字をしたのが氣という文字だったのだ。この氣という文字は、もともとは雲の形からできたのではないかと私は考えている。学者諸氏は、米を主食にしていたから中に米という字を書いたと説明しているが、そうではない。上の「气」という部分は天体をかたどっており、下もまた米ではなく、八方に開いている姿をかたどっている。つまり、てんたいの下で生命エネルギーを四方八方に放出していく状態を表したのが、もともとの「氣」という文字の意味で、氣とは出すものなのである。しかし、最近のように「米」ではなく「メ」(締める)と書いてしまっては、氣を内側に閉じ込めるという意味になってしまう。これは、古代中国では氣が一方に出れば他方が少なくなる、だから出口を締めてできるだけ氣をため込んでおくほうがいいと考えていたので、その影響を受けてのものだ。氣はもともとためるものではない。氣は出すから入ってくるのである。天地の氣と人間の氣が交流することを「息」というが、息が一時的にとだえれば氣絶する。永久にとだえてしまえば死ぬ。つまり、天地の氣と人間の氣の交流が止まったときが死なのである。氣を出していればこそ、生き生きとした健康な生活が送れるのである。



















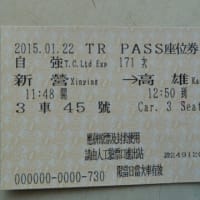
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます