「はだ色」は、人権派によって「肌の色はヒト其々で人種によっても違い、不適切な呼び名」とされています。ところが、「白人」は確実に白くはないし、「黒人」も黒くは有りません。黄色人種は決して「黄色」ではないのに、日本人が自分の「肌の色」を「はだ色」と言うと「白い目」で見られます。勿論、その見ている眼は「しろ色」ではなく「目色」をしています。また、メジロの目も「しろ色」ではなく「目の周りが白い」だけです。
「うぐいす色」は「ウグイスの色では無くメジロの体色」と言われますが、これはメジロが「うぐいす色」をしているだけで、ウグイスが「うぐいす色」ではないと云う証拠にはなりません。
ウグイスが枯れ枝に留まっている写真を見ると、確かにウグイスは「えだ色(灰褐色)」をしていますが、若葉をバックに陽光が反射するとウグイスは「うぐいす色」に見えます。
また、青葉や青信号は「あお色」ではなく「みどり色」なのですが、青信号の場合は「新聞のフェイク」が発端なので無視するとして、「陰陽五行」思想では、中央に土(大地=黄)が在り、周囲に木(春=青、緑)、火(夏=朱、赤)、金(秋=白)、水(冬=玄、黒)を配置しています。
「みどり色」は黄色っぽい青で、「しゅ色」は黄色っぽい赤です。「しろ色」は無色とも言います。「くろ色」は総ての「いろ」を含んでいるのが「黒」で、暗闇で何も見えないのを「玄」と言い黄色っぽい黒です。「緑・朱・玄」は「つち色(黄)」を含んでいる「状態色」と言えます。
「状態色」は、特定の人々が一定の条件下で感じる色なので、固定された色を示すとは限りません。「赤ら顔」は赤くないし、「青ざめた顔」も青くは有りません。
若葉は「わかば色」で、青葉は「あおば色」。ウグイスが「うぐいす色」なのは、日本人が「初夏の陽の射す若葉茂る木に留まったウグイス」を見た時の「状態色」を表現した「いろ」なので、外国人や日本人の様な人には理解できないかも知れません。
当然、場所や季節が変わると「いろあい」も変わります。
以上、単なる「自論」です。
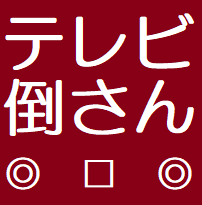










「もともとの日本語には色の表現・・・」の時代はいつ頃ですか?
陰陽五行思想は4世紀ごろに日本に伝わったとされているので、「黄色」もその頃には有ったと思います。
古事記の「黄泉の国」は地下の国で、黄色い硫黄の泉をイメージでき、黄色の概念は既にあったと思います。
2000年以上前の日本では、元々は「ねずみ色」とか「物の名前」が色名だったと思います。「黄・赤・青・黒・白」等の色名は、それ以降に支那大陸から伝わった、「モノの色」ではない「イロの色」を名前にして客観性を持たせたのではないでしょうか。