スタグフレーションは一般に、
「stagnation(停滞)」と「inflation(インフレーション)」の合成語で、経済活動の停滞(不況)と物価の持続的な上昇(インフレ)が併存する状態を指す。
とされていますが、これは「文系経済学」での定義です。
そこで、「理系経済学」で再定義(正しくは、本来の定義)します。
・デフレ:通貨収縮(通常は、通貨のモノに対する相対価値が上昇する)。
総分配(賃金など)の減少により、供給能力に対して通貨量が減少した場合は「通貨の相対価値」が増加(対外的には円高要因)し、多くの場合は物価の下落を起こします。これが行き過ぎると国内生産では採算が取れず生産拠点が海外に移り、国内の設備投資も減少して物価の下落を加速します。
デフレとは、市中の通貨量が減少(通貨の価値は上昇)する現象を言うので、当然ながら増税はデフレを加速します。但し、消費税等のように相対的に税負担率が小さい富裕層には「持ち金の価値」が上昇するので、増税分と通貨価値は実質的に相殺され、金持ちは痛くも痒くもありません。
企業の国内設備投資意欲や個人の消費マインドが低い時(需要不足)に、政府が財政出動では無く、金融操作(国債の買い入れによる金利下げ等)だけで対応すると対外金利差が拡大して円安が進み「輸入物価の上昇」により、「スタグフレーション(不況時の継続的な物価高)」が起こるかも知れません。
多くの経済専門家は、これを「コストプッシュ型のインフレ」と言うようですが、インフレの定義はあくまでも「通貨膨張(通貨価値の低下)」なので、市中に通貨量が増えない金融政策下では「デフレ状態」が継続し、「・・インフレ」とは言えません。
・インフレ:通貨膨張(通常は、通貨のモノに対する相対価値が下落する)。
物価上昇はインフレに付随する「良くある現象」に過ぎません。当然乍ら、インフレ時にも物価が下落をする事も有り得ますし、逆にデフレ時に物価が上昇(通常言われるスタグフレーション)する事もあります。
例えば、資源大国で輸出額が多く、且つ国内経済活動が自己完結する国の場合、資源の輸出で自国通貨量が増加(理論上のインフレ)し、その資金で設備投資をすると効率が良くなり、物価が下落(一般にデフレと言われる)する可能性が大きくなります。但し、多くの資源大国の国民は働くのが嫌いな為に、増えた通貨が自国で流通しない場合も有り、投資資金として海外に流出する為に物価下落は起き難いです。
アメリカのように、資源量も多く且つ無駄使いが多い国では、稼いだ金を自国で回転させる為に、総分配(給料など)と物価が同期し易く安定的な経済成長を遂げます。但し、ここでも金融政策に傾き過ぎるとインフレ(通貨膨張)を起こし、膨らみ過ぎたバブルが破裂します。
・スタグフレーション:景気低迷時の通貨膨張(通常は物価が上昇する)。
「stagnation(停滞)」と「inflation(インフレーション)」の合成語で、経済活動の停滞(不況)と物価の持続的な上昇(インフレ)が併存する状態を指す。
とされていますが、これは「文系経済学」での定義です。
そこで、「理系経済学」で再定義(正しくは、本来の定義)します。
・デフレ:通貨収縮(通常は、通貨のモノに対する相対価値が上昇する)。
総分配(賃金など)の減少により、供給能力に対して通貨量が減少した場合は「通貨の相対価値」が増加(対外的には円高要因)し、多くの場合は物価の下落を起こします。これが行き過ぎると国内生産では採算が取れず生産拠点が海外に移り、国内の設備投資も減少して物価の下落を加速します。
デフレとは、市中の通貨量が減少(通貨の価値は上昇)する現象を言うので、当然ながら増税はデフレを加速します。但し、消費税等のように相対的に税負担率が小さい富裕層には「持ち金の価値」が上昇するので、増税分と通貨価値は実質的に相殺され、金持ちは痛くも痒くもありません。
企業の国内設備投資意欲や個人の消費マインドが低い時(需要不足)に、政府が財政出動では無く、金融操作(国債の買い入れによる金利下げ等)だけで対応すると対外金利差が拡大して円安が進み「輸入物価の上昇」により、「スタグフレーション(不況時の継続的な物価高)」が起こるかも知れません。
多くの経済専門家は、これを「コストプッシュ型のインフレ」と言うようですが、インフレの定義はあくまでも「通貨膨張(通貨価値の低下)」なので、市中に通貨量が増えない金融政策下では「デフレ状態」が継続し、「・・インフレ」とは言えません。
・インフレ:通貨膨張(通常は、通貨のモノに対する相対価値が下落する)。
物価上昇はインフレに付随する「良くある現象」に過ぎません。当然乍ら、インフレ時にも物価が下落をする事も有り得ますし、逆にデフレ時に物価が上昇(通常言われるスタグフレーション)する事もあります。
例えば、資源大国で輸出額が多く、且つ国内経済活動が自己完結する国の場合、資源の輸出で自国通貨量が増加(理論上のインフレ)し、その資金で設備投資をすると効率が良くなり、物価が下落(一般にデフレと言われる)する可能性が大きくなります。但し、多くの資源大国の国民は働くのが嫌いな為に、増えた通貨が自国で流通しない場合も有り、投資資金として海外に流出する為に物価下落は起き難いです。
アメリカのように、資源量も多く且つ無駄使いが多い国では、稼いだ金を自国で回転させる為に、総分配(給料など)と物価が同期し易く安定的な経済成長を遂げます。但し、ここでも金融政策に傾き過ぎるとインフレ(通貨膨張)を起こし、膨らみ過ぎたバブルが破裂します。
・スタグフレーション:景気低迷時の通貨膨張(通常は物価が上昇する)。
例えば、政府が景気低迷を打開するために財政支出をしても、中抜きが横行し行くべき所にお金が廻らない場合は、消費が伸びずに通貨量のみが増加し通貨価値が下落(通常は物価が上昇)することからスタグフレーションが起こる可能性が有ります。
最近の日本の場合は、円高になると余剰資金が海外に流出し、円安になると輸入物価が上昇して、何れにしても国内経済を疲弊させます。また、日本の「GDPに対する貿易依存度」は30%程度(輸出15%、輸入15%)ですが、貿易収支がほゞ均衡している事から、GDPに占める貿易収支額は誤差の範囲と言えます。
GDP=民間支出額+企業支出額+政府支出額+(輸出額-輸入額)
つまり、円安で輸入価格が上昇しても輸出額が増える為に、日本全体では均衡がとれていて「物価上昇(個別価格ではない)」が起き難い経済構造にあると言えます。
現在の日本では、金融政策(市中の通貨量が増えるとは限らない)が主体で財政政策(確実に、市中の通貨量は増加する)が緩慢な為に30年間の経済停滞を招いたのですが、これは「日本は貿易立国」だとの思い込みが有るからです。
更に、コロナ禍以前には何を血迷ったのか「文系」が思いつきそうな「お・も・て・な・し観光立国」を目指し、しかも国内資本で開発するのでは無く、外資に日本を売り経済新興国並みにしました。
・経世済民:世を經さめ 民を濟ふ(国を治めて民を救う)。
「文系」ならば、経済の意味を理解してから政策に生かして貰いたいと思います。
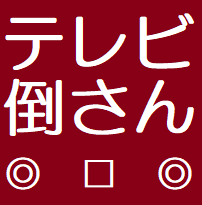
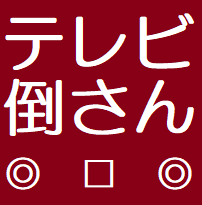










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます