グレゴリオ暦新年 あけましておめでとうございます
今日は「イエス・キリスト」が生後8日目の割礼と命名を受けた日とされているので、八百萬の神の一人である「耶蘇様」の命名日を神道でもお祝いする日です。仏陀に関してもお祝いしたいのですが「ガウタマ・シッダールタ」の誕生日が分らないのが残念です。但し分かっていても、お釈迦様の母親であるマーヤは出産後7日目に死んだので、生後8日目は「喪中」で祝うことは出来ません。
ちなみに、次の旧暦(天保歴)の元旦はグレゴリオ暦では今年の2月12日だそうです。「神道」には開祖も経典も無いので「宗教」ではないのですが、外来憲法(通称、日本国憲法)に詳しい学者の説では「宗教的」とされています。つまり、新暦(グレゴリオ暦)の元旦を祝う事自体が「和洋共に宗教的」なので、公務員が公務で正月行事を行うと「憲法違反」になります。旧暦の元旦は「科学的な自然現象(太陰太陽暦)」から算出されているので、護憲派にはお勧めです。
ところで、聞くところによると、「佛」の「弗」は「非」と同意文字だそうです。すると「佛」は「人に非ず」と云う意味になり、似た言葉に「ひとでなし」や「にんぴにん」が有りますが、これとの関連性は判りません。
「沸く」も良く考えると、「水に非ず」と理解すれば納得も出来ます。沸いている水は「気体と液体の境界域」にあり、「何れでもあるが何方でも無い」状態と言えます。つまり、「佛」は「人の昇華境界域」を意味し、「娑婆」から「極楽浄土」には未だ辿り着いていないのではないかと思われます。
「私」の「ム」自体に「私(自分)」の意味が有り、「禾(稲)」と「自分」で「個人(私)」が成立するらしいです。つまり、「佛」を簡略化した字である「仏」には、「人として簡略化された自分」の意味が有り、「ひとでなし」では無く、自分から無駄な部分を削ぎ落とした人を「仏」と書くような気もします。
「稲」は「斎庭の稲穂の神勅」により託されて日本の主食になったのですが、「佛」も「仏」も支那大陸で造られた文字なので、単なる「音写」であり然ほど深い意味は無かったのかも知れません。
「ほとけ」は日本語で「死者」の意味が有るそうです。「神道」では萬物に神が宿るので、死体が昇華すると神が分離し天に戻ると考えると、「佛」の字義と一致します。これが、日本で「葬式佛教」が受け入れられた理由の様な気がします。
また、人には全て本質的に「仏性(ぶっしょう)」が有るとされていて、これもまた「神道」とは融和性が有ります。ところが、「萬物に神が宿る」と言うと白い目で見られ、「すべての衆生が仏性を持つ」と言うと妙に納得する人が多いようです。
これは、一神教の「God」を「神」と訳した事が間違いのもとで、神道の「神」は寧ろ仏教の「仏」に近いと思います。
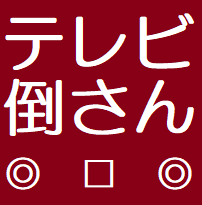
今日は「イエス・キリスト」が生後8日目の割礼と命名を受けた日とされているので、八百萬の神の一人である「耶蘇様」の命名日を神道でもお祝いする日です。仏陀に関してもお祝いしたいのですが「ガウタマ・シッダールタ」の誕生日が分らないのが残念です。但し分かっていても、お釈迦様の母親であるマーヤは出産後7日目に死んだので、生後8日目は「喪中」で祝うことは出来ません。
ちなみに、次の旧暦(天保歴)の元旦はグレゴリオ暦では今年の2月12日だそうです。「神道」には開祖も経典も無いので「宗教」ではないのですが、外来憲法(通称、日本国憲法)に詳しい学者の説では「宗教的」とされています。つまり、新暦(グレゴリオ暦)の元旦を祝う事自体が「和洋共に宗教的」なので、公務員が公務で正月行事を行うと「憲法違反」になります。旧暦の元旦は「科学的な自然現象(太陰太陽暦)」から算出されているので、護憲派にはお勧めです。
ところで、聞くところによると、「佛」の「弗」は「非」と同意文字だそうです。すると「佛」は「人に非ず」と云う意味になり、似た言葉に「ひとでなし」や「にんぴにん」が有りますが、これとの関連性は判りません。
「沸く」も良く考えると、「水に非ず」と理解すれば納得も出来ます。沸いている水は「気体と液体の境界域」にあり、「何れでもあるが何方でも無い」状態と言えます。つまり、「佛」は「人の昇華境界域」を意味し、「娑婆」から「極楽浄土」には未だ辿り着いていないのではないかと思われます。
「私」の「ム」自体に「私(自分)」の意味が有り、「禾(稲)」と「自分」で「個人(私)」が成立するらしいです。つまり、「佛」を簡略化した字である「仏」には、「人として簡略化された自分」の意味が有り、「ひとでなし」では無く、自分から無駄な部分を削ぎ落とした人を「仏」と書くような気もします。
「稲」は「斎庭の稲穂の神勅」により託されて日本の主食になったのですが、「佛」も「仏」も支那大陸で造られた文字なので、単なる「音写」であり然ほど深い意味は無かったのかも知れません。
「ほとけ」は日本語で「死者」の意味が有るそうです。「神道」では萬物に神が宿るので、死体が昇華すると神が分離し天に戻ると考えると、「佛」の字義と一致します。これが、日本で「葬式佛教」が受け入れられた理由の様な気がします。
また、人には全て本質的に「仏性(ぶっしょう)」が有るとされていて、これもまた「神道」とは融和性が有ります。ところが、「萬物に神が宿る」と言うと白い目で見られ、「すべての衆生が仏性を持つ」と言うと妙に納得する人が多いようです。
これは、一神教の「God」を「神」と訳した事が間違いのもとで、神道の「神」は寧ろ仏教の「仏」に近いと思います。
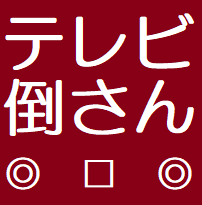










毎日読ませていただいております。
難解なものがあって、ボケ老人寸前のノラには容易に理解できないものがあります。
どの「いいね」を押すか迷うこと屡々です。その時は「グッド」か「パチパチ」をクリックしています。
数学は、特にへばりついて考えても、とっかかりさへ見つけることが出来ません。
そんなnoraですが、よろしくおねがいします。
私もボケ防止に、検索して、思い出しながら書いています。