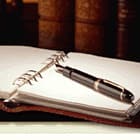
この夏休みに念願だった古典の名著を読み終えることができました。
学生時代ならいざしらず、社会人になると読書のできる時間が限られます。いかに効率読むかがポイントです。今回の記事は、そのコツを書きしるしておくものです。
・いきなり新刊を買わない
何巻にもわたる大作の場合、まずは図書館で借りてみましょう。最初だけ読んであわない、時間がないから読めなかった場合でも、本棚の肥やしにならず、後悔せずにすみます。それに古典はすでに著作権が切れていますので、新刊を買わなくとも著者に申し訳ない気持ちが立つこともありません。
・複数巻にするか、単巻にするか
古典文学はたいがい図書館では文学シリーズや、世界の名著等の分厚い単巻で読めるもの。しかし、二段構えになっていたりしますし、訳が古くさく固かったりもします。個人的には、複数巻ある、新訳の出ている文庫版がオススメ。光文社古典新訳文庫は、装丁がキレイで、かつ訳がかなりフラットなので初心者にはとっつきやすいです。
・事前情報を仕入れておく
映画でも小説でもそうですが。名作と呼ばれる作品はたいがいネット上で概説が出回っています。とくにわかりやすいのはウィキペディア。あらすじがとてもわかりやすく、ロシア文学のような名前が複雑なキャラが多く出る作品は、かならず一読しておいた方が無難。
・先に映像化や漫画化されたものを頼ってもよい
文字で読む前に、コミカライズされたものや映画、ドキュメンタリー、解説本などを参照してもOK! 私が参照したのは、100分で名著のサイトの解説でした。なお、松岡正剛などの識者のレビューサイトは骨太で読み応えがありますが、かえってそのサイトの感想文ばかり惹かれて読み始めてしまうので、要注意です。
・キャラクターの相関図を作成する
私のように和風のお話が好きな人間は、とにかくカタカナが苦手で、海外文学を敬遠しがち。まず、名前が覚えられない。なので、ネットでの事前情報などをもとに、あらかじめ登場人物のリストを作成しておくとよいでしょう。ちなみに想像力が豊かな人は、登場人物のイメージを膨らませて、絵にしておいてもいいですね。
・読書ができるまとまった時間を確保する
細切れ時間で読むと、どうしても流れがつかめないものです。休日のうち、せめて3時間ぐらいはまとめて集中できる時間が取れるようにスケジュール調整しましょう。そのあいだは、スマホや電話などもオフに。また部屋が散らかっていると集中できないので、片付けておきましょう。寝ころびながら読むと眠たくなるので、座ったほうがよいです。小休止をはさみながら、疲れないように。
・最初に巻末のあらすじを読む
海外の古典文学には、かならず訳者がわかりやすくあらすじを書いてくれています。とくに光文社古典新訳文庫は、各巻末のあらすじを読んだけで概要がわかり、しかも適度に見どころを引用してくれています。ドフトエフスキーの『罪と罰』『白痴』等を読んだときも大いに助けられました。
・大胆に飛ばし読みしてもいい
今回、私が読んだ『戦争と平和』は、光文社古典新訳文庫全六巻。ただし、二巻ぐらいめまではしっかり読みましたが、夏休み中に読み終えられない可能性があったので、三巻、四巻あたりの戦争の描写のところはかなりすっ飛ばして読みました。逆にピエールやアンドレイ公爵などの主要人物が意識転換して、生の喜びに目覚めたり、人生を変えるような大きな出会いがある場面はしっかり熟読。こうしたターニングポイントな部分は、たいがい巻末のあらすじで訳者がしっかり解説してくれて、しかも、どこの章の、どの編の、どの節かまで指示してくれているので、その場面へジャンプしていくこともできました。
・読書メモをとりながら読みすすめる
拾い読みするとはいえ、点と点とを頭の中でつないでいくのはなかなか難しい作業。キャラクター相関図を地図として、ときどき、メモをとったり、抜き書きしながら内容をざっくりまとめていくと理解が早まります。とくにあとで感想を書きたかったり、全体を読みなおしたくはないが、どんな話か振り返りたいときに、このメモが役立ちます。
・作品が気に入ったら、同著作や関連作にも手をのばす
いったん一作の虜になったら、その作家のファンになり、著作全てを読破したくなるのが読書ヲタク。また、著者が影響を受けたという作家や、注釈で引用されたものの出所を調べたり、好奇心で読書の幅が広がります。ただ、広げ過ぎて手付かずになりやすいので、気をつけましょう。
長編モノの攻略のポイントは、律儀に読了することにこだわらないことです。
学者さんや翻訳者ならば、言葉の妙を味わうためにじっくり読むでしょうが。一般人読者は雑読みで読んだことにしてもかまわないのです。大事なことは、時間をかけて読書したことよりも、そのキャラの動きを通じて読者が何を学び、それを自分の人生に活かせるかなのです。
このトルストイの大作は、かねてから名作の誉れ高いこともあってか。
挑戦して良かったと思えるような読後感がありました。引用して、手帳に書き留めて、人生の迷ったとき、他人を信じられなくなった時に読み返したい。そう思えるような教示がたくさんありました。
学生時代の高慢ちきな時期に読んでいたら。きっとこの文学の神髄を理解しないまま、ただ、読み終えたことを功績にするだけのインテリぶったえせ読書家になっていたことでしょう。
(2022/08/14)





























