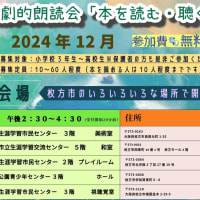今回の内容は、あらすじと登場人物(もちろんsolitudeシリーズなので一人です)と作者クスキユウ氏の後書きです。
<あらすじ>
劇場に入ると、劇団の稽古場のようなところで、俳優が一人座っている。開演時刻になったのか“前説”を始め、急にチェーホフ「ワーニャ伯父さん」のセレブリャコフを演じたり、かと思うと入院中の苦労話を観客相手につらつらと話し始める。彼は話しながら、演じながら歩き回る。ぐるぐる、ぐるぐる・・・と。
<登場人物>
“剤の効き目か? 効くならばしっかり効け。”
入院と手術を機に声の不調に苦しんだ俳優。現在は劇場で、チェーホフの短編「煙草の害について」をモチーフに描いた戯曲を上演中。見えざる“死”と対峙しつつ、今まで演じたキャラクターと対話し、無事に本番を迎えるまでが描かれた、ドキュメンタリーに見せかけたオートフィクション形式の物語。
妻がおり、姉が一人いて、その息子、つまり甥と土地を巡って若干の係争中。娘が離れた所に住んでいるが疎遠ではなく、入院していた時には見舞いに来てくれ、そこまで孤独なわけではない。
尾崎放哉、小林一茶の俳句などをよく引用し、聖書にも造詣が深い。今までシェイクスピアを始め、チェーホフやブレヒトなど多彩な役を多様な発話で演じてきた。「桜の森の櫻守り」という現在上演中の戯曲作者が書いた絵本の読み聞かせを児童館などでやっている。
<作者あとがき>
画家の宮崎智晴氏の「荒れ地のさくらもり」という作品を見て、その絵一枚の絵本を作ろうと文を書いたことがありました。
京都の俳優、氏田敦さんの入院日記を読ませていただき、今回の作品にしようと思いました。この二つがヒントになっています。
今回の主人公は俳優で、人前で話すのですが、その中でもチェーホフの台詞を引用して話します。入院の話をするのですが、どちらかといえば、あまり関係のない話、奥さんとかお姉さんとか娘さんの話をします。その中で、日本人には、いや普遍的に人々にはありがちですが、本音ではなかなか話せない。いやむしろ台詞に託した方が感情を放ちやすい。そんな気がしてきました。
いつしか、台詞が本音なのか、普段の会話が台詞なのか、どちらなのか分からなくなる。実際、私は極度の人見知りで、基本的に人と会話するときは、本当にセリフを考えています。考えないで喋るときにはかなりの高確率で失言して怒られます・・・。
“演じる“と言うことを普段からやっているので、俳優って台詞の方が本音を出しやすかったりするのかなあ、と言う想像で書きました。つらつらと他愛のない、些末なことを話すことで、主人公の狂気というよりは本気、本当のところが染み出していかないか、と思いました。
やはり、コミュニケーションという私の問題意識が強く出た作品になったと思います。
さて、なぜさくらもりか。私は演劇って桜のようだな、と思ったのです。数日のうちに散ってしまう、でもその間はものすごく人々に愛でられ、魅了する。やがて消えゆく運命にあるのに、でもそれを丹念に時間をかけて、労力をかけて創り出す、そうした作業がさくらもりに通じるなあ、と感じるのです。
普段、私は永遠に生きる前提で生活していますが、それでもやはり死というものを考えたり、今現在は治らない病気にかかったりすることを考えると、桜の散りざまを人の一生に見立ててしまいそうになります。
俳優もまた演劇作品というはかない桜を守ってきた人なのではないでしょうか。
クスキユウ
『ぐるぐる―countless traces—』(氏田敦『入院メモ』より)
“ぐるぐる、てくてく。よりみち、まわりみちして、歩いてく。”
作:クスキユウ 演出:松浦友 出演:氏田敦(劇団冬芽舎)
“思いもよらないことがいつ誰にでも起きる”
入院と手術を機に声の不調に苦しみ、見えざる“死”と対峙する俳優。
今まで演じたキャラクターと共に闘い、無事に本番を迎えるまでを、チェーホフや聖書、また尾崎放哉、小林一茶の俳句などの引用と共に上演。
演じること、生きることの本質を、多様な発話によって表現する。
2022年5月14日(土)16:30開演 (第39回5月祭参加)
(開場は15分前、上演予定時間20分)
<会場>枚方市立楠葉生涯学習市民センター3階視聴覚室
〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木2丁目29-5
<アクセス> 京阪樟葉駅から東へ800m:徒歩約10分
京阪バス、あさひバス停 徒歩約2分
<参加費>500円
高校生以下無料(要学生証、小学生以下は保護者同伴が必要)
最近の「プロデューサーズボイス」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事