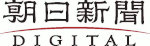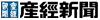電通過労自殺問題をきっかけに、「ブラック企業を許すな!」という声が、日本でますます大きくなっている。ブラック企業の話になると、「企業体質」の問題に焦点が当てられることが多い。長時間労働や、パワハラ上司の存在が当たり前になっているという話だ。しかし、ブラック企業の問題は、それだけではない。サービスを受ける「お客」側も、労働環境の悪化に一役買ってしまっているのが、現状だ。こうした指摘をする、ある会社員の次のようなツイートが、2万6000回以上リツイートされている。
ブラック企業をなくしたいなら、社員にまともな賃金を払っている、適切な労働時間を働かせていることによって生じる不便さに寛容でないと。「土日休みなんで納品までにもっと時間かかります」「定時過ぎたんで会社もう閉めました」と言われて文句言う人は、言ってみれば「ブラック市民」ですよ
過剰なサービスを要求する「お客様」
あなたも、理不尽な要求をする客にうんざりしたことはないだろうか? 私は以前、家具の販売員として働いていたが、過剰なサービスを要求する客は必ずいた。例を挙げると、次のようなものだ。
「雪が降っている影響で、家具の配送に時間がかかる」と言えば、「値引きしろ!」。「もう閉店時間だから」と言えば、「少しくらいかまわないだろう!」。
これはまさに、ブラック企業ならぬ、「ブラック客」だ。日本ではいつだって、カネをもらっている側の人間は、圧倒的に立場が弱い。なぜ、このような客の振る舞いが許されてしまうのだろうか。
日本のサービスは、「おもてなし」という言葉で表される。大辞泉によれば、「もて成す」とは、「心をこめて客の世話をする」ことを意味する。しかし、心を込めて客の世話をするという意味を、現在は一方的な奉仕をすると理解され、「お客様は神様」の状況になっている。客の立場が異常に高く、サービス提供者がへりくだるという、歪んだ関係だ。
そもそも、神とは、人知を超えた絶対的な存在で、信仰の対象をいう。人々は昔から、人間の力ではどうにもできないものを「神の仕業」「たたり」として恐れ、敬い、あきらめ、受け入れてきた。凶作になったとしても、神を責めることはない。「自分たちが悪かったから、罰が当ったのだ」とせっせと生け贄を捧げたり、祈ったりしていた。
この理屈をサービスにも当てはめると、客が傍若無人な振る舞いをしても、決して反論したり、拒否しないということになる。まるで自分の気持ちや時間を生け贄に捧げているようである。そして客側もそれに慣れてしまったため、「思うままに振る舞ってよい」と勘違いしてしまったのではないだろうか。そう考えると、日本の「お客様」は確かに「神様」のように扱われており、対等な関係とは程遠い。
客に茶を振る舞う、もてなしの作法の中から
一方、「おもてなし」に対して、少し違った見方もある。城西国際大学観光学部助教の岩本英和氏が、国際学術文化振興センターに所属する高橋謙輔氏と共同で発表した「日本のおもてなしと西洋のホスピタリティの見解に関する一考察」という研究レポートでは、おもてなし精神を理解するため、茶道を引き合いに出している。そこでは、「亭主は、客のために一身に濃茶を練り、その心を感じ取った客は心から感謝の気持ちを礼に込める」と書かれていた。
つまり「おもてなし」とは、まず客を思いやる気持ちがあり、客もその厚意を感じて感謝する、「互いに心地よくなるための心遣い」であったということだ。「おもてなし」が「互いが心地よくなるための心遣い」であったことを考えると、現在の不平等な客とサービス提供者の関係は、その精神とは真逆に位置している。
なぜこんなにも客の立場が上になってしまったのだろう。さまざまな要因があるだろうが、他社に負けないように、「サービス」という付加価値で勝負しすぎる傾向が強いことが原因ではないだろうか。値下げや品ぞろえでの差別化には限界がある。そこで、精神論でどうにかなる「サービス」で競争を勝ち抜こうという発想になるわけだ。空気を読むことに長けている日本人にとって、サービス精神を持つこと自体は難しいことではない。だが問題は、この状況を当然だと思ってしまった「お客様」の意識だ。
「過剰サービスを当然だと思う発想」を助長するものとしては、どこにでもあって、24時間営業が当たり前になっているコンビニがいい例だろう。30年ほど前は、お盆や年末年始は営業していない百貨店が多かったが、数十年で「年中無休が当たり前」になった。
かつては商店街でしか食材が手に入らず、夜は店が閉まっていたが、その不便こそが「普通」だった。「労働環境の改善により不便になる」という指摘も一理あるが、この感覚こそ、客が当然だと思って要求する過剰サービスの厄介さだ。それが過剰なサービスであっても、もう「当然」になっているため、当たり前のように要求する。店が閉まっていれば「不便だ」と言うくせに、店が開いていることに感謝しない。いくら企業が労働環境を改善しようとしても、過剰なサービスを求める客がいれば、労働者は仕事を終わらせることができない。ブラック企業をなくすためには、そういった悪意のない「ブラック客」の意識改革が必要だ。
「ブラック客」の目を覚まさせるためのいちばん有効な手は、サービス提供者がノーをたたきつけることだろう。欧米では、過剰なサービスを要求する客を、「客ではない」と店が拒否する。
ヨーロッパ旅行をしたとき、日曜日に店がすべて閉まっていて驚いた、という経験をお持ちの方も多いのではないだろうか。筆者が住むドイツでは、閉店法という法律により、店の営業時間が規制されている。キリスト教では日曜日が安息日と定められているので、「日曜、祝日は閉店」が基本だ。また、労働者の休息時間を守り、小売店の営業時間延長による競争を阻止するため、「月曜日から土曜日までの小売店の営業時間は、6時から20時」という決まりが守られていた。
ただ、2006年には、閉店法の権限が国から州に移り、その後は各州で規制緩和が続いた。現在は16の州のうち、9つの州が月曜から土曜、3つの州が月曜から金曜の24時間営業を認め、14の州が年4回、またはそれ以上の日曜日の営業を認めた。しかし、法律改正後、ドイツ人は喜んで、店の営業時間を長くしたかというと、そうではない。今でも多くの店で、24時間営業や日曜営業は行っていない。フランクフルト中央駅には、スーパーとパン屋が合計17店舗入っているが、24時間営業しているのは、2軒のパン屋だけだ。
自分も休めば、他人にサービスを要求することはない
フランクフルトの中心街にある、ドイツの2大デパートのうちのひとつKaufhofは、月〜水が9時半から20時まで、木〜土が9時半から21時までで、日曜は休館。もうひとつのKARSTADTは、月〜土の10時から20時までの営業で、同じく日曜休館。ショッピングセンターのMyZeil、Skyline Plazaは月〜水が10時から20時まで、木〜土が10時から21時まで営業、同じく日曜は休みだ。フランクフルトにある4つの巨大商業施設でさえこの営業時間なのだから、あとは推して知るべしだ。日曜や深夜にどうしても食料品が必要になったら、大きい駅の構内の店か、閉店法の規制から外されているガソリンスタンドに行くしかない。
一見不便に思うだろうが、ドイツ人は深夜や日曜に買い物をする習慣がないので、大して気にしていない。「なぜドイツ人は店が閉まっていても気にしないのか」といえば、「自分も休んでいるから」の一言に尽きる。ドイツには「深夜や日曜日は休むべき」という価値観が前提としてあり、自分自身が休んでいるのだから、他人に「働け」とは言わない。店が閉まっているのなら、前日に食料品を買って家でのんびりしていればいいのだ。
それでも「店を開けろ」「働け」という客には、はっきりとNOを突き付ける。ドイツだけでなく、欧米では客にNOと言うことが許される。だから対等な立場でいられるのだ。客の要求を拒否することは、サービスの質を下げることではない。労働者を守るために必要なのだ。
日本の「お客様」は、自分の立場が上で、過剰なサービスも当然だと思ってしまっている。だがサービス提供者がNOと言えば、「この要求は過剰なものだった」と気づくのではないだろうか。日本でも、極端な話、コンビニのオーナーたちが口をそろえて「営業時間は10時から18時」と決めてしまえば、客が泣こうがわめこうが、18時に店を閉めればいい。客がサービスに感謝し、サービス提供者の目線に立つことができて初めて、日本ご自慢の本当の意味での「おもてなし」になる。客が相手を思いやる気持ちを持てれば、労働環境も少しはマシになるだろう。
ブラック客が増えている背景には、便利に慣れすぎていることもあるけど、ストレス社会のはけ口的なものもあるんだろうかねぇ。