
「兵庫」と呼ばれるのは、なんで


兵庫県の名称は、
現在の神戸市兵庫区辺りを指す「兵庫」という地名に由来しています。
兵庫には、「兵庫津」と呼ばれる港(現在の神戸港の一部)があり、
幕末にはアメリカやその他の国々と貿易を行うための開港場として指定されました。

明治政府発足後の慶応4年(1868)、兵庫には、周辺の旧幕府領を管轄する
兵庫鎮台が置かれましたが、この兵庫鎮台は、間もなく
兵庫裁判所と改称され、さらに同年5月23日、兵庫県となりました。
このように役所が置かれた地が兵庫にあったからと推測されます。
それではなぜ「兵庫」(ひょうご)と呼ばれるのでしょうか?
「兵庫」の地名については、かつて兵器の倉庫が、そこに置かれていたために
名付けられたのではないかとも考えられますが、よくわかっていません。
「兵庫」は「武器庫」の意味で、大化の改新の際、摂津国境の播磨関を守るため、
武器を収める庫として設置された「兵庫(つわものぐら)」に由来する説がありますが、
もう一説として、阪神地方に古称である、武庫(むこ)に由来すると言う説もあります。
これは、奈良時代より前は、現在の武庫川の川口付近に、武器が集められた庫があり
兵庫県の中心であった、その後中心地は神戸側に移り、武庫の湊となったが、
それが転じて兵庫の湊となり、兵庫の地名はここから生まれたと言われている。
ただし、「兵庫」という地名は史料では、長治元年(1105年)の古文書
「橘経遠寄進状」に記された「兵庫庄」という荘園名で初めて見られます。
近隣には古代より瀬戸内海水運の重要拠点となっていた大輪田の泊(おおわだのとまり)
がありましたが、鎌倉時代になるとここが「兵庫津」と呼ばれるようになっていきました。

しかし、気ままなオジンの私としては、兵庫の地では古来より「源平合戦」や
「湊川の合戦」以来たびたび大きな合戦があったことから、兵士(戦士)が
集められた場所「兵どもの集合所」であったのではないかと勝手な空想をしている。

兵庫津のキャラクター「清盛くん」
当サイトに掲載の画像及び説明文などの無断転載はお断り致します。
Copy Right (C) 2010 653yamanet. All Rights Reserved
Copy Right (C) 2010 653yamanet. All Rights Reserved

















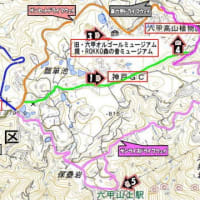

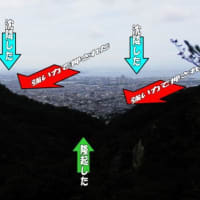
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます