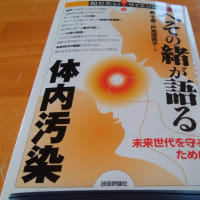― 自給生活 その1 ―

(これが人間かー)
サトイモを保存用の穴に埋めながらこう考えた。10本しかない。もっと作っておいた方がよかったのではなかろうか。
近所に80半ばのばあちゃんがいて、終戦直後の話をしてくれたことがる。当時はひどい食料難で、東京の人間は食べるものに不自由していた。それで、着物や金目のものをリュックにつめて大勢列車でやってきたという。
食べ物が欲しければお金を持ってくればいいと考える。ところが当時はお金の価値がひどく下がっていた。つまり、モノの値段が上がっていた。
たとえば、終戦直前の昭和20年4月、ハガキは5銭で買えた。2年後の22年4月には50銭にはね上がった(「ダイヤモンド」第36巻9号 昭和23年3月11日)(1銭=100分の1円)。
ばあちゃんにしてみたら、(当時ばあちゃんは子供だったろうから、農家の嫁にしてみたらとでもいうべきか)そんな紙くず同然のお札をらったところで迷惑だ。着物か指輪がいい。こういう時農家の嫁は俄かに目利きになる。「いい指輪してるね」なんてこと言ったかもしれない。東京の人間の方は、「だからなに?」とは言えない。
指輪は知らないけど、「今でもタンスの中には着物がいっぱい詰まっている」と言っていた。
イモがすぐ前の畑にあれば、せっせとお金を稼ぐ必要もなくなる。お金なんて所詮イモを買うための手段だ。着物や指輪もいらない。
終戦直後こんなことになったのには訳がある。
訳はともかく、“ ゆく河の流れは絶えずして ” などといかにもワケ知りのような顔をして来し方を見、行く末に備えようと思えば、自分の行きつく先はまずイモになる。
( 次回は ― 自給生活 その2 ― )