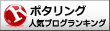2021/5/22(土) 曇/晴
梅雨入りのこの頃、今回のポタリングも中三日となった。今日は午前中10時出発、目的地は、南関町関町の熊本県指定天然記念物大津山下ツ宮の椋と、和水町の熊本県天然記念物山森阿蘇神社の樟とする。
先ずは、南関町関町の大津山下ツ宮の椋(写真1参照)を観る。

相当の老木(写真2参照)である。近所の方のお話では、「私の子供の頃は、木に登って遊んでいた。大きく枝張りしていて樹も大きかったが、現在は小さくなってしまった。」とのことでした。

説明板(写真3参照)では、「かって、この地祠堂があったので、ここ南関第一小学校の校地を今も堂の前と称しており、この椋の木は神木とされている・・・椋の木としては県下屈指の巨木であり・・・幹のひだにキセルガイが棲息している。
宝永3年(1706)南関の関所役人井沢長秀が著した「南関紀聞」に、天正(1573~1591)の大津山家稜時代の祭礼の様子がでており、本宮大津山神社から、ここ下ツ宮まで神輿行列があり、ここが御旅所になっていたことがわかる。したがって、この椋の木は天正年間まで南関を治めた大津山氏時代から、下ツ宮の神木であった。このことから樹齢も500年前後と推定される。」とある。

大津山下ツ宮の椋の木を後にして、和水町山森阿蘇神社(写真4参照)に移動する。
鳥居扁額は、阿蘇五宮とある。

立派な楼門(写真5参照)がある。

石段を上ると広い境内と社殿(写真6参照)がある。

由緒書(写真7参照)によると、「御祭神は、阿蘇本宮五の宮阿蘇惟人命。
神社の創立、社伝に土御門帝の御代正治二(1200)年十一月四日坂梨弥吾助翁が本宮より御分霊を奉戴して当地に来たり斎き奉り自ら祭祀を司る爾来凡そハ百年連綿として子孫後継して現在に至る・・・」とある。

目的の熊本県指定天然記念物の樟(写真8参照)は、境内東南方向の斜面にある。

鳥居横から見る樟(写真9参照)

楼門横から見上げる樟(写真10参照)

説明板(写真11参照)には、「・・・推定樹齢800年・・・正治2年(1200)に阿蘇家の家臣である坂梨弥吾郎が、この地に下向して祀ったことが始まりであると伝わり、この大クスは神社とほぼ同じ年数をこの地で過ごし・・・」とある。14時半前、帰途に就く。

帰宅は17時、今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)47km→高瀬裏川38km→熊本(自宅)
所要時間7時間(実6時間) 総計85km 走行累計40,845km