たまにはボブ・ディランのことを書こう。
私にとってはあまりに大きい存在なので、大きさゆえにあまり軽々しく書けなかったのだが、やはり書いておこう。
最近、「ドント・ルック・バック」の日本版DVDも出たことだし、ちょうどいいタイミングかもしれない。
ディランの魅力というと、たいがいはその歌詞をあげる人が多い。
また、その歌い方の味についても触れる人はいる。
だが、気のせいかもしれないが、彼の作るメロディラインについて触れられた記事って、少ないと思う。
確かにその歌詞の魅力は大きいのだが、その歌詞が載せられてるメロディも実はすごく魅力があるんだ。
実をいうと、私がディランを聴いて最初に何が好きになったかというと、まず、そのメロディだった。
まずメロディの良さに惹かれ、次にその歌い方に影響を受けた。で、歌詞に惹かれたのはその後だった。
レコードを聴くようになってしばらくしてから「ボブディラン全詩集」という本を買い、あらためてその歌詞の意味を知り、唸ってしまった。
でも、それでメロディが歌詞の素晴らしさにかすんだかというと、全然そんなことはない。
やはり私にとっては、彼の作り出すメロディは魅力的だった。
けっこうディランのメロディに潜在的に惹かれた人は、私以外にも多いのではないだろうか。
拓郎も、そういうことを昔ラジオで言ってたことがある。
そういや、拓郎の「イメージの詩」は「廃墟の町」の雰囲気に似てるし、「イメージの詩」にでてくるハモニカのメロディは、ディランの「時代が変わる」というアルバムに入っていた「船が入ってくるその時」のボーカルメロディと似ている。
また、拓郎の「金曜日の朝」の出だしのメロディは、ディランの「ナッシュビルスカイライン」に入っている「今宵は君と」の出だしに似ている。
又、拓郎の「春だったね」はディランの「メンフィスブルースアゲイン」からヒントを得ているはず。
こう並べてみると、拓郎はディランからは歌詞よりもメロディやサウンドの影響を受けている部分が大きいと思う。
で、それも当然と思わせる魅力が、ディランのメロディラインにはある。
初期の彼は、トラディショナルミュージックのメロディを借用することが多かったようだ。
たとえば「風に吹かれて」も、その中の1つと言われてる。
また、先輩シンガーのメロディをうまく自作に取り入れることも多かったようでもある。
たとえば「くよくよするなよ」がそうであるといわれている。
でも、そういうのを手本にして、彼は自分のメロディラインを確立していった。
で、確立されていった彼のメロディラインは、親しみやすいものだった。
いくら歌詞が素晴らしくても、いくらサウンドが革新的だったとしても、それだけじゃ今の地位に到達することはなかったはずだ。
今の地位を確立したのは、歌詞の素晴らしさに負けないくらいの作曲の才能を彼が持っていたからだ。
本人は「僕はメロディ作りはあまりうまくない」と言ったことがあるが、それはあまりにも歌詞が凄すぎただけであろう。
でも、彼の作曲の才能もまた並外れたものであったということを、私は確信している。
歌詞が凄いだけだったら、ミュージシャンとしてここまで生き残ってはこれなかったと思う。
作詞、作曲、歌唱表現力、そのどれもが卓越していたからこそ、今がある。
また、その生き方に、人から共感を覚えられたり憧れもされたりしてきたからこそ、今の地位があると思う。
歌詞だけで彼を評価したら、それは彼の一部分にしか過ぎない。
ボブ・ディラン。私の憧れの人。
いくら近寄ろうとしても、近寄れない。
やはり・・・とんでもない人なのだ。
私は「だんぞうさんの作る曲のルーツって何ですか?」とか「誰の影響をだんぞうさんは一番受けていますか?」と聞かれると、私はディランの名前をあげることが多い。
十代の頃は、彼の真似をしたような歌詞を書いてはみたが、第3者から見たらその歌詞は「ただの意味不明、もしくはくだらない」にしか受けとられないことが圧倒的に多く、それ以来そういう作風はやめるようになった。
だから、今のだんぞうはディランの影響を受けてるようには見えない・・そんな印象を持つ人は多いみたいだ。
でも、そうじゃないんだ。根っ子の部分では、ちゃんと(?)影響受けてる。
それも、かなり。相当。
あえて言うなら、ディランの影響は今の私にとっては、精神的な部分が大きい・・と言い換えられるかもしれない。
それでも、音楽的な面に関していえば、私は彼のメロディには影響を受けてるんじゃないかと自分では思っているのだが.・・・どうであろうか。










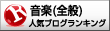

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます