
今でこそJリーグなどのおかげで、日本でもサッカーは特に人気の高いスポーツになっている。
その人気は野球といい勝負だろう。
テレビ中継がある試合もあるし、なにより国際試合でのサッカーの注目度は野球以上かもしれない。
だが、その昔・・・・まだサッカーのプロリーグなど夢の夢だった時代もあった。
そんな時代にも、スポ根(スポーツ根性もの)ジャンルの人気もあって、サッカーコミックはあった。
当時の代表的な作品はなんといっても「赤き血のイレブン」だったろう。
アニメ化もされたほどだ。
今ではサッカーコミックといえば、「キャプテン翼」が代表格かもしれない。
だが、まだまだ日本のサッカーが今ほどメジャーじゃなかった時代のサッカーコミックの代表格的な存在は「赤き血のイレブン」だった。
原作は梶原一騎さん。
作画は園田光慶さん。ただし、作画は後半は深大路昇介さんにバトンタッチした。
そのバトンタッチの理由が気になるが、真相は私には分からない。
深大路さんの元々の画風は私はよく知らないが、少なくても「赤き血のイレブン」に関しては、前任者の園田さんの画風を、懸命に似せようとしていたのは、読んでてよく分かった。
私はこの作品は連載版では読んでなく、単行本でまとめて読んでいた。
単行本で読んでても、漫画家交代によるいきなりの画風の変化にはとまどったが、毎週連載版を読んでた読者にとっては、もっと驚きだったろう。
連載されていたのは、確か少年キングだったと思う。
ちなみに、梶原一騎さん原作の作品では、他に「空手バカ一代」という作品が、途中で漫画家の交代があったようだ。
もしかしたら原作者と漫画家の意見の相違があったのか、それとも別の理由によるものなのか、今となっては知りようがない。
「赤き血のイレブン」には、登場人物たちにはしっかり必殺技があった。
例えば「巨人の星」には「大リーグボール」があったように。
「柔道一直線」には「二段投げ」などがあったように。
「赤き血のイレブン」には、「サブマリンシュート」「ブーメランシュート」「スクリューシュート」「カミソリドリブル」「フォークシュート」などの必殺技があった。
これらは、野球マンガで言えば「魔球」的な存在であった。
このうち、主人公の玉井真吾の必殺技が「サブマリンシュート」であり「ブーメランシュート」だった。
梶原一騎先生の生みだすスポ根作品には、精神論と共に、荒唐無稽的な必殺技はつきものだった。
というか、そういう必殺技は、作品の「売り」でもあった。
たいがい、そういう必殺技をあみ出すために、主人公はど根性によって必死の努力で特訓をする。
そして生まれた必殺技は一時無敵になる。
だが、主人公には必ずライバルがいて、そのライバルたちも必死の努力で主人公に対抗できる必殺技を生みだしてきたり、あるいは主人公の必殺技を撃破したりする。
そして、主人公とライバルたちはそれぞれ相手に勝ったり負けたりをくりかえしていく。
そんなパターンが王道であった。
そういう必殺技は、とうていリアルな世界では実現不可能だったが、見ていて面白かった。
私も熱中した覚えがある。
とはいえ、熱中しながらも、ツッコミ所も考えるようになっていた。
玉井真吾のサブマリンシュートは、「赤き血のイレブン」の中では、個人的にはもっとも印象度の高い必殺シュートであった。
これは蹴った後に主人公が後方に半回転する態勢になるのが特徴で、蹴ったボールは、キーパーの前でググッと沈む魔球・・・ならぬ魔シュートであった。
一時無敵だった気がするが、相手に研究されるようになり、蹴った後にバックに半回転する態勢になるのを防がれるようになった。サブマリンシュートを撃つには、そういう蹴り方をする必要があったようだった。
もっとも、やがては玉井も、相手がそういう仕草をしてきたら、サブマリンはフェイントで蹴らなくなったりしていった。
まあ、そんな展開があった。
当時はこれだけでも、そのかけひきも面白く見ていた。
当時はそれでよかったのだ。サッカーというスポーツは学校の体育の授業の中にもあったし、それなりに人気もあったので、おおまかな捉え方としては知ってはいた。
サッカーの奥深さや戦術、世界レベルの試合での展開もよくわからず、楽しんでいた。
単に、必殺技と、それに対するライバルたちのからみを、「巨人の星」などと同じような感覚で楽しんでいた。
だが、サッカーのプロリーグができ、サッカーそのものへの関心が全国的に上がり、国際試合などの緊張感あふれる大舞台の試合をテレビで見れるようになると、かつて熱中した「サブマリンシュート」へのツッコミどころも見えてくるようになった。
たとえば、サッカーのワールドカップのような大舞台での試合を見ると分かるが、例えばシュートを撃つ時などは、一瞬一瞬のミクロ的なチャンスに撃つしかない。
なにせ、敵チームは必死に、シュートを撃たせまいとして邪魔をしてくるからだ。
野球のように、例えば決め球を持つ投手と、それに対抗するライバルとの一対一の勝負の局面で時間などかけていられない。野球で魔球を投げる時は、それ用の球の握り方をして、それ用にひねり、さらにそれ用のピッチングフォームもあったりする。
それは、投手と打者が対戦する時、1対1の空間になるからだ。ピッチングフォームや投げ方の邪魔をする敵はいない。
だが、サッカーの流れの中でシュートを撃つ時は、一連の流れの中で、ある意味どさくさの中で一種の隙をついて撃ったりする。
そんな時、シュートを撃つのに、態勢を整えたりしている余裕などない。
むしろ、どさくさの展開の中で、いかに態勢を崩しながらも撃てるか、本来の撃ちたい形とはかけ離れた状況の中でも、決めることが出来るか、どうか・・が大事だったりする。
そんな時に、撃つのに一定のフォームが必要になる魔シュートなど、撃ってる余裕はないと思う。
いかにサブマリンシュートがすごくても、それを撃つのに必要な態勢など整えてられないだろう。
サブマリンシュートみたいな魔シュートは、PKの時ぐらいしか撃てないと思う。
PKの時は、蹴り方を敵が邪魔してくることはない。
だが、通常の流れの中では、フォームに制約のある魔シュートは、中々無理だと思う。
それが現実だと思う。
ただ、現実でのプレイでは、蹴ったボールが大きくカーブしてゴールに突き刺さることはよくある。
日本でも例えば中村俊輔さんのフリーキック。すごいのは、一瞬のミクロなタイミングでもああいう軌道の球を蹴れるのは、ある意味コミック的な凄さ(もちろん、良い意味で)。
そんなことを考えれば、今の日本のサッカーは、「赤き血のイレブン」が描かれた時代のコミックを超えるレベルに達しているのだろう。コミックは、当時の日本のサッカーをはるかに超えるプレイを描いていたような気がするから。
赤き血のイレブンの時代に、巨人の星のような「消える魔球」が出てきていたら、まあ、これはコミックで描かれたサッカーを、現実のサッカーが追い抜くのは永遠に無理だろうけど(笑)。
さすがに「赤き血のイレブン」にも消える魔球・・ならぬ「消える魔シュート」は出てこなかった(笑)。
それとも、何かのサッカーコミックに、「消える魔シュート」は出てきたことがあるのだろうか。
ともあれ。
「赤き血のイレブン」は、今では浦和レッズのキャッチフレーズとして、親しまれている。
それは、「赤き血のイレブン」の主人公である玉井真吾の所属していた高校が、浦和の高校だったという設定ゆえであろう。
「赤き血のイレブン」のメイン舞台のモデルとなったのは浦和であったことを考えれば、浦和レッズのキャッチフレーズが「赤き血のイレブン」であることには、個人的に違和感がないどころか、ピッタリだとは思う。
かつて私がコミックやアニメで好きだった作品「赤き血のイレブン」が、こういう形で残されているのは、なんとなく嬉しい。
かつての名作サッカーコミック「赤き血のイレブン」は、浦和レッズを通して、今でも現役なのだ。
少なくても、この存在や作品名は。
ところで・・「キャプテン翼」や「浦和レッズ」が好きなサッカーファンに、「赤き血のイレブン」は読まれているのだろうか。
案外、「赤き血のイレブン」は、そのタイトルは有名でも、実際には今となってはあまり読まれていないような気もするのだが・・。
もし今後この作品を読まれる方は、この作品は「キャプテン翼」とはだいぶ傾向の違う作品であることは、頭に入れて読んでほしい気はする。
相当荒唐無稽ではあるが、少なくてもこの作品が日本でのサッカーコミックのパイオニア的な作品のひとつであったことは間違いない。










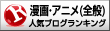

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます