


移植に当たって最近ドラムブレーキの整備シーンを書き直したので、ついでにドラムブレーキの画像うp。
正確にはここにドラムという蓋をかぶせるのですが。
半円状に金属板、ブレーキシューの動きの支点になる側、このブレーキはリーディング・アンド・トレーリング型なので前後とも下側ですが、支点に固定される側をヒール、ピストンの動きで外に動く側をトゥと呼びます。
ドラムは真ん中の円形の部分、ハブから突き出したボルトが貫通する穴が開いており、ハブの動きに合わせて共廻りしています。
で、半円形のシューが外側に押し広げられて、ドラムの内側に押しつけられることで制動するわけですね。
二枚目の画像はオートアジャスターの拡大画像ですが、ギザギザになった部分がラチェット機構です。ギザギザの部分は直角三角形の様な片側が垂直になっており、一方向へ回転するときはスムーズに動きますが逆方向に回転させようとすると引っ掛かって回らない様になっています。
オートアジャスターは3ピース構造になっており、雌ねじを切られたシューストラットと牡ねじを切られラチェットギアを持つアジャスターボルト、アジャスターボルトを自由に回転させるためのフリー構造のピース(名前知りません)からなっています。
アジャスターボルトが緩め方向に回転するとシューストラットから抜けて行き、結果としてアジャスター全体の全長が伸びていきます。
両端はシューの金属部分の内側に固定されているため、全長が伸びるとシューが内側から押し広げられることになります。
これを用いて、シューとドラム内側の隙間を詰め、摩擦材の摩耗による隙間の広がりにある程度対応するわけですね。
でも、ラチェット機構では一定の角度回転しないとラチェットが次の歯に移らないので、これでシューとドラムのクリアランスを一定に保てるわけではありません。なので、車検なんかの際には手動でのクリアランス調整が必要になります。
だいたいですが、足踏み式や手で引き起こすタイプのサイドブレーキの場合、タイヤをつけずにドラムを直接手で回した場合に二ノッチ引いて回転が重くなり、三ノッチ引いて完全に廻らなくなる程度に調整すれば車検は通ります。後輪駆動車の場合は、ディファレンシャルの回転の抵抗が加わるんでちょっと判断が難しいですがだいたい同じです。シフトをニュートラルにすると判断しやすいです。


ちなみに調整が楽なのはスズキとかダイハツで、アジャスターの構造が違うので調整にあまり手間がかかりません。延々ラチェットを廻さなくていいからですね。










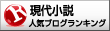








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます