
さて、皆様あけましておめでとうございます。
あんまり寒くない昨今、スキー場とか雪国でお勤めの皆様は大変なのではないでしょうか。
さて、そんなまったく寒くない冬、俺は今日も今日とて電装品いじってます。
小説書けよ? ですよね。
デイトナ(DAYTONA) V-プロテクター ボルテージサポートコンデンサ
それはともかく、バッテリーを保護するというコンデンサー、デイトナのV-プロテクター ボルテージサポートコンデンサを買ってみました。
セルモーターは回転の瞬間、大電流を放出して瞬間的にバッテリー電圧が大きく低下します。エンジンが始動すると消費した電力は再び充電されていくのですが、これを繰り返すことでバッテリーの劣化が進んでいきます。
これは未始動状態での電力消費が大きく、さらにバッテリー性能の低い単車では特に顕著なのですが、この瞬間に蓄積していた電力を瞬間的に放出して電圧降下を抑制し、バッテリー性能の劣化を抑えると同時に、自然放電による電圧低下を充電して長期保管時の性能低下も抑えるというものです。
いわゆる補助バッテリーとはまた趣の異なるものですね。

これが本体。
あとは結束バンドが二本だけでした。


テールカウルの内側でフレームに括りつけるのが最善なのですが配線の長さが足りず、今回はサイドカバー横に括りつけました。すぐ下にスターターリレーと一緒にフューズボックスがあり、もしニューズ切れを起こしたときに作業の邪魔になるので、そのうちハーネスの延長線を作って移設しようと思います。

サイドカバーを閉じたところ。

アース線はこのへんに共締めにしました。これも出来ればアーシング用の太いケーブルを使ってバッテリーとじかにつないだ方がいいので、今度やってみようと思います。
あと、バッテリーにジャンプケーブルや充電器を接続する場合ははずしたほうがいいみたいですね。
蓄電装置である関係上はずしたコンデンサの赤黒の端子が接触するのも危険なのですが、これは30Aのフューズをはずしてターミナルに電圧がかからない様にすることで事前に防止出来ると思います。
個人的には延長線を作ったときにスイッチをつけて、必要に応じて機能をオフに出来たらと思ってます。いちいちフューズを抜くのは煩わしいですからね。
それと同時に太い線を用意して、バッテリーにジャンプケーブル用の専用の端子を追加したりとか。こないだBMWのエンジンルーム内に専用のプラスターミナルとアース用ナットがあるのを見つけて思いついたんですけど。
あんまり寒くない昨今、スキー場とか雪国でお勤めの皆様は大変なのではないでしょうか。
さて、そんなまったく寒くない冬、俺は今日も今日とて電装品いじってます。
小説書けよ? ですよね。
デイトナ(DAYTONA) V-プロテクター ボルテージサポートコンデンサ
それはともかく、バッテリーを保護するというコンデンサー、デイトナのV-プロテクター ボルテージサポートコンデンサを買ってみました。
セルモーターは回転の瞬間、大電流を放出して瞬間的にバッテリー電圧が大きく低下します。エンジンが始動すると消費した電力は再び充電されていくのですが、これを繰り返すことでバッテリーの劣化が進んでいきます。
これは未始動状態での電力消費が大きく、さらにバッテリー性能の低い単車では特に顕著なのですが、この瞬間に蓄積していた電力を瞬間的に放出して電圧降下を抑制し、バッテリー性能の劣化を抑えると同時に、自然放電による電圧低下を充電して長期保管時の性能低下も抑えるというものです。
いわゆる補助バッテリーとはまた趣の異なるものですね。

これが本体。
あとは結束バンドが二本だけでした。


テールカウルの内側でフレームに括りつけるのが最善なのですが配線の長さが足りず、今回はサイドカバー横に括りつけました。すぐ下にスターターリレーと一緒にフューズボックスがあり、もしニューズ切れを起こしたときに作業の邪魔になるので、そのうちハーネスの延長線を作って移設しようと思います。

サイドカバーを閉じたところ。

アース線はこのへんに共締めにしました。これも出来ればアーシング用の太いケーブルを使ってバッテリーとじかにつないだ方がいいので、今度やってみようと思います。
あと、バッテリーにジャンプケーブルや充電器を接続する場合ははずしたほうがいいみたいですね。
蓄電装置である関係上はずしたコンデンサの赤黒の端子が接触するのも危険なのですが、これは30Aのフューズをはずしてターミナルに電圧がかからない様にすることで事前に防止出来ると思います。
個人的には延長線を作ったときにスイッチをつけて、必要に応じて機能をオフに出来たらと思ってます。いちいちフューズを抜くのは煩わしいですからね。
それと同時に太い線を用意して、バッテリーにジャンプケーブル用の専用の端子を追加したりとか。こないだBMWのエンジンルーム内に専用のプラスターミナルとアース用ナットがあるのを見つけて思いついたんですけど。










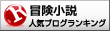








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます