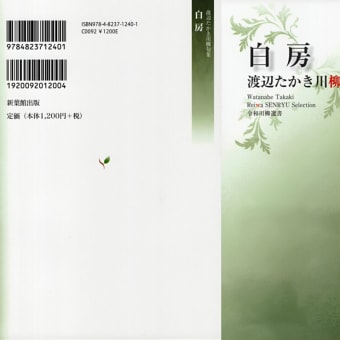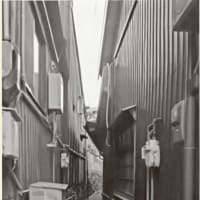□本日落語一席。
◆五街道雲助「居残り佐平次」(寄席チャンネル)。
横浜にきわい座、平成28(2016)年7月13日(「五街道雲助独演会」)。
昨日一昨日と、続けて聞いてきた雲助独演会の最後はこれ。ふり返ると、「徳ちゃん」「五人廻し」「居残り佐平次」は、みな廓噺だ。ふつうの落語会だったら、ネタがつくので避けるところだが、ここが独演会の強またはおもしろみといったところか。
◆五街道雲助「居残り佐平次」(寄席チャンネル)。
横浜にきわい座、平成28(2016)年7月13日(「五街道雲助独演会」)。
昨日一昨日と、続けて聞いてきた雲助独演会の最後はこれ。ふり返ると、「徳ちゃん」「五人廻し」「居残り佐平次」は、みな廓噺だ。ふつうの落語会だったら、ネタがつくので避けるところだが、ここが独演会の強またはおもしろみといったところか。
廓噺でありながら、それぞれ視点の異なるものを三席ならべてあるところが、ご趣向である。前二席は、当時の感覚からすると、あるあるだったかもしれないが、その最後ま三席めは、廓の遊びとしてかならずしも一般的と言えなかっただろう、「居残り」の噺である。
落げは従来どおりものだと、現代感覚からすればわかりにくいものである。だから、立川談志家元なども、独自にかえて演っていた。
しかし、今回、雲助は、落げのための仕込みも入れず、ふつうに「おこわにかけた。……頭がごま塩」で落げていた。一つには、ふつうの落語会でなく、これが雲助の独演会だということ。おそらくほとんどの客は、仕込みなどなくても、みなこの落げの意味を知っているだろう。ともすると、客の多くは、雲助の「居残り佐平次」を、もうすでに何度も聞いている人たちではないのか。
しかし、今回、雲助は、落げのための仕込みも入れず、ふつうに「おこわにかけた。……頭がごま塩」で落げていた。一つには、ふつうの落語会でなく、これが雲助の独演会だということ。おそらくほとんどの客は、仕込みなどなくても、みなこの落げの意味を知っているだろう。ともすると、客の多くは、雲助の「居残り佐平次」を、もうすでに何度も聞いている人たちではないのか。
また、もう一つには、この落語は落げにあまり意味がない。聞かせどころは、噺のなかにいくつもあるのである。だから、落げはおまけみたいなものだ。「芝浜」のように、落げがきまって落着という噺ではない。
個人的にいちばん好きな聞かせどころは、佐平次が布団部屋に入って以後、はじめて客の前に出てくる場面である。カスミさんの客かっつぁんのところへ下地を持って入ってくるところ。ここから、佐平次の活躍が始まる転機となるところで、すこぶる盛りあがる。
まあ、人によっては、金がなくて若い衆をけむにまくところ、または、最後の旦那とのやりとりなどがおもしろいという向きもあるだろう。それほど、この落語は重層性に富んでいると言えるのである。