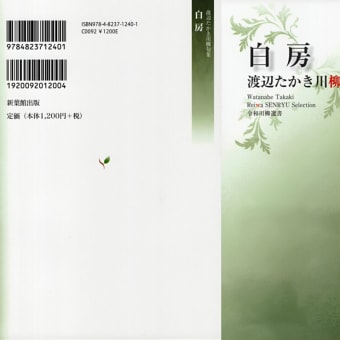□本日落語二席。
◆古今亭菊之丞「火焔太鼓」(寄席チャンネル)。
神楽坂毘沙門天善国寺書院、令和2(2020)年1月29日(神楽坂毘沙門寄席 第48回「菊之丞の会」)。
◆古今亭菊之丞「火焔太鼓」(寄席チャンネル)。
神楽坂毘沙門天善国寺書院、令和2(2020)年1月29日(神楽坂毘沙門寄席 第48回「菊之丞の会」)。
◆笑福亭鶴二「祝いのし」(衛星劇場『衛星演芸招待席』)。
DAIHATSU心斎橋角座、令和2(2020)年1月1日(「新春揃踏角座落語づくしの会」)。
「祝いのし」と言えば、故三代目桂春團治の得意ネタで、三代目は、よくこれをめでたい会(襲名披露・新春寄席など)にかけていた。そういう御祝儀的な落語だとの意識からか、また、他に理由があるのかはわからないが、三代目は、この落語にいつも落げをつけず、「おなじみ『祝いのし』でございます」というようなひと言を残して、高座をさがっていた。若いときもそうだったのかどうだか。
DAIHATSU心斎橋角座、令和2(2020)年1月1日(「新春揃踏角座落語づくしの会」)。
「祝いのし」と言えば、故三代目桂春團治の得意ネタで、三代目は、よくこれをめでたい会(襲名披露・新春寄席など)にかけていた。そういう御祝儀的な落語だとの意識からか、また、他に理由があるのかはわからないが、三代目は、この落語にいつも落げをつけず、「おなじみ『祝いのし』でございます」というようなひと言を残して、高座をさがっていた。若いときもそうだったのかどうだか。
春團治以外の落語家がこれを演るとき、さて、落げはどうしていただろう。ちょっと思い出せない。というか、もしかすると、三代目が存命だったとき、他の落語家はあまりこれを演らなかったのだろうか。
皆無ではないが、自分の鑑演記録には、東京を除いて、上方の落語家がこれを演ったのを聞いたというのがあまり出てこない。2006年から三代目が亡くなる2016年までで、二代目桂春團治や五代目桂文枝などの昭和のレコード・CD等を除いて、上方の落語家でこれは聞いたのは桂梅團治、桂文三(つく枝時代)、桂文昇、桂米輔だけである。それに比して、三代目の「祝いのし」を聞いた記録は数限りなく出てくる。
皆無ではないが、自分の鑑演記録には、東京を除いて、上方の落語家がこれを演ったのを聞いたというのがあまり出てこない。2006年から三代目が亡くなる2016年までで、二代目桂春團治や五代目桂文枝などの昭和のレコード・CD等を除いて、上方の落語家でこれは聞いたのは桂梅團治、桂文三(つく枝時代)、桂文昇、桂米輔だけである。それに比して、三代目の「祝いのし」を聞いた記録は数限りなく出てくる。
そして、笑福亭でこれを聞いたのは、自分の鑑演記録としては、これが初めてだ。鶴二はなんとなく三代目春團治のを参考にしていたように思ったが、どうだろう。また、鶴二は、地口の落げをつけていたが、たぶん独自に考えたものではないかな。