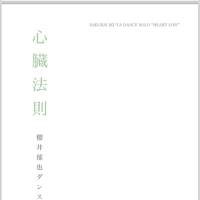(前稿と少し関連あり)
「われわれは突然この地上にとり残されてしまった、、、」
20世紀初頭の荒地のような心情を表しているこの言葉は、いま目にしたとき、どこか僕らの心性の始まりを描写しているようにも思えた。
発話者のオルテガは当時、ヨーロッパで起こりつつあった前衛芸術を観て、未来の芸術は現実の生活感から遠ざかり特別な人にしか分からないものに発展するのではと危惧していた人だ。彼の言葉にもう少し触れたくなり数冊を手にとったが、主著『大衆の反逆』はヘビーだった。
近代。
ニーチェが神様は死んだと宣言し、哲学や信仰は家庭や社会の共有物から個人の心の問題になり、あらゆる価値は多様性の一つであることが前提になった時代。
戦争もまた複雑で理解を超えた原因をもって、怪物のように現れ、命や街を食い荒らし始めた時代。
一人一人が自立せざるを得ないゆえに起きる断絶や葛藤。
人と人が互いに理解し合うしか道が無くなってゆくなか、強烈な思想を語る輩が跋扈する。
不条理や闘いや苦しみや淋しさが広がるなか、
経済や競争や集団心理が生き物のように姿を露わにしはじめた時代。
王様や神様のかわりに現れた資本の網とイデオロギーの嵐。
欲望の渦中に生き残されたことを沢山の人が感じ始めたであろう時代。
オルテガの先の言葉から、そんな時の流れを反省する機会を得た。
オルテガはアカデミックな論理構築よりも公開スピーチによる言論展開を好み政治家としても行動を起こしたそうだが、あらためてその言葉を読んでみると、言葉を思索の結果でなく、行動の始まりとして発話している感じが強い。『大衆の反逆』にちょろっと出てくるだけの「馬鹿は死ななきゃ直らない」という言葉はやけに有名だが、「馬鹿」とは誰に向けてのたまうか、ちょっと高飛車な書きっぷりを我慢しながら読書した。
気を静めて読んでみると、そこに描かれてある大衆像は当時以上に21世紀の現在に警句を出してくれている感が少ししてきた。
オルテガはこの書で「大衆」なるものを来るべき権力実体と捉え、その心理を「あの甘やかされた子供の特徴的な心理に」似ていると喝破する。
その大衆が少数者を排除する心理を生み出して社会を支配してゆくだろうと予見する。
みんな、こうしているみたいだ。
みんながんばってるのだから。
みんながまんしてるのだから。
みんな、こう思っているにちがいない。
大衆の合言葉は「みんな」であるが、その実体は何なのだろう、、、。
いまもしょっちゅう使われる「みんな」というさりげない言葉に、そのさりげなさに、しばしば得体の知れない暴力性を感じることがあるが、
この書を読んでいると少しその理由にも想像がおよぶ。
(僕の場合、この「みんな」という言葉との出会いは「学校」だったのだが)
個々の差異が放棄される一線が社会にはあるのだろうか。
ひとりひとり、と言いつつ思いつつ、いつしか集団的な幻想が社会を動かしてしまうのが、いわゆる大衆社会というものの厄介なところなのかもしれない。
世の中という場所がどんどん広がってゆく反面、個と社会の関係は抽象的になり、人と人のあいだにある筈の、身体性、差異の認識、距離感、それらが薄れるのかしら。
「自分自身に特殊な価値を認めようとはせず、自分はすべての人と同じと感じ」ること。
「凡俗であることの権利を敢然と主張し、いたるところでそれを貫徹しようとする」「人々」。
とは書中からのもの。
みんな、という観念が主体になってしまう世界。
そこから個々の人の心にはどんな現象が起こるのか。
断定的な辛辣な、と思う反面、我が身を振り返りたくもなる。
「なぜ人々は、あらゆる行為は一つの未来の実現であることに気づかなかったのか」
日々の生活に気を取られているあいだに、何かが変化してゆく。
時代の足音が聞こえてくるのは非常にゆるやかで、気付いた時には取り返しがつかなくなっている。
直接にはボルシェビキやファシズムに支持が向かいつつあった当時の世相への警告だったかもしれないが、
すでに次代を生きている僕ら自身にも跳ね返ってくる感があるのは少し背中が寒くなる。
古いと思っていた「大衆」という言葉と意識、、、。
それは幽霊のように今も世界を徘徊して、僕らの存在の仕方に魔を放っているのではないか、とも思ってしまう。
個とは。我とは。
この書を読んでいると、省みざるを得ない言葉が沢山出てくる。
「私とは、私と私の環境である。そしてもしこの環境を救わないなら、私をも救えない」
彼の一言一言は、どきりとする。
「われわれは突然この地上にとり残されてしまった、、、」
20世紀初頭の荒地のような心情を表しているこの言葉は、いま目にしたとき、どこか僕らの心性の始まりを描写しているようにも思えた。
発話者のオルテガは当時、ヨーロッパで起こりつつあった前衛芸術を観て、未来の芸術は現実の生活感から遠ざかり特別な人にしか分からないものに発展するのではと危惧していた人だ。彼の言葉にもう少し触れたくなり数冊を手にとったが、主著『大衆の反逆』はヘビーだった。
近代。
ニーチェが神様は死んだと宣言し、哲学や信仰は家庭や社会の共有物から個人の心の問題になり、あらゆる価値は多様性の一つであることが前提になった時代。
戦争もまた複雑で理解を超えた原因をもって、怪物のように現れ、命や街を食い荒らし始めた時代。
一人一人が自立せざるを得ないゆえに起きる断絶や葛藤。
人と人が互いに理解し合うしか道が無くなってゆくなか、強烈な思想を語る輩が跋扈する。
不条理や闘いや苦しみや淋しさが広がるなか、
経済や競争や集団心理が生き物のように姿を露わにしはじめた時代。
王様や神様のかわりに現れた資本の網とイデオロギーの嵐。
欲望の渦中に生き残されたことを沢山の人が感じ始めたであろう時代。
オルテガの先の言葉から、そんな時の流れを反省する機会を得た。
オルテガはアカデミックな論理構築よりも公開スピーチによる言論展開を好み政治家としても行動を起こしたそうだが、あらためてその言葉を読んでみると、言葉を思索の結果でなく、行動の始まりとして発話している感じが強い。『大衆の反逆』にちょろっと出てくるだけの「馬鹿は死ななきゃ直らない」という言葉はやけに有名だが、「馬鹿」とは誰に向けてのたまうか、ちょっと高飛車な書きっぷりを我慢しながら読書した。
気を静めて読んでみると、そこに描かれてある大衆像は当時以上に21世紀の現在に警句を出してくれている感が少ししてきた。
オルテガはこの書で「大衆」なるものを来るべき権力実体と捉え、その心理を「あの甘やかされた子供の特徴的な心理に」似ていると喝破する。
その大衆が少数者を排除する心理を生み出して社会を支配してゆくだろうと予見する。
みんな、こうしているみたいだ。
みんながんばってるのだから。
みんながまんしてるのだから。
みんな、こう思っているにちがいない。
大衆の合言葉は「みんな」であるが、その実体は何なのだろう、、、。
いまもしょっちゅう使われる「みんな」というさりげない言葉に、そのさりげなさに、しばしば得体の知れない暴力性を感じることがあるが、
この書を読んでいると少しその理由にも想像がおよぶ。
(僕の場合、この「みんな」という言葉との出会いは「学校」だったのだが)
個々の差異が放棄される一線が社会にはあるのだろうか。
ひとりひとり、と言いつつ思いつつ、いつしか集団的な幻想が社会を動かしてしまうのが、いわゆる大衆社会というものの厄介なところなのかもしれない。
世の中という場所がどんどん広がってゆく反面、個と社会の関係は抽象的になり、人と人のあいだにある筈の、身体性、差異の認識、距離感、それらが薄れるのかしら。
「自分自身に特殊な価値を認めようとはせず、自分はすべての人と同じと感じ」ること。
「凡俗であることの権利を敢然と主張し、いたるところでそれを貫徹しようとする」「人々」。
とは書中からのもの。
みんな、という観念が主体になってしまう世界。
そこから個々の人の心にはどんな現象が起こるのか。
断定的な辛辣な、と思う反面、我が身を振り返りたくもなる。
「なぜ人々は、あらゆる行為は一つの未来の実現であることに気づかなかったのか」
日々の生活に気を取られているあいだに、何かが変化してゆく。
時代の足音が聞こえてくるのは非常にゆるやかで、気付いた時には取り返しがつかなくなっている。
直接にはボルシェビキやファシズムに支持が向かいつつあった当時の世相への警告だったかもしれないが、
すでに次代を生きている僕ら自身にも跳ね返ってくる感があるのは少し背中が寒くなる。
古いと思っていた「大衆」という言葉と意識、、、。
それは幽霊のように今も世界を徘徊して、僕らの存在の仕方に魔を放っているのではないか、とも思ってしまう。
個とは。我とは。
この書を読んでいると、省みざるを得ない言葉が沢山出てくる。
「私とは、私と私の環境である。そしてもしこの環境を救わないなら、私をも救えない」
彼の一言一言は、どきりとする。