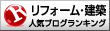早送り映像のように、
いいかげんな推論が
ラクダの背に乗ってウマの背を登る。

休憩中のラクダたちはいつも笑っている。その笑いに理論的な理由はない。おそらくアリが「概念をよせつけない城」を笑いのモチーフとして提供するのだろう。このみごとな透視図が草むらに愛の秘めごとを沈殿させる。生態学的な「おそらく」は気持ちよさそうに砂風呂につかっている。いい湯だな、をゾウの鼻唄で歌う。雲は都合よく来ない。雨も合理的に落ちない。早送り映像のように、いいかげんな推論がラクダの背に乗ってウマの背を登る。例の「かんべんしてや」を折り返し点にして、「生きられた体験」から親しい関係を感受するための水場が渇いた脳内を逆走してくる。乾きがじわじわと「小さいゾウさんと大きいアリさんのお話」をスライドする。どうしても食べてみたい砂丘プリン、その可逆性の先端からおいしい水がしたたり落ちる。だからだな、ラクダの口がいつも笑っているのは。どんなにつらくても。