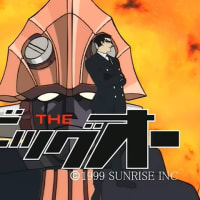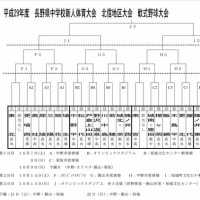2025年の節分は2月2日(たぶん明日)になります。
例年、節分といえば2月3日だと思っていたのですが、しつこいようですけど2025年は2月2日(たぶん明日)。
節分といえばいろいろと行事がありますが、「鬼は外、福は内」の声に合わせて豆まきを行い、恵方巻を食べるのが定着しています。有名なお寺とか神社での豆まきはニュースになりますが、あまりニュースにはならない一般家庭でも豆まきってやっているのでしょうか?
我が家では息子たちが小さいころまではやっていましたが、いまとなっては「絶滅危惧行事」となっています。
ただ、「鬼」が家のなかにいるのを見かけましたら、容赦なく豆をぶつけるのですけど・・・。基本的には息子たちがいたころからは、「からつき落花生」を使用。あとで回収して食べられますのでね。

久しぶりに、まいてみますかな・・・のまえに、味見。やっぱり落花生はおいしいです。
「恵方巻」は買うこともありますが、豆まきと同じで我が家では絶対行事ではありません。
バリエーション豊かなのはいいですが、値段が高くなる一方ですのでね。でも、昨年は一番高いものを買って、切って食べていたような記憶があります。お寿司が苦手な方には恵方巻もどきのスイーツ、たとえばエクレアでもいいかもしれません。
スイーツも苦手な方は、そうですねえ、たとえば、ちくわとか・・・。
ほかにも地域によっては、「節分そば」「けんちん汁」や「節分まんじゅう」とか、いろいろあるようです。
さて、節分は立春の前日。
1984年までは4年に1度のうるう年の節分は2月4日でした(そうでしたっけ?)。1985年~2020年までは毎年2月3日でした(そうでした)。2021年~2057年まではうるう年の翌年の節分は2月2日となります(だそうです)。
数十年単位でだんだんと前倒しになっていく計算ですが、4で割り切れてもうるう年にはならない1900年、2100年、2200年などの翌年に1日遅れて帳消しになります。
そもそも節分は立春の前日であって、立春は太陽黄経(太陽の見かけ上の通り道)が315度となる日。よって、将来的に何らかの天文学的なズレなどの影響によって日にちが変わることもあるかも知れません。
立春は1年を24等分した「二十四節気」のうちのひとつ。二十四節気には立春や立夏などの他に夏至や冬至、春分、秋分、処暑、大寒などがあります。
1年は通常365日ですが国立天文台によれば実際に地球が太陽の周りを一周するのは365.2422日。つまり365日と約6時間。この約6時間のズレは4年経つと(6時間 x 4回 = 24時間)で約1日になります。そのため4年に一度、1年を366日とする、うるう年を作って調整。
ところが、うるう年によって調整しても、二十四節気は 約45分ズレるため、4で割り切れてもうるう年にはならない年もあり、立春の日も違ってくるのです(らしい)。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
例年、節分といえば2月3日だと思っていたのですが、しつこいようですけど2025年は2月2日(たぶん明日)。
節分といえばいろいろと行事がありますが、「鬼は外、福は内」の声に合わせて豆まきを行い、恵方巻を食べるのが定着しています。有名なお寺とか神社での豆まきはニュースになりますが、あまりニュースにはならない一般家庭でも豆まきってやっているのでしょうか?
我が家では息子たちが小さいころまではやっていましたが、いまとなっては「絶滅危惧行事」となっています。
ただ、「鬼」が家のなかにいるのを見かけましたら、容赦なく豆をぶつけるのですけど・・・。基本的には息子たちがいたころからは、「からつき落花生」を使用。あとで回収して食べられますのでね。

久しぶりに、まいてみますかな・・・のまえに、味見。やっぱり落花生はおいしいです。
「恵方巻」は買うこともありますが、豆まきと同じで我が家では絶対行事ではありません。
バリエーション豊かなのはいいですが、値段が高くなる一方ですのでね。でも、昨年は一番高いものを買って、切って食べていたような記憶があります。お寿司が苦手な方には恵方巻もどきのスイーツ、たとえばエクレアでもいいかもしれません。
スイーツも苦手な方は、そうですねえ、たとえば、ちくわとか・・・。
ほかにも地域によっては、「節分そば」「けんちん汁」や「節分まんじゅう」とか、いろいろあるようです。
さて、節分は立春の前日。
1984年までは4年に1度のうるう年の節分は2月4日でした(そうでしたっけ?)。1985年~2020年までは毎年2月3日でした(そうでした)。2021年~2057年まではうるう年の翌年の節分は2月2日となります(だそうです)。
数十年単位でだんだんと前倒しになっていく計算ですが、4で割り切れてもうるう年にはならない1900年、2100年、2200年などの翌年に1日遅れて帳消しになります。
そもそも節分は立春の前日であって、立春は太陽黄経(太陽の見かけ上の通り道)が315度となる日。よって、将来的に何らかの天文学的なズレなどの影響によって日にちが変わることもあるかも知れません。
立春は1年を24等分した「二十四節気」のうちのひとつ。二十四節気には立春や立夏などの他に夏至や冬至、春分、秋分、処暑、大寒などがあります。
1年は通常365日ですが国立天文台によれば実際に地球が太陽の周りを一周するのは365.2422日。つまり365日と約6時間。この約6時間のズレは4年経つと(6時間 x 4回 = 24時間)で約1日になります。そのため4年に一度、1年を366日とする、うるう年を作って調整。
ところが、うるう年によって調整しても、二十四節気は 約45分ズレるため、4で割り切れてもうるう年にはならない年もあり、立春の日も違ってくるのです(らしい)。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。







![[ 閲覧注意 ] どういう状態になったかと言うと・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/ff/52ba0cd2fa20b2d36331b107d2ce63e4.jpg)