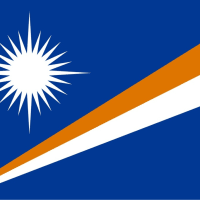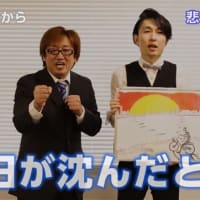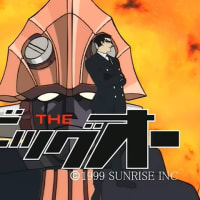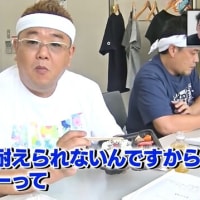サッカーではシーズンが始まってすぐに結果が出なかったりすると、監督交代のニュースが飛び交うことが年中行事のようにあります。
また、新しく就任した監督の戦術によって、今までスターティングメンバーだった選手がサブどころかベンチにも入れなくなってしまうというようなニュースも出てきます。それでも勝っていればいいのでしょうけど、さらに負け続けてしまったりして、二進も三進も(にっちもさっちも)行かなくなってしまうこともあります(ACミランとかマンUとか)。
神奈川県にある桐光学園。
楽天のゴールデンルーキー松井裕樹の出身校ですが、サッカーでも全国レベルの強豪校であり、元日本代表MF中村俊輔(横浜F・マリノス)やMF藤本淳吾(名古屋グランパス)を排出しています。
このサッカー部を強豪チームへと育てた佐熊裕和前監督が一昨年度末に退任し、後任となったのが1年前に戻ってきた鈴木勝大現監督です。
名将佐熊前監督の退任は新年度が直前での出来事だけにチーム内外には大きな衝撃が走り、抜けた穴の大きさを不安視する声が挙がったそうです。
そして、シーズンが始まると参戦するU-18プレミアリーグEASTで14試合1勝13敗3分。インターハイ(高校総体)県予選ベスト8敗退と監督交代による弱体化となってしまったそうです。
しかし、鈴木監督は「夏(=インターハイ)落とした中でこの冬(=選手権)につなげていくために僕自身、確固たる決意の下やってきた」、「プレミアでズタボロにされたことにめげず、選手たちがタフにやり続けたということがこの成果と結果につながった」というほどのチームに成長していきます。
その結果、この冬の第92回全国高校サッカー選手権大会神奈川県大会で優勝。切り替えの速さと自陣ゴール前での体を張った守備で県大会は失点ゼロ。
「代表クラスのスーパーな選手はいませんが、全員が攻守共にハードワークできるはうちの良さの一つ。日本で一番切り替えの速いチームを目指してやっています」
と言っています。
さて、高校野球でも同じですが監督交代をきっかけにして、その後に姿を消してしまうチームは多いそうです。
そうした学校は一人の“先生”の情熱や指導力によって作られてきたチーム。
ですから、あまりにも影響力が強すぎるカリスマ的監督であったために、選手への影響力もあるでしょうし、後任の監督へのプレッシャーがあるのではないかと考えます。
この桐光学園の場合は佐熊前監督が中国からプロコーチのオファーを受けて日本を離れたこともあったことは、結果としてバトンタッチが上手く行ったと言います。
(よく、料理店でも名人といわれた先代を引き継いだ二代目が、先代と同じレベルであったとして、あまりにも先代が神格化されてしまい、同じではレベルが下だと言われるのも同じようなことでしょうか(違うか?))
名将と言われた監督交代では、前任者のことを踏襲してやることの方が難しいでしょうし、どうしても比較してしまうことがあり、周囲も不安、不満になってしまい、それがまた比較する対象となってしまいます。
でも、本当の名将とは、自分が居なくなったとしても”勝てる”チーム作りをして、後継に託していくことができる人だと私は思います。
監督交代に対しては、後任監督がどれだけ早くに自分のカラー出せるのか。その環境で楽しくできるのか。
桐光学園が難しい監督交代を上手く出来た要因なのでしょう。