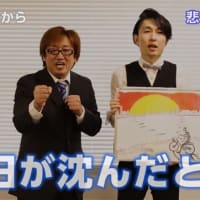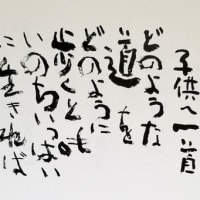「鼻の穴」「靴下の穴」ときて、第3弾も「穴」だと思っている方も多いと思いますが、ネタ切れでございます。前回2回も真面目でしたが、最終回の今回は、さらに真面目な話でまとめておきたいと思います。
そこで、大人も子どもも好きな場所で、少しでも涼しげなところといえば「水族館」です。今回は水族館の小ネタをまとめてありますので、参考にしてみてください。
■アザラシではないアシカ
おなじみのアシカとアザラシ。アザラシは耳のあるところに穴があいているだけですが、アシカには小さな耳が付いています。 また、アザラシの後ろヒレは小さく、折りたたむことはできませんが、アシカは後ヒレをたたむことができ、前肢と後肢で器用に歩きます。
■シロイルカは脱皮する
野生のシロイルカは1年に1回脱皮するそうです。北極海近辺は夏でも氷が多いため、ぶつかって傷だらけになってしまいます。そこで冬が来る前に新しい皮膚に替えるために脱皮するそうです。
■ホッキョクグマは地黒
真っ白なホッキョクグマの地肌は黒色です。これは、寒い地域に住んでいるため、太陽の熱をたくさん吸収できるように黒くなったと考えられています。そして、毛は白ではなく透明で、空気を溜められるようストローみたいになっていて、光を反射して白く見えるそうです。
■クマノミは一番大きいオスがメスに変身する
通称「ニモ」。イソギンチャクを住処にしており、1株のイソギンチャクに1つの群れが暮らしていますが、メスは1匹しかいません。実は群れの中で一番大きな個体がメスに性転換し、二番目に大きな個体がオスとなるそうです。
■マンボウの99.99%は大人になれない
体長約3m、体重約2tを超えるマンボウ。最大で約3億個の卵を産むそうです。しかし、そのうち大人になれるのは約2匹といわれています。泳ぎが遅く、これといった防御手段もなく、のんびりとした性格のためといわれています。
■マンボウは年齢不詳
もう一つマンボウネタです。魚には耳石といって耳に小さな石があり、木の年輪みたいな模様があって、そこから年齢を知ることができます。でも、マンボウは魚なのに、その耳石がありません。ですから、マンボウの年齢をはっきりとはわからないのです。80~100歳くらい生きているという説もあります。
■カツオのシマシマ
カツオは頭から尾に向かって薄い「たてじま」模様があります。しかし、興奮すると、しまの向きが変わって「よこじま」に変化するそうです。理由は不明です。
■サメはめんどくさがり屋
サメと同じ水槽の中に小魚がたくさん泳いでいますが、サメは同じ水槽の小魚は食べません。仲間意識といえば、なんとなくいい話ですが、同じ水槽の小魚を食べない理由は「めんどくさいから」なんだそうです。実際は、めんどうというよりも、無駄なことはしないからなのです。水族館ではサメにそれなりのエサを与えており、エサは逃げないので、サメにとっていちばん楽に食べられるからなのです。なお、水槽にはお互い食べにくい相手を入れているからも理由の一つのようです。
それでも最後に「穴」のお話を2題。
■イルカは眠るとおぼれる
イルカは人間と同じほ乳類のため、頭のてっぺんにある「鼻の穴」を水面に出して呼吸しなければなりません。ですから、イルカは完全に眠ることはできません。数分ごとに片目を閉じて、脳を半分ずつ休めているそうです。一日に300回以上繰り返して眠っているそうです。
■クラゲは口と肛門がいっしょ
見た目に似合わず、強い毒のある触手を持つクラゲ。その触手で獲物を刺して弱らせ、そのあとに口に運んで体内で消化吸収してから、食べかすを再び口から外にだします。つまり、「口からうんこ」をだしているということになります。
ちなみに、どうでもいい話ですが、「さかな」の語源は酒のつまみを指す「酒菜」といわれています。もともと、酒菜は魚類だけでなく肉や野菜も対象とする言葉でしたが、一番多くお魚がつまみとして親しまれていたので、そこから転じて魚類に「さかな」があてられたそうです(諸説あります)。それまでは「とと」や「うお」と呼ばれていたようです。
緊急事態宣言が解除され、また、新型コロナウイルス感染が終息した際には、ゆっくりと水族館にでもお出かけください。もっといろいろな不思議に出会えると思いますよ。
今日も、私のブログにお越しいただいてありがとうございます。
今日がみなさんにとって、穏やかで優しい一日になりますように。そして、今日みなさんが、ふと笑顔になる瞬間、笑顔で過ごせるときがありますように。
どうぞ、お元気お過ごしください。また、明日、ここで、お会いしましょう。