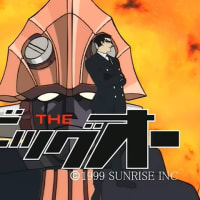埼玉県勢が夏初優勝。花咲徳栄高は埼玉県勢としては24年ぶりの決勝進出で初優勝しました。この前祝ではなかったと思いますが、今年の夏は甲子園で真昼の花火がポンポンと打ちあがった年です。49代表校がすべて出揃った大会7日目の第3試合終了時点で、ホームランは35本。この数はすでに昨年の大会全本数に肩を並べるほどでした。
さらに8月19日の大会第11日の第一試合では、岩手・盛岡大学付高と愛媛・済美高では同じイニングで、両チームが満塁ホームランを放つという、大会史上初の出来事が起きました。
さて、今年は最終的には68本でした。どのくらいホームランが多いかと言えば、ここ10年間の大会全体でのホームラン数を見れば明らかだと思います。
2007年 24本(49試合)
2008年 49本(54試合)
2009年 35本(48試合)
2010年 26本(48試合)
2011年 27本(48試合)
2012年 56本(48試合)
2013年 37本(48試合)
2014年 36本(48試合)
2015年 32本(48試合)
2016年 37本(48試合)
なお、今までの大会記録としては2006年の60本(49試合)です。この年は、早稲田実高・斎藤佑樹選手(現;北海道日本ハムファイターズ)と駒大苫小牧高・田中将大選手(現;ニューヨーク・ヤンキース)が決勝再試合の名勝負を繰り広げたことで記憶にありますが、その一方で、準々決勝では智弁和歌山高と帝京高が両チーム合わせてホームラン7本が乱れ飛ぶ壮絶な打ち合いを演じていた年です。
昔の高校野球では「小さなことをコツコツと」でしたが、現代の高校野球には「打てないと勝てない」という考えとなっています。打撃練習用マシンや金属製バットの性能向上、最先端のトレーニングによるスイング速度の向上など、ピッチャー以上に技術力向上のための土台が多いくらいだと思います。また、どこも普段の練習で守備よりも打撃に時間を割いているチームが増えていることも一因だと思います。
また、今年はプロのスカウトやマスコミが大きく注目するようなピッチャーが見当たりません。140km/hを超える球を投げるピッチャーは多いのですが、四死球は多く、ワイルドピッチでの失点シーンも多く、アバウトな制球力でのピッチングは、打撃強化が著しいチームにとっては、狙い球を絞って思いっきりスイングできるので余計に打ちやすいのかも知れません。
それと、甲子園と言えば、一塁側アルプススタンド後方からレフト方向に通称「浜風」と言われる有名な風が吹いています。この夏の甲子園は常に一定以上の強さの風が吹いていて、そうした風の影響を受けてタイミングよく捉えた打球は軽々とフェンスを越え、バットで拾ったように見えた打球も予想以上に伸びてスタンドインするという説もあります。
だったら、日時は違っても阪神タイガースにその恩恵もあるはずですが、そういうことはなさそうです。ちなみにタイガースの、ここ10年の年間ホームラン数(ビジター含む)は次のとおりです。
2007年 111本
2008年 83本
2009年 106本
2010年 173本
2011年 80本
2012年 58本
2013年 82本
2014年 94本
2015年 78本
2016年 90本
最後に、こんなことはあってはいけないと思うのですが。今年は東西の強豪校にホームランバッターがいました。特に東のチームの選手は高校通算記録を超える勢いでした。その選手が出場すると見込んで、反発力の強いボールを使っているのではないかと思えちゃいます。
彼が甲子園でホームランを量産すれば、大会が盛り上がります。しかし、その肝心なチームが地方大会で敗退。西のチームも地方大会で敗退です。よって、反発力を高くしたはいいものの、結果として長距離バッターではない選手までホームランを打つことになり、これだけ量産されているのかも知れません。
また、個人として大会6本のホームランを打って、32年ぶりに記録が塗り替えられました。あの選手に打ちまくってもらい、かの選手名のお名前を・・・ゴホン。
ちなみに、今年の夏に使われているボールは○○○社製のボールだそうです。2011年からNPBが導入した低反発球の影響で、従来の○○○社製のボール(飛ぶボール)の在庫が出回っているのでは? と思えちゃえます。なお、選抜は他社製のボールだったそうです。ただし、高校野球ではメーカー名と規格は非公開になっています。
まあ、いろいろ書き、最後はちょっとブラックでしたが、純粋に打撃技術向上とピッチャーの力量バランスによるものの結果でしょう。