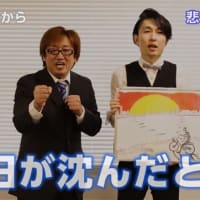「ベースボールいまだかつて訳語あらず、今ここに掲げたる訳語はわれの創意に係る。
訳語妥当ならざるは自らこれを知るといえども匆卒の際改竄するに由なし。
君子幸に正を賜え。」
野球のポジションに「ショートストップ(略してショート)」と呼ばれるポジションがあります。
2014シーズンで中日ドラゴンズではいろんな選手が守っており、選手が固定されていませんが、他のチームではショートと言えば…ということで、チームの顔的な選手が守っているポジションです(たぶん)。
日本語で表記する場合は、「遊撃手」っていいます。
ピッチャー(投手)やキャッチャー(捕手)はその文字のとおり、「投げる人」と「捕る人」だと判ります。
ファースト(一塁手)、セカンド(二塁手)、サード(三塁手)という内野のポジションは、それぞれの塁を主に守ることが判りますし、外野もレフト(左翼手)、センター(中堅手)、ライト(右翼手)と言うように、担当守備範囲=ポジション名となっています。
でも、ショート(遊撃手)というポジションだけは、どういう訳かちょっと違います。
どうして、あのポジションを守っている人が「ショート」であって、「遊撃手」と呼ばれているのかを(ナイツの塙風に言います)ちょっと調べてみました。
ベースボールという競技が始まった頃のことです。
内野のファースト、セカンド、サードはそれぞれ対応するベースに張りつくように守っていました。つまりファーストとサードは、現在とほぼ同じ位置、そしてセカンドは二塁ベースの周辺を守っていました。ところが、ショートストップは特定の位置を受けもたず、状況に応じてファースト方向やサード方向に寄って、守備位置を切り替え、しかもバッターからみてピッチャーとほかの内野手の中間に位置することが多かったそうです。
そして、「打球を短い距離で止める」という意味で「ショートストップ」と呼ばれるようになりました。
その後、二塁ベースを守っていたセカンドが一塁ベース寄りを守るようになったたため、ショートが二塁と三塁の間に移動し、現在の守備形態となったのです。
そして、明治時代に日本へ野球が伝わった頃、正岡子規によって「short=短く」「stop=遮る」の直訳で「短遮」(たんしょ)、「短遮者」と呼ばれました。
その後、明治時代に中馬庚(ちゅうま かのえ)が「ショート・ストップは戦列で時期を見て待機し、あちこちを動き回って守備を固める“遊撃”のようだ」と説明したため、ショートストップというポジションは「遊撃手」と呼ばれるようにいう名称が広まったと言われています。
コメント一覧

まっくろくろすけ

eco坊主
最新の画像もっと見る
最近の「プロ野球」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事