人間は誰もが考えている
インテリだけがそれを自慢しているのだ
シモーヌ・ド・ボーヴォワール (1908~86年)
【聞く耳を持つ王様 持たぬ王様 ~ 礼を厚くするか 斬り殺すか ~ それが問題だの巻】
■政治を「まつりごと」と読むのは、
いにしえより民の利益をもたらすものは
天神地祇(てんしんちぎ)であり、
神々をまつることにより
国よやすかれ、民よ豊かなれ
と祈願したことから起こっている。
こうした思想は上代において、どこにでもみられる。
中国しかり、エジプトしかり、バビロニアしかり。
日本でも皇祖皇宗の霊をまつられたのである。
この政治のあり方を祭政一致というが、
信仰と政治の混同であり、そのスタイルゆえに
民衆は重い税や不当過酷な労働をかせられることもある。
ピラミッド、天壇、東大寺――。
これらは決して過去のものではなく、
現代も形を変えて存在しているのではあるまいか。
◇
驕りに支配されがちな立場でも
聞く耳を持つことが肝要である。
そんなお話を一つ。
むかし大陸に「木桶の輪替え」を生業としている男がいた。
ある日、王様に召され、輪替えの作業をやっていたところ、
ちょうど王様が堂上で本を読んでおられた。
男は
「おそれながら、お尋ねいたします。
王様が今、読んでおられる御本は、
どなたのものでございますか」
と申し上げた。
すると王様は
「これは、むかしの聖人の書かれたものじゃ」
といわれた時、
彼は
「そうですか。
そんな古いものはカスですから、
何の役にも立ちませんでしょう」
と言い放った。
大いに立腹した王様は
「こんな無礼者は斬ってしまえ」
と臣下に命じた。
しかし男は怖れるイロもなく
「今わの際に、一言いわせていただきとうございます。
それは、私の仕事から考えましても、
例えば、輪を作るのに、
ゆっくり過ぎれば甘くて固くならない、
また速ければ堅くて入りませず、
このように緩急よろしきを得なければ、
ピッタリとはハマリません。
こうした呼吸(いき)は人の伝授などでは分かりませんが、
陛下が一国を統治なさいますにも
やはり緩急よろしきをえたもう妙味は、
おそらく古人の死書からは
学び難いかと思います」と言った。
これを聞いた王様は深く感服し、
礼を厚くして帰らしめた、
という。
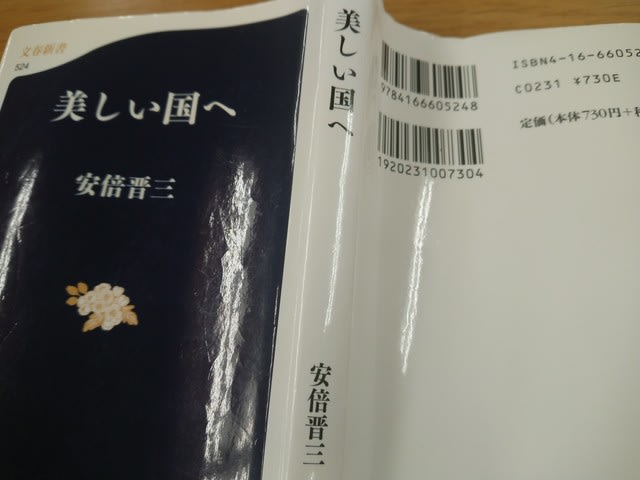

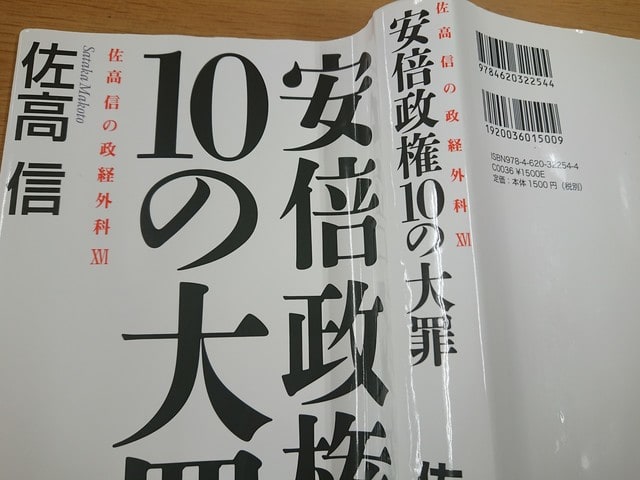

【君子は豹変す】
「君子」は教養や徳の高い立派な人(人格者)の意
「豹変」は季節によりヒョウのまだら模様が美しくなることから
主張や態度などが急に変わることを指す
現代は、権力者などの無節操ぶりを非難する言葉である
「要領のいい人間は、態度をすぐ変えて、主義も思想も捨てるものだ」
しかし原義は逆であって
「優れた人間は、過ちを直ちに改め、速やかによい方向に向かう」
「立派な人は、自らを変革し、人々も改めさせ、革命を成功させる」
「あたかも、虎が毛が抜け変わり、紋様が美しくなるようにーー」
との故事が古代中国に多くみられたのである
これは、どうしたことか
長い時を経て、
現実が理想を駆逐し続けてきたためだろうか

















