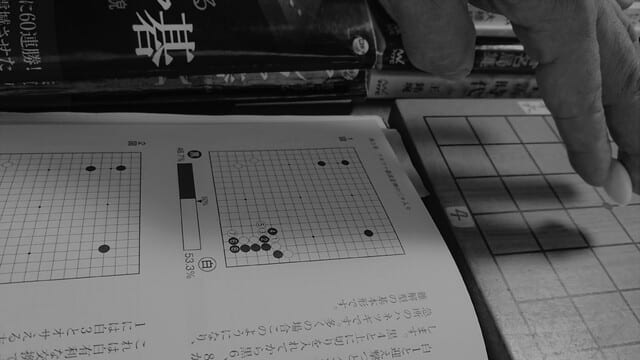【半袖の季節は、碁とバイクが良く似合う の巻】
春秋時代の紀元前548年
衛の献公が亡命先の夷儀の地から
卿(最高級の重臣)の甯喜(ねいき)に向かって
「国に帰りたい」
と申し送った
甯喜はそれを承諾した
献公は暗君であったので
太夫(卿に継ぐ重臣)大叔文子は
古訓と棋理に依って
甯喜に異論を唱えたという
このように古くは
「政」「聖」の色彩が濃いのが
中国の碁の特徴であった
◇
棋を挙げて定まらず(挙棋定まらず)
碁石を打ち下ろすのに
迷ってどこと定まらない
その場その場の思い付きにて
適当に処理することのたとえ
ときに国家の存亡につながる慢心のことである
碁石をつまんだまま、着点定まらず空中に彷徨う
時間制になり、秒読みに追われたプロでもやらかす
アマのなかには碁笥に手を入れて石をガチャガチャ混ぜる者も
よくあるマナー違反で、みっともないクセの一つ
石はもてあそぶものではあるまいに
碁は、ゲームになり、スポーツになったか
着点をココロで決めてから
おもむろに石をつまんで
そっとおくべし
これだけで
「おぬし、出来るな!」
となるから不思議なものである
これは「気」の問題か
「棋」が「気」に通じるのである
マナーが悪くても強い人もいるにはいるが……
下品(げぼん)のそしりを免れぬ
悲しいかな、本人には聞こえないものである
嗚呼、お気の毒、ご愁傷様――