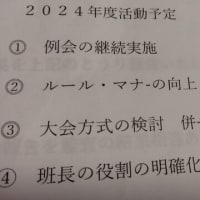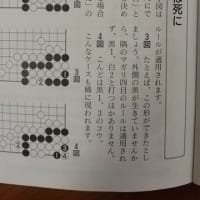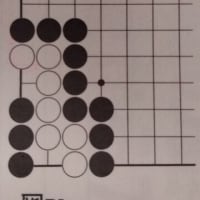【お笑いムラ愛憎劇場にみる嘘と法螺の巻】
■ウソがウソを呼び、あらぬ方向にいってしまった「反社会的勢力とお笑い芸人のカネを巡る諸問題」。
誰かが、問題を整理整頓しないと、一体どこへ行くのやら。
■「わたしは、これまでウソを付いたことはありません」という究極の大ウソがあるとすれば、それは永田町や霞が関あたりにしか残っていない「特別天然記念物」と言えましょう。
ウソはウソ、カネはカネ、関係は関係。
こりゃやっぱり「ちゃんと差配できる行司」が、お出ましいただけねばなりませんね。
◇
■1970年代に「面白半分」なる傑作・珍作・奇作満載の月刊誌がありました。
初代編集長・吉行淳之介を始め、そうそうたる物書きが「柔らかな筆」を競い、大いに楽しませていただいたものです。
12代編集長の筒井康隆によるエッセイ「嘘と法螺(ほら)」から。(抜粋)
最初、嘘は必要に迫られて発生した。
子供が叱られないためにつく嘘がそうである。
しかしその嘘が面白いという場合がある。
すると大人は、子供を叱る気がしなくなってしまう。
子供は奇想天外な嘘をつくからである。
どこかで読んだ話だが、こんなのがある。
あるひとが、下駄を片方なくして帰ってきた子を叱った。
するとその子は、泥棒が持って逃げたのだと言いわけした。
泥棒が持って逃げるのをみていたのなら、 どうしてお巡りさんに言わなかったのだと訊ねると、
子供は、下駄を持って逃げた泥棒というのが、 じつはお巡りさんだったという。
お巡りさんが、下駄を片方持って逃げたって、 何の役にも立たないだろうというと、
そのお巡りさんが片足だったという。
こうなってくるとその嘘は一種のシュール・リアリズム文学に近づいてくる。
叱られないためという実用的価値以外に、芸術的価値を持ちはじめるのである。
嘘から実用的価値をとっぱらってしまったものは、もはや嘘とはいわない。
法螺とか出たらめとかいうものになる。
(中略)
法螺話ばかりして楽しむ習慣というのは、日本人にはないようだ。
ある文学雑誌の書評欄で、あるひとが「この小説には嘘があるからいけない」と書いているのを見て、ぼくはびっくりしたものだ。
(中略)
本当にあったような話、というのを喜ぶ人が大多数で、いかにも架空の話といった小説を喜ぶ人が少ないのは、これはしかたないと思うが、ぼくにとっては癪(しゃく)のタネなのである。(一部略) 嘘であることが最初からわかっている小説のジャンル、つまりSFを選んだのも、そのためではなかったかと思っている。
◇
■嘘も、法螺も、むろん時と場合による。
そもそも正しいか正しくないかなどに重きを求めるのはいかがなものか、とは思う。
■「包帯のような嘘」は、もっぱら政治家と官僚に任せておけばよろしい。だが、シャレにもならぬ嘘から発し 、自己保身のウソが次々飛び出すのだが、いつまで経ってもシャレにならないのも、困ったものだ。
■この混乱を見ていると、嘘とホントがごちゃごちゃの法螺ならぬホラー。どんどん寒くなる。
■この会社の行く末に正直なところ興味を持てないのだが、こうなってくると「お笑い」の行く末を案じたくもなってくる。いや、待てよ。この手の笑いが、果たしてなくてはならぬのだろうか?