
朝日記180529 Ruth Benedict 「菊と刀」をななめによむことと今日の絵(2021年2月修正加筆版)
おはようございます。日本列島が梅雨の気配をつよめてきました。湿度がたかいようです。体操にいってきました。このところいつもの寺院で、社屋の構えや、屋根のしたの框のつらなりなどを描いています。十二単のころもをおもいなしてペンを走らせています。
Ruth Benedictの「菊と刀」を図書館に通って読んでいます。さあっと斜め読みの気分でひらきましたが、結局 4回くらい通ったことになりました。
「菊と刀」
Ruth Benedict The Crythansemum and the Sword Patterns of Japanes Culture
訳 越智敏之、越智道雄 平凡社
目次は文末にあげます。
徒然こと Ruth Benedict「菊と刀」をななめによむこと
おそらく日本の有識者にはショックであったろうと推察します。文化人類学者として、日常の日本人の言動から日本人の意識と行動方式へと切り込む。その糸のたどりかたがスリリングであり、読者を飽きさせない。忠孝仁義を権威序列順位の異なる4つの基本ドグマとしてカードを一式手にして、相手同志が問題解決ゲームとして意識のすり合わせ運動によって予定調和的な合意を探索する、そのような社会的(道徳)規範の定式の存在を説明します。これを動かす人倫価値としての「恥」の概念を前面に押し出しています。なによりも「ひとである」ことが(人倫)価値の第一義とみます。社会はあまたの数のゲームが進行しているがここでのチョンボやルール違反は、当然プレーヤにとっての存在資格にかかわる評価分岐点であるとみます。この進行のなかで、サムライのごとき研ぎ澄まされた集中力の存在のもつ社会での品性付加への貢献力をも説明されます。ベネディクトは、この段階で、ゲームとしての勝負のつけ方について、上で言う忠孝仁義のカードの使い方のなかで、ひとの価値意識の構造について触れていきます。日本人の意識のなかでの優位価値は、階級序列という政治旧体制力がそのまま順位を定めているとして、天皇を国民の最上優位(至上)価値としているとみます。「誠心」という人倫価値は、ここに報身集中純化した意識とみます。結局はそれは人的(政治的)超越序列としての存在化なりとしてみる。それからの脱離を「恥」とし、人倫価値の喪失とし、その回避のために自らの命を賭けるとみます。
著者は、これを西洋での「超越」(神)との契約いう内面性の価値観とは異なるとみます。「超越」というとばは直接使いませんが、ユダヤーキリスト教基盤、とくにプロテスタントの宗教的意識である「原罪」としての意識をとりあげ、これと「恥」意識とを対比します。前者(「原罪」側;西欧側)は、超越とひと(個人)との契約を、社会契約よりも優先する意識(精神性)を第一優先原理とする。ひととの関係は、その意味で第二義的位置づけとします。第一原理的な理念(規範)が根底にまずあって、これから現実条件への取り組み(契約)がはじまる。これを「恥」の意識構造との違いを対比し説明していきます。彼女は、日本人の意識からうまれる理念には国をこえた普遍性がない。(超越概念とつながらない)から世界規範をあたえる指導国になるための内容を 備えていないとみる。哲学としてもローカル的で他国民に対しての説得力がないと言い切る。Ruth Benedictは、とはいえ、この「罪」意識と自由と平等を掲げる民主主義との関係をここで説明しているわけではありません。単に、理念に関わる判断力はその思考階層として、ゲーム遂行の意識判断力よりも認識論的に上にあると区分します。彼女は、日本人が、理念次元での反省的判断力よりも、ゲームルールを全うする技能的(規範的)判断力にその価値の重きをおく民であると断じます。したがって近代国家の民としては、ニューギニア土民社会のような理性的未熟性を含むとみます。日本占領政策のひとつの有力背景でもあったとおもいます。
ところで、最近読んだ、カール・ヤスパースの「責罪論」Schouldt Frageをここでおもいだします。彼のこの著は、ドイツ敗戦の間もない1945年ころに書かれたものです。かれは責任一般について論考し、現在のドイツの基本姿勢を決定づけたといわれます。彼は責任を負う、罪として、形而上的罪、政治的罪、道徳的罪、刑法的罪の四つに区分し上げ、これに対するドイツ国民の贖罪を説いています。そのなかで、この最初のものを除くあとの三つは、ドイツ国民が償うべき対象とします。、一方、最初の罪は人間としての「原罪」に関わるもので、1.これについては人類共通の罪であり、贖罪のための歴史的努力が負わされていること。2.この歴史的命題として近代文明進歩をさらに選択することの必然性があること。3.したがって、戦勝国も敗戦国もともにれからも形而的罪を負うべきと主張している。(逆説的な見方をすれば、見積もり計算できない責任は放置することにもなります) これが、本当に、現在の西洋の根底認識として共有されているかどうか確信をもちませんが、Benedictの説明はやや皮相的な観は否めません。また、一方、「国民総責任」と単純に割り切ってしまい、「禊」(みそぎ)をしてしまって、理念としての掘り下げもない(たとえば上の2.「近代文明進歩」はほんとにただしいかなど)、わが方の歴史的意識構造では、世界がどうあるべきかという知にまことにとぼしい。また単に「平和」というだけでは願望次元にとどまり、理念として自分の国日本の次元にとどまり、人類次元での、説得力がとぼしいということになります。(余談ですが、あのヒトラーも日本をそう評価していたようです)
私見としては、それ以上に、われわれが、ある日忽然として、、この国の存立に関わる重大な意思決定に迫られる状況におかれないとはいえません。(すこしも騒がず)ここに至るさきに、理念にもとづいた采配の舵が粛々としてあり、為すべきことが整備準備されている理性国家に至っているか、もういちど問われることになります。
さて、Ruth Benedictの立場からみますと、1944年6月という、ドイツの西部戦線に決着がつき、日本への勝利も見通しがでてきたときでした。この時に、終戦に持ち込むための戦略決定に急を告げいたと考えられます。基本的に日本をどう理解するかが、急きょ問われたといいます。このときにBenedictの学問に白羽の矢があたった。彼女の学問上の識見が、ある意味で日本にって決定的であったということを知ります。その枠組みでこの本をよむ意味があるとおもいました。
主張が単純明解で、分析的に問題がのこるとはいえ、おおいに説得力があったであろうことは容易に理解できます。そして現在は、それでどうであったかについての問いかけが、断然、活きていることを感じるものであるます。終わりですが、彼女のなかにある日本への理解への知的接点として賀川豊彦と鈴木大拙のふたりの巨人の存在が大きかったことをあえて書き添えておきます
。長くなりました。失礼。
ご参考まで この本の目次を記します。
~~~
研究課題 日本 戦時中の日本人
「各々其ノ所ヲ得」
明治維新
万分の一の恩返し
「義理ほどつらいものはない」
汚名をすすぐ
人情の領域
徳のディレンマ
修養
子どもはまなぶ
降伏後の日本













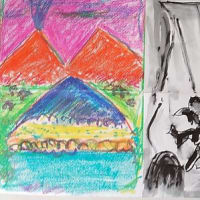













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます