(朝日記190108 (酒神礼賛その2) 話題 「習作自画像」)
~~~~~~
その2 話題 「習作自画像」[1]
話題 「習作自画像」
技術者としての徒然こと
商船大学と明治学院の先輩に送った手紙

~~~~
話題 「習作自画像」
2008年の夏に 埼玉は浦和の学習塾「はなまる学習塾」の若い先生方に語ったシリーズの内、荒井の部分を掲載します。[2]
(目次)
1.わたくしの略歴
~ふるさと
~戦時体験
~終戦をむかえる、闇市と「はぶゆー・あ・ちょこれっと?」
~父親のこと、知的な刺激をうける
~キリスト教教育のこと、明治学院に学ぶ
~横浜山手の丘から、はるか客船ウイルソン号を望む
~ルネッサンス的人間像への憧れ、”よし きらいなことに挑戦しよう”
~ニュージーランドへの遠洋航海、自分探しの青春であった商船大学
~原子力船の乗り組みに志願しよう、東京大学に行こう
~機械工学大学院で熱工学を専攻する、「七輪の火も、原子炉の火も熱反応で同じ、反応現象な
ら化学産業だ
~化学を熱現象として見てみる。コピュータの技術応用に夢を馳せる
~コンピュータに化学技術の夢を乗せる、アメリカに行こう
~およその職歴
2.ちょっと語っておきたいこと(1)
宇宙飛行士になりそこなったキリギリス
3.ちょっと語っておきたいこと(2)
「お稽古事のまとめ~`わたしの羊よ`、声楽レッスンの10年に思うことごと」
i 声楽レッスンの動機 ii 素朴な期待感 iii 具体的にやってみたこと
iv レッスンの記録 v レッスンによる効用 viii わたしのよろこび
翻訳詩を数編
4.参考になりそうな考え方、あるいは態度について(1)
「参考になりそうな考え方、あるいは態度について」
5.参考になりそうな考え方、あるいは態度について(2)
「歌曲、いわしの歌、ってありますか」
ゲーテの‘ミッシイグ・リング’ すみれ、鱒、野ばら、そして?
6.参考になりそうな考え方、あるいは態度について(3)
私の65歳
~そのころの自分についての捉えかた ~セカンドの職について
~セカンドで、特技を生かすということ ~なにに苦しんだか、どう考えたか。
~「これは、仕事なのだ」 ~自分の専門を大切にする
~「 哲学がなくては、 飯が食いつづけられない」 ~ 「食うために生きる」こと
~「生きるために食う」こと
7.おわりに ~自画像とはなにか、なぜ自画像を描くか
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(本文)
若い世代と語る HEART きみたちへのメッセージ
「習作自画像」
HEARTの会
荒井康全
1.わたくしの略歴
~ふるさと
多摩川の下流は六郷川と古くからよばれていたが、多分、砂が堆積してできた中州を指しているのであろう。東海道、川崎の宿はそのひとつの郷にあったと想像する。わたしの生家はその周辺の農家のひとつであった。
家は江戸のしかるべき時期に摂津の方から来たらしいが、まだルーツをただしていない。なるほど尼崎と川崎かと地勢的類似性を思う。いずれにしても開拓団移民であったのであろう、
地誌を散見するに、江戸時代至って、盛んに干拓が行われたようだ、地名に池上新田、田辺新田、小島新田などが残っている。「荒井新田」というのがあったという、横浜の歴史博物館での展示でそれを知った。鶴見区史をみると、確かに荒井という一族が親子二代にわたって干拓をおこなっている、結局 風水に流されたということらしい。それ以上のことは、これから調べておきたいが、その直系なのか、その下男のながれなのかわからないが、今回には間に合わない。自分の先天性について語るためには過去としては短かすぎるし、自分自身の後天性について語るには長すぎるのである。
38年神奈川県川崎市川崎区小田にうまれる。
父健蔵、母うらの長男として生まれる。後に二人の弟が加わるが、この時点では、2歳違いの姉に私を加え4人の家族であるが、当時は父の両親と、まだ娘時代の3人の叔母たち、そして徴兵で外地にいる叔父で構成される十人に及ぶ大家族であった。 生後三ヶ月でリンパ腺炎での手術を行っており、「腺病質」ということばがいまも耳になじんでいる。また、小児麻痺の初期であったのであろうか、ある日突然に片足が棒のようになり歩けなくなってしまった。親は医者を探すこと、神仏に頼めることなどすべてをやってくれたようだ。 占いの神託では、端午の節句の折の鯉幟を立てるための穴の位置が、地神の癇に障ったという。寡黙で強面の祖父が、大きく育ったら親孝行をせよと幼い私に言い聞かせたという。幸いなるかな、なにかのきっかけで、回復すると、こんどは近所の餓鬼なかまに入って真っ黒になってトンボとりやフナとりに走る、やんちゃな男の子への軌道に乗っていった。京浜地区工業化の中にも、まだ各処に田園が残っていた。
~戦時体験
44年川崎市立前沼国民学校に入学。出征軍人を送る歌を祖父の背中で聞き、そして自分もその行列で旗を振っている。戦時色が日に日に強くなり、大人の会話から、ただならぬ変化が起こることを感じ取っていた。 夕食後の家族の団欒、ラジオから流れる広沢虎蔵の「旅行けば」ではじまる浪曲、ひょっとした弾みで、満州の話、そして「おい、満州に行こう、連れてってあげよう、明日の朝」で、戦況や銃後の話に華が咲く。いつ満州に行くのか心待ちにして、それなりにわたしは傷ついていたが、この家族にとっては、いっときの平和な時期でもあったであろう。
やがて、防空演習、国防服、もんぺ、頭巾、地下足袋、ズックの肩掛けなど、そして初めての空襲警報。夜間空襲で聞く空気の鋭いうなり、そして体を吹き飛ばすような炸裂音。囲炉裏の灰が天井に舞い上がった。爆明で見えたのだとおもう。百メートルもない距離の中学校の校庭とそれに続く住宅、田んぼにいくつもの爆弾が落ち、だれだれさんの一家が全滅したという。いくつもの爆弾池がその威力を残していた。
~「大師様があるから家は焼けやしねえ」
祖父はよくそう言っていた。川崎には、厄除けで有名な川崎大師がある。一方、父は近くの電機会社の工場で潜水艦の主機モータ組み立ての現場主任をしていた、あるとき父がその機械とそこに立つ人間を私に、そおっと鉛筆で描いて見せた、山のように巨大なものらしい。そしてこれは秘密だといって塗りつぶした。ともかくも父が立派に思えた。家族は、川崎からは離れる様子がなかったが、火災の延焼を防ぐための家屋の取り壊しがはじまると、さすがに 母は姉(8歳)とわたし(6歳)をつれた疎開することになった。 が、行き先がない。母の遠縁を頼って茨城県の鹿島の近く、利根川沿いの徳島という地へと疎開するが、それもつかの間三浦三崎の漁港の町へと転々とする。徳島では、父が訪ねてきてお腹をこわししばらく寝込んで、帰っていったこと。 あるとき 私は家の無花果の木にのぼって実を食べているうちに、バランスを失して、あっと思う間もなく下の堀切の水のうえに転落したことなどを思い出す。
三崎には祖父と叔母のひとりが、ときどき来てくれた。 祖父のためにバス停で吸殻のたばこ
を拾って感激させたりした。
そのようなある夜に 川崎に大空襲があった。 それで家をことごとく焼失した。父は家財
を守るか、自分の書籍にするか迷ったらしい、彼の決断は両方とも火の中におき去った、がただひとつ 伝来の阿弥陀如来の木像を、井戸のなかに投げ入れ、数キロメートル先の家族たちのもとに走った。 途中、そして燃え盛り 阿鼻叫喚のひとを救けたりして、ようやくにして祖母や叔母たちのもとに、たどりついたという。
この事態で、わたくしの母は、自分の夫と生死をともにすべき時と決し、三浦三崎を引き払い、いそぎ川崎に向かった。途中、京浜急行の追浜駅に爆弾の直撃があったが、われわれ母子は、ひとつ手前の駅にあって救われた。ほうほうの手で川崎の父のもとに帰り、焼け野原のバラックに親子がおさまった。

~終戦をむかえる、闇市と「はぶゆー・あ・ちょこれっと?」
天皇陛下の声を初めてラジオで聞いた、尊いひとは、高い声なのかなあと思った。近所のひとたちと一緒に聞いていた、炒り大豆を食べながらだったと思う。近所のおじさんや 動員で働いていた朝鮮の青年もいた。これからどうなるのかと元無産党だというとなりのおじさんと動員青年との口論がはじまったが、それ以上の争う勢いとならなかった、不安ななかにも、どこかほっとしたあかるさがあった。もう空襲がないことがうれしかったようにおもう。 まもなく、駐留軍のジープが、トラックが、長蛇となって、近くの第一京浜国道を東京へと向かっていく光景を見る、母親はサツマイモをサッカリンで甘味を作った代用今川焼きを焼いては、闇市で商った。
地回りがきても気丈夫に渡り合っていた。わたしは、焼け跡の工場から歯車を4つ失敬して台車をつくり、うなる音をジープに見立てたり、ときに、国道に出ては「はぶゆーあ・ちょこれっと」とジープに声をかけ、チューインガムを投げてもらった。いちどおおきな缶詰を投げてもらった、何の缶詰であったろうか、わすれたころに、それがどんぐりか なにかの粉に変わっていたことを知った。
さてこの間、ずい分学校に行っていなかったように思う。 もとの前沼小学校の校舎は焼失
していた、焼け残った市立新町小学校に間借りし、やがて、その小学校に糾合された。蓋のない机、二つの椅子に板を置いて三人がけにして座る。授業時間中鉛筆を無心で削っている子がいた、油紙で塞いだガラス窓等々、冬の時雨のときは、足のつま先が痛かった記憶がある。とにかく家に帰りたかった、家もトタンで雨露をしのぐ陋屋(バラックといった)であったが、それでも家がよかった。勉強ははるか遠くにあるような気がしていたと思う。
~父親のこと、知的な刺激をうける
「お前はできる、かならず川中に入れ」、まだ学校に入る前だったとおもう。川中とは、神奈
川県立川崎中学校(現在の県立川崎高等学校)のことで、当時、国民学校からは級長の子でなければ入れない学校だったという。 そこの中学生たちの 何か後光の射した通学姿にあこがれをもって眺めていたようにおもう。 銭湯帰りに、中天の夜の星にねがいを賭けようとも思った。一瞬の光芒の消滅はなにか願いの無謀さを告げているようであったが。
戦後まもなく、父は会社の労働組合の創設に係わり、そのリーダーに推された。初期の労働運動であったから夜も遅かった、若い組合の人たちが、よく深夜 バラックの我が家に立ち寄り、私が寝ている傍で、大議論をやる。 新しい時代がきた、すぐにでも社会主義革命が起こるのではないか、訳わからず、なにかすごいことになりそうだと思った。 議論に一段落した合間などに、ときおり ちょっと挟むかれらの学生時代のことなどの会話が交わされ、カントやデカルトなど 製図や力学など森羅万象に話が及ぶ。 そういう会話のなかで 自分のまだ知らない、はるかに向こうの世界を感じとった。 その多くが機械や電気や法律など、さまざまな学問を大学で学んだひとたちであるということも知った。 また大学を出ていないひとのなかにも、勉強を積んだりっぱなひとがいることも知った。 どこか知的な興奮が漂っていた。
勉強すれば、あのようなひとたちになれる、それにもしかしたら、あの運動会の予行演習でみた気位の高そうなマドンナに対してだって、一定の尊敬を受けることが出来るかもしれないと思った。 生涯の友達であるM君が転校してきたのは、小学校4年の2学期であったとおもう、勉強ができて、気風がいいライバルが現われた。
私の父親は、組合に推されて 川崎の市議会議員に立候補し、当選を果たしていた。わたし
の「川中」はまだ遠くにあった。

~キリスト教教育のこと、明治学院に学ぶ
昼休みに友達とじゃれついて、子犬のようにどちらかが追っかけて遊んでいた、わたしが逃げるばんであった、息せき切って、校舎の屋根裏へ逃げた、そこはもう袋小路だ、どうしようか。薄暗がりに ひとがいる。 よくみると集会をしている、みんながお祈りしている、そうだと思ってそおっと 仲間にまぎれ隠れた。 追い手が、迫る。 そして あれっときょろきょろしていたが、やがて そお状況に気づいて、 彼もそこに入って座ってしまった。 キリスト教の学校のクラブであった。ふたりとも「宗教部」に入ってしまったのだ。
私はキリスト教の学校である明治学院中学校を受験させられた。島崎藤村が出たというハイカラな雰囲気の漂う学校であった。 面接の試験に失敗して、補欠で入れてもらうために父親は、たいへん奔走した、「あれを落したのはあなた方が間違いだ、一学期だけためしてくれ、それでだめならいつでも引き取る」と頑張ったらしい。 組合でのキャリアーが、押しをつよくさせていたのか、ともかくそれで入れてもらった。 ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」、あの主人公の少年ハンス・ギーベンラートの名前をいまでも覚えている、NHK のラジオ 加藤道子さんの「わたしの本棚」の朗読であった。憂鬱であったが、 ハンス少年のように夢中で頑張った。英語のリーダの一冊丸暗記を敢行した。'th'の発音で猛烈なヒステリーをおこすオルトマス女史の英会話の授業も快調に飛ばした。すべての学科の予習と復習を試みた。そして、いよいよ夏休みがはじまったある午後、M 君と一緒に京浜急行の花月園にあるプールの水泳から帰ってくると 母親が学校の父兄会から帰ってきた。 まず「おまえ、よかったねえ」と誇らしげに、ほめてくれた。 その夜 みんなで川崎の繁華街に出て食事したとおもう、そして御祝いにテニスのラケットを買ってもらった。明治学院の学校生活は軌道に乗っていったとおもう。
父は、宗教に思いを持っていたひとであった。戦前から教団「生長の家」の誌友会であった。
この宗教は、スピノザ的な汎神論のながれにある思想であったろうが、基幹は皇国思想であったと思う。戦後、自ら選んだ社会民主主義との間の思想的葛藤に悩んでいたようである。あるとき組合機関紙が、父の寸描記事を乗せた。そのなかで、時代の過激なながれのなかで、ものごとに対して批判的、懐疑的な思索の傾向を示しはじめた息子に触れ、敬虔な内面性の経験を涵養していくことの必要を感じているという感想を述べていた。 息子について そのような関心を示してくれていたことに感動をおぼえたことを記憶している。 かつて祖父の事業の失敗で、神奈川県立第二中学校(現在の翠嵐高等学校)の試験に受かりながらも、一家の生計ために断念しなければならなかった、そのなにかが、多分わたしの上に投影していたようにおもう。

~横浜山手の丘から、はるか客船ウイルソン号を望む。
夏の陽光の下、きらきら光る紺青の海、メリケン桟橋に客船が入らんとする。巨大なライトグレーの、華麗な船体、白いブリッジとそれに続く白い居住のエリア、その上に鷲の飛翔のファンネル(煙突)、米国の客船プレジデントウイルソン号だ。白い半袖の士官服のチーフオフィサーが船首にあってきびきびと指示している、あでやかな原色っぽいいでたちの人影が動く、そんな光景である。 いつのまにか、桟橋近くに自分を立たせている、いくつかの記憶が重なっているらしいが、そのとき、誓うものがあったとおもう、船にのってアメリカに行こう。
また、ハリウッド映画「二人でお茶を」を鑑た。中学校のときの夏休みで、これもM 君といっしょだった。ヒロインのドリス・デイのタップダンス、プールつきの広大な邸宅、足のすらっとした若者たちが歌い、抱擁する、この世の中にこんな国がある、こんなに陽気で、眩しさに満ちた社会がある、そして一方に 貧しく、しょぼくれたわが日本がある。「あこがれのハワイ航路」は不滅のカラオケ定番であるとおもうが、当時ははるか遠い現実のように思われた。なんとしても現実を引き寄せようという思いがわたしに起きていた。船にのってアメリカに行こう。
~ルネッサンス的人間像への憧れ、”よし きらいなことに挑戦しよう”
都立一橋高等学校に入る。 熱病に罹ったように都立日比谷高等学校を受験したが、見事に
落ちた。私の高等学校は、浅草橋にあって、もともと女学校が母体であった。男女共学で、男子は全体の二十パーセント程度で少数派であるから、いきおいクラスの結束はよかったと思う。あとで考えれば、ここに残っていても何の問題もないのであるが、日比谷落選組みが 転校を密かに模索していた、なんとなく落ち着かなかった。
夏が終わると 熱っぽく語っていた友人は残り、私が転校して、神奈川県立湘南高等学校に
移ることになった。このときの友人とはいまも続いている。湘南校は、当時有名な受験校でもあり、鎌倉、鵠沼、茅ヶ崎などこの地方独特ののんびりした空気があり、また自由な気風があったようだ。科目のスタートの取り遅れた分は気合で生きる決意をした。
アメリカ帰りで気負い気味のM先生に授業中に食いつき、目に留められ、彼の英語の時間に、公開質問時間「荒井タイム」をもらう。必死になって文法書を調べ先生の解釈に異を唱え、対抗するという筋書きでまわりの秀才たちに、一種のエンターテイメントを提供したようなものであった。 コーラス部に入る、生徒会委員になる。生涯の友となったH 君等とは、ここからはじまる。この学校は、二年間でコースが終わる方式で、数学は、解析と幾何が2科目平行、理科は物理、化学、生物の3科目並行で、特に出遅れた数学と物理の調整に手間取った。これが、以降の私の生き方に陰に陽に影響し、いまに至っていると思う。つまり数学と物理コンプレックスである。 英語や世界史は快調であった。一度はこのような世界に進むことを考えたが、不得意なもの(嫌いなものがあるということを認めようとしない)をそのまま残すことに拘った。 そのままでは、残念とおもった、たまたま出会いがわるかっただけであり、自分の向き不向きにかかわりないと考えた。
たしか国立大学一期校は八科目であったから嫌いなままでは済まされないという切迫した事情があったかもしれない。 あるいは、最後に理系コースである商船大学に焦点を置いたときのこじつけであったかも知れないが ともかくそう考えることにした。 世界史が得意科目であったから、古今東西から、いろいろな人間像を曳き出し、自由に思いを馳せる、理想的人間像をルネッサンス世界に求める。 ダ・ビンチでよし、聖フランシスコでよしであった。
これらの全人格的なものに現代人は達することができるか、分科した時代では、ただ考えることだけでおわりであろうかとも思った。しかし、とりあえず、つぎのようにその道筋を想定してみることにする。
ひとつ、好きなことは出来たとする。
二つ、いま苦手とおもうものに賭けてみる。
三つ、きらいなものが好きになったときに 全人的な接近がおこなわれたとする。
~ニュージーランドへの遠洋航海、自分探しの青春であった商船大学
眉目秀麗であることということが入試要綱に入っていると聞いたことがあるがほんとか、と訊いたひとがいる、わたくしの顔をチラッと見たようだった。 裸眼で視力1.0 とか、綱に片手でぶら下がって10秒以上とか、あるいは、性病検査とか海洋日本の伝統的な独特の体力試験があった。「紅顔可憐の美少年」で知られる寮歌が、事実を虚飾するのかもしれないが、わかいときはだれも、それなりに、意気がいい。
商船大学は 当時東京と神戸にあった学校が戦時統合され静岡県清水市にあった。伝説羽衣で知られる三保の松原の砂浜のなかにあった。満月の夜は、駿河湾の海がきらきら光り、遠く伊豆の対岸や達磨山の灯が見えて、切なくもうつくしい。 「完全就職、陸の倍の給与、たばこも酒も免税で、しかも外国が見られる」、たしか雑誌蛍雪時代での紹介であった。
そして、1956 年(昭和31年)目出度く機関科に入学する。そして 低空飛行で1960 年(昭
和35年)秋に5年半の過程で東京越中島の地にて卒業。 卒業実習は6ヶ月、最初の3ヶ月は三菱日本重工横浜造船所 いまの‘みなとみらい’の場所である。 あとの6ヶ月は運輸省航海訓練所の生徒になり航海実習にでる。 練習船大成丸という3千トンクラスで日本列島を周航して、瀬戸内海で特訓を受けると、ニュージーランドへの遠洋航海にでる。 長駆赤道を越え、熱帯スコールに身を洗い、ブーゲンビルの夕日を望見し、いくつか南十字星を仰ぐとやがてクック海峡に投錨する。 折りしも雨雲が切れて陽が射す、波洗う崖の海岸線に鮮やかなみどりの丘陵が目の当たりに現出する。 赤い屋根のバーンやサイロがある、たくさんの羊の群れがある。首都ウエリントンに着いたのだ。 ときに、”六十年安保” 東京はデモの渦で騒然としいたときに出航したが、国際放送は、池田勇人内閣の発足を報ずる。いま思うと、自分の生きるべき道筋と現実の学問・教科にしっくりしないものがあったのだと思う。 それを認めたくないから困ったものであった。 この辺のところは、いずれ、もう一度整理しておこうと思うが、物理にも数学も その他もあまりこころ踊るものではなかった。
それ以上に基本的には、外国を無料で行きたいというところにあったから、相対的に手段としての位置づけになる学業が軽くなってしまったのかもしれない。 初めて家を離れたという開放感とみずからの責任で方向を定めるという自意識との葛藤があり、思索は旺盛であるが、意欲に敏でなく、なんとなく身を浮き漂わせていたように思う。 石原慎太郎の芥川賞作品である「太陽の季節」に障子を破る下りがあったが、持てるエネルギーが向かうべき何か、当たるべき壁の喪失感のあった時代だったように思う。 思えば日本が経済大国として離陸しようとして必死にもがいている時代でもあった。 成績のよいクラスメートに対する競争心はあまりおきなかったし、むしろ冷ややかにみていたと思う。
蒸気タービンの実験の時間に、側の十メートルほどの水槽を、往復して帰ってくる賭けを引き受け、実際に実行して担当教官を烈火のごとく怒らせたことがあった。この教官には、後に就職した会社からの米国派遣の件につき、大変助けてもらうことになったが、当時はそのような状況であった。
~原子力船の乗り組みに志願しよう、東京大学に行こう
「あなた、あれほど勉強しないのにこれから東京大学に行くって?」、母は意外に思ったらしい。 惰眠を貪ってきたが、卒業航海が近づくにつれて、それまでの自分を振り返ってみる。すくなくも受験の頃の直向きさにもう一度帰ることの必要を感じた。 船体は揺れて傾いてもまた復元をして姿勢を保つのであるが 自分の復元性をためすのも ひとつの挑戦だろうと思った。 それ以前に文系の大学に入りなおすことも考えたが、これからひとり立ちして食っていくたねは、やはり技術におこう、逃げるべきでない、それをようやく納得しかかっていた。それにしては、いまのこの状態はお粗末であること、やるならその世界で一線に立つべきであるというところまではきた。
飛躍するがとりあえず聴講生で、東大にいってみよう、あとはそれから考えることにした。
これには ヒントがなかったわけではない。卒業研究は、例の水泳事件のD 教官に師事したが、テーマは航路による海水温度とエンジン効率の関係であった。
当時 丸の内のレンガ建てビルにあった飯野海運本社の工務部に通い 機関航海日誌から丹
念に海水温度とエンジン効率算出諸元のデータを集めた。 船会社の機関部門がどのような状態で動いているかが伺えて興味があった。あるときここのN 課長が、帰りにビヤホールに誘ってくれた。 「君、会社に入って陸でやるんだったら、なにか特別な武器をもたなければいけないよ」といって、部下の一等機関士であるK さんの話をしてくれた。会社から東大に留学派遣されているという。 そして その人に会いに機械工学科を訪ねたことがありこれが下地になっていた。もっとも、このひとは、船の大学を首席で卒業している点が、私と大いに違っていたが。
さて、ターゲットは原子力工学としよう、親には将来、原子力船の乗り組み第一号になるために、機関をつくることをやるのだといってしばしの猶予をもらうことになった。 ときは、1960 年(昭和35年)9月、甲種一等機関士の面接試験を終えて、力学の再履修のために東京大学の駒場の教室に走った。
~機械工学大学院で熱工学を専攻する、「七輪の火も、原子炉の火も熱反応で同じ、反応現象なら化学産業だ制度もそうであろうが、ものごとが始まるときは変なことがおきる、とにかく、一年がむしらに勉強して、親の手前 大学院を受験しなければならなかったから受けることにした。夏に大阪大学、京都大学そして最後に東京大学と大学院受験行脚をした。勝率は2勝1敗であった。1962 年(昭和47年)春東京大学大学院数物系研究科機械工学入学となる。
さて、これ以降は、やや話はかたくなるが以下に概略を記す。
~化学を熱現象として見てみる。コピュータの技術応用に夢を馳せる
~コンピュータに化学技術の夢を乗せる、アメリカに行こう
~およその職歴:
64年 東京大学大学院機械工学で熱工学終了。昭和電工入社。
プラント建設設計部門に配属(装置設計担当)。
`東京オリンピックの年。
69年 米国ウィスコンシン大学大学院化学工学。プロセスシステム工学の研究。
74年~98年 現象・プロセス・品質の解析技術の研究所を作り、育てる
;技術計算、管理技術、そして数理技術分野
`第1次石油危機。技術の中心は省エネルギーと軽薄短小へ向かう。
計算機支援現象・プロセス解析(CAE)、計算機分子化学(CC)などによる材料開発、装
置設計、運転品質管理領域への支援と普及推進。
83年 宇宙飛行士に応募、書類審査で落選。
90年~98年 (社)新化学発展協会にてCCの調査研究活動とプロジェクト化推進。 め
でたく、平成10年度大学連携型プロジェクト「高機能材料設計プラットフォームの開発」採択。
98年 昭和電工退職。
ふたたび、忽然として?? 時代の変わり目にある大学と付き合うこと。
98年~現在 武蔵工業大学事務局(国際交流、産官学交流事業企画と推進)
1998年 武蔵工業大学国際交流と産学協同の推進
2002年 東京工業大学資源化学研究所特任教授
2007年 桜美林大学非常勤講師
2007年 人間環境活性化研究会常務理事
家庭:
1967 年(昭和42年)結婚、妻 敏子、一女一男。
1973 年(昭和48年)から1年間休職 幼稚園経営












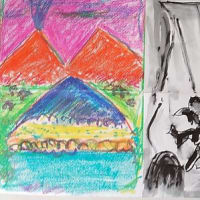













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます