
おはようございます。
今朝は霜がおりていました。快晴です。
徒然こと
孫子通信 3をお届けします。
訳(金子 治)
勝利をよみとるのに一般の人々が分かる(ようなはっきりしたものについて知る)ていどでは、最高にすぐれたものではない。(まだ態勢のはっきりしないうちによみとらねばならぬ。) 戦争にうち勝って天下の人々が立派だとほめるのでは、最高にすぐれたものではない。
(無形の勝ち方をしなければならぬ。)だから、細い毛を持ち上げるのでは力持ちとはいえず、太陽や月が見えるというのでは目が鋭いとはいえず、雷のひびきが聞こえるというのでは耳がさといとはいえない。
昔の戦いに巧みといわれた人は、(ふつうの人では見分けのつかない、)勝ちやすい機会をとらえてそこでうち勝ったものである。だから戦いに巧みな人が勝った場合には、(人目にひくような勝利ではなく、)知謀すぐれた名誉もなければ、武勇すぐれたてがらもない。そこで、彼が戦争してうち勝つことはまちがいないが、そのまちがいないというのは、彼がおさめた勝利のすべて、すでに負けている敵に勝ったからである。
それゆえ、戦いに巧みな人は(身方を絶対負けない)不敗の立場において敵の(態勢がくずて)負けるようになった機会を逃さないのである。
以上のようなわけで、勝利の軍は(開戦前に)まず勝利を得てそれから戦争しようとするが、敗軍はまず戦争を始めてからあとで勝利を求めるものである。
訳(金子 治)
形篇四ー2 岩波文庫「孫子」p.57)
備考
見勝不過衆人之処知、 非善之善者也、戦勝而天下白善、非善之善者也、故擧秋 (後略 メモ:この文を別のブログに入力中に、特定故意かどうかわかりませんが、 漢文体で本書き込み全体が乱調になったことを
記録しておきます。 )















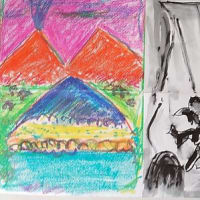









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます