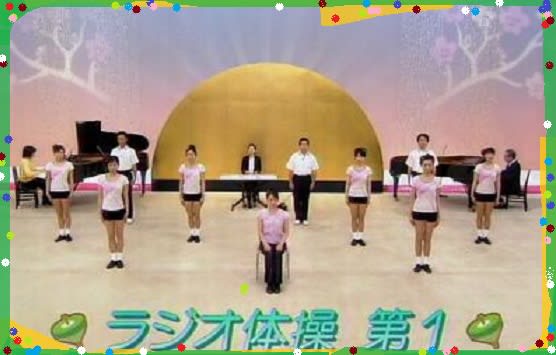◆サンバは優しい処方箋♪◆
去年、友人と共に初めてサンバの拠点クラブ「プラッサ・オンゼ」へ。
ラテンダンスと言えば、
サルサのペアダンスしか興味がなく、、
お付き合いで友人の師匠の演奏を聴き、ハイサヨナラ♪のつもりだった。
耳慣れない派手な音の重なりは大音響と化し、
バンドのボーカルの声は、ビックリするほど浪花節。
歌詞は、日本語だったりポルトガル語だったり。。
それらの歌は、
『生きるって切ないよ イヤになるけどさ、、
躓いても立ちあがる勇気出そうぜ!
一緒に歌ってくれる友もいるじゃないか!』
どん底の歌なのに、ナヨナヨ クヨクヨしてない…
顔を上げて、チクショーー!負けないぜ。。的な人生の応援歌。
内心では「うわぁ、、演歌ダゼ」と慄いていた。
◆サンバは海馬に優しく 右脳を豊かに♪◆
同じラテン音楽でもサルサの場合は、
メロディアスだったり、どこか風景を感じさせる。
聴き慣れたスペイン語の語感にはエロ感が漂う。
だがエロ感や哀愁のメロディの歌詞は
<火事で家が燃えて~みんな死んじゃった~>という歌でも、
スペイン語の歌詞が分からないため、
見知らぬ男女は雰囲気たっぷりで踊れちゃう。
男性はオトコを満喫し、女性はオンナを思い出す。
たとえ一瞬でも
踊る相手を敬い、気遣うのがマナー。
だがサルサは心が不健康だと、ダンスも不健康になる。
一言で言えば、デリケートでめんどくさい、、
ラテンダンスはそんなものだと思っていた。
それが
サンバは一般的なラテン音楽とは全く違った、、
アフリカから連れてこられた奴隷たちのソウルが「サンバ」という形に。
楽器も違うが、リズムが2拍子らしい。。
慣れないリズムに乗ることでいっぱいいっぱい…考える暇などない。
日常生活では思考停止なんて滅多にならず、
いつも何がしらかの不安がドーーーンと居座っている。
が、不思議なことに
あの派手な大音量とリズムは、マイナスの思考回路に良く効いた。
左脳を使わず、右脳が活発になることで脳内麻薬が出たらしい。
サンバライブが終わり
ボーカルの浪花節クンが、ワタシに放った言葉が図星だった。
『サンバってイイでしょ♪元気になるでしょ!』
そしてサンバはホントにそういう背景から生まれた歌と踊りだった。
1888年 ブラジルでの奴隷制度が廃止され、
仕事を求めてリオ・デ・ジャネイロに集まりだした。
居住地区はプラッサ・オンゼ(第11広場)
ここで育まれたサンバは居住区が解体されても、
細々と残り、それでも徐々にブラジル全体に広まった。
今もそうだがブラジルの格差社会はかなり酷い。
リオのサンバカーニバルの踊り手は貧困層。
観る人達は富裕層。
友人の師匠曰く
『昔は富裕層が観てたけど
街中が大音響になるからね
お金持ちはカーニバルの時期はバカンスに行ってるよ~
若い人はサンバは踊らない。。
ヒップホップやレゲトンを踊る
サルサもそうだけど
サンバはおじさん・おばさんの踊りだよ」
若い時は
エネルギーを持て余すほど溢れてて、
深い哀しみや憤りは時間と共に消化吸収される。
若者は侘び・寂びのダンスで癒される必要もない。
だけど
おじさん・おばさんと括られる頃になると、
自分が張ってるバリケードはボロボロになっている。
それを治してくれるのは、抗鬱剤でも睡眠導入剤でもない。
胸に届いた音楽だったり、心を無にしてくれるダンスだったり。
海馬を無心にし、右脳を活性化させ豊かにする。。
おじさん・おばさんのダンスには優しい処方箋がついている。
しかも副作用はないの。。。。
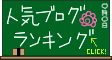
人気ブログランキングへ←ランキングに参加してます。クリックして応援お願いします(*^_^*)