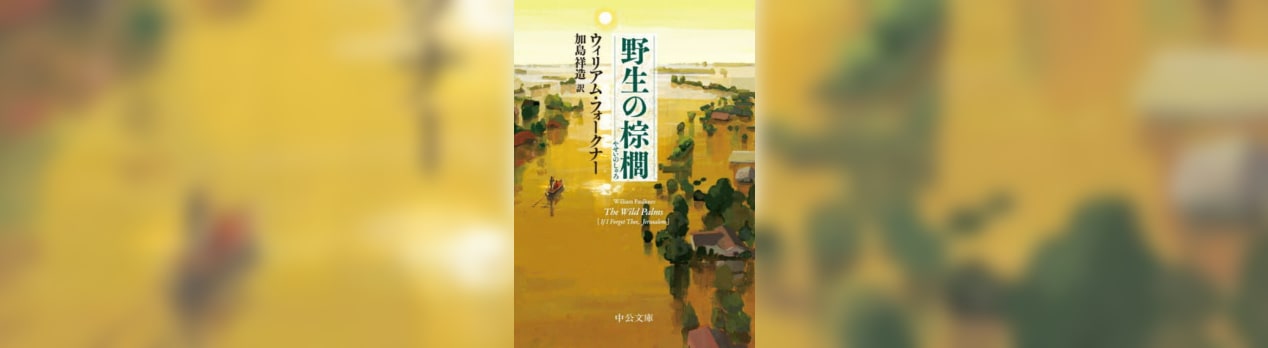フォークナーの『野生の棕櫚』オンライン読書会、みなさんの感想備忘録です。
今回はこちらのお二人。
*** yuiさん
読んだけれど、私生活が大変すぎてなんにも頭に残っていない。
当時の女性が妊娠して手術のしかたとか、その経緯、それだけで一冊になるくらい。この時代に生まれなくてよかったなと。
「オールド・マン」の方は、刑務所から出て流れていって…男の人ってシンプルでいいなあ、というのが率直な気持ち。読み終わって何が残ったかといえば「女の人ってほんと大変」ってことですね。
*** 八方美人男さん
フォークナーを読むのは初めてで、結構骨太っぽい話の感じがしたので、できるだけ早く読もうと思って2ヶ月前くらいに読み終えてました。
正直読むのがきついなと感じまして、特に中盤のハリーが鉱山に行くときに友人に会って自己主張するあたりとか。それと、「オールド・マン」後半くらいで、囚人どうしが語る場面もカッコで囲まれて書かれたり、あれも結構きつくて。
最初は真面目に全部読んでたんですが、カッコは飛ばして雰囲気を読み取っていけばいいか、と。とりあえずバーッと読むことに努めてました。なので細かいところは正直、あんまりよく覚えてなかったりします。
■いかにもアメリカっぽい話
この作品、確かにいろんな捉え方ができますが、私は「野生の棕櫚」のハリーとシャロットの社会のルールに背を向ける生き方をしていくアウトロー的な流れは、実はアメリカという国の一つを象徴しているような感じもしていて。
アメリカの建国って、イギリスのカトリックを拒否したプロテスタントの人たちが新天地に行って…という話なので。そう考えると、ハリーが父の言いつけで医者になるとか、宗教的な理由で堕胎してはいけないとか、過去の社会のルールを疑問視するのがアメリカという国だとしたら、この物語はいかにもアメリカっぽい話だったかもと。
「オールド・マン」にしても、別にその人が意識してそうしたわけじゃないけれど、あるタガが外れて自分の力で金を稼ぎ始めるとか、子供を出産した女性と一緒にいるとかも、なんとなく西部開拓と相通じるかもしれない。
「オールド・マン」で特に印象的なのが何回目かの陸地で、その現地の方が何で稼いでいるのかというところ。言葉は通じないけど、ワニ狩りをして一緒に金儲けをし始めるとか、なんかアメリカのサクセスストーリーみたいな感じ。確かに皆さん仰ってたけど、「オールド・マン」は割と面白いエピソードという感じはしてましたね。
■家や宗教が個人の生き方よりも大事にされていた時代
今、私たちって個人至上主義で、自分の個性を大事にしようという価値観がありますが、でもそれは第二次大戦後くらいの話。この作品の時代背景は、おそらく戦前くらい。個人至上主義的な考え方はそれほど浸透してなくて、それよりは家や宗教が個人の生き方よりも大事にされていた時代。だとすると、このハリーとシャーロットとの生き方はすごい斬新に見えたのかもしれないと想像できる。
今の私たちからすると、確かにもっと現実的になれよっていう気持ちに思ってしまうんですけど、当時の人からするとかなり斬新だったのかなって感じがしますね。
囚人も、無法者みたいな人では全然なくて、なんかちょっとカッコいい感じにしちゃうのが面白いなと。
ただ、正直読んでてきつかった。結構だらだら続くし、このカッコ書きのところとか正直いらないんじゃない?って思っちゃうきつさはありましたね。
***
ありがとうございました!
カッコ内の面倒くささ、私も苦労しました!真面目に読んでしまいました…。そして確かに、アウトローとサクセスストーリー的(またはフロンティア精神?)な対比とも言えそうですね。
そして、ほんと女の大変さをひしひしと感じさせられる作品でした。(スウ)
まだ続く、かもしれません!