「良いか、二人とも。義貞では、この戦は、勝てぬぞ」
後醍醐の言葉に二人の息子は顔色を変えた。明日はその義貞と共に山を降りる身の二人である。それなのに、その行く先が敗北であるとは、親の言葉とは思えない言い様である。
二人の皇子は後醍醐の真意が見えずに唾を飲み込んだ。
青ざめ戸惑う皇子たちを見る後醍醐の目が、細く光った。
「敦賀へ着いたなら、義貞は捨てて昆布衆に頼るのじゃ。そして、昆布衆の船で、十三湊(とさみなと)か蝦夷島へ、渡るのじゃ」
尊良には後醍醐の真意が見えて来た。後醍醐の言葉を待つ。
「義貞はあのような男じゃ。逃げ出そうとすれば切り殺されるに相違ない。上手く騙して、船に乗るのじゃ。敦賀の昆布衆には、我の手の者によって話を通してある」
僧兵か神人か、はたまた異形の男女など、後醍醐の手の者は多い。既にその者を走らせて、手配を済ませているという。
「安東一族を頼って、北へ渡るのじゃ。昆布衆が導いてくれるから、心配は無用じゃ」
後醍醐は不敵に笑みを浮かべた。
「義貞の隙を見て船に乗り、津軽か蝦夷島の安東氏のもとへ行くのですね」
心得たとばかりに、尊良が言葉を返す。
「そこで、何を‥‥?」
恒良も口を開きかけたが、まだ良くは飲み込めていないようだ。
「昆布じゃ。昆布を売り捌いて、銭を貯めるのじゃ。この戦は長引くであろう。我は京へ還幸と相成るが、いつまでも尊氏の手中には留まるまい。安心させるのじゃよ、尊氏と義貞を。戦には銭が要る。昆布で銭を貯めるのじゃ。これしか生き延びる道は無いものと思え。良いな!」
後醍醐の鋭く妖しい眼光を受けて、二人の皇子は平伏した。
息子にとっても後醍醐は怖ろしい存在であった。親だからというのではない。一人の人として怖いのである。後醍醐と比べれば、義貞を騙すなど何ほどでもない。上手く騙して、何としても船に乗らなければ、一族の命運が途絶えてしまう。幼い恒良にも、父の言葉と想いが胸に染みた。
翌日、京へ向かう天皇の鳳輦よりも先に、義貞の軍勢は北へ向かった。尊良と恒良も、輿に乗らずに馬を駆った。
敦賀への七里半越えの峠は、やはり尊氏方によって固められており、義貞の軍勢は別の遠回りでの峠越えを目論んだ。
例年になく早く雪の降った険しい山道を、凍える者まで出しながら越え、漸く敦賀の町に入った。
気比社の神官や神人らが、武装して迎えに来ていた。気比社近くの山城へ入る前に、町の家屋に分散して疲れを休める事にした。
尊良と恒良は、浜に近い商家に泊まる事となった。義貞が付けた警護の武士が家を囲む中、二人の皇子は付き人と共に、その商家の広い座敷に通された。昆布をはじめ、北国の物産を扱う家だった。主人は廻船を何艘も所有して北国と商いをしている商人の一人だ。
その家の主人と、気比社の神人が挨拶に来た。
「お疲れでございましょう。湯もありますゆえ、今宵はごゆるりとお休みになされませ。主上よりは、確かに承ってございます。向こうへも、知らせは届いておりますゆえ、ご安心を」
主人が、外の武士を警戒する目で、指先を彼方へ示した。










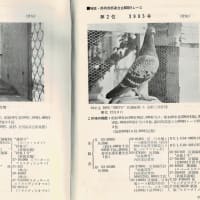

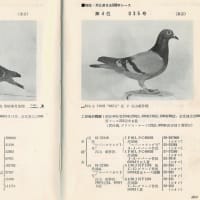







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます