マルクス剰余価値論批判序説 その1
はじめに
驚異は哲学の始まりであると、アリストテレスは言っている。(1)
マルクスはこのように書いて、自分が驚異と出会っていることを隠していない この出会いについてマルクスは、『経済学批判』の序言の中で整理して述べている。
その文章から、マルクスが第一に、「物質的利害」との出会いに驚いたことが判る。そして第二に、「フランスの社会主義と共産主義」に対する驚きが窺える。前者には困惑し、後者には判断できないことを白状したほどの、深刻な驚異だったことが読み取れる。
これらの驚きは、マルクスにとって、問題に遭遇した、問題を問題として自覚させられたことの驚きであって、何らかの答えに遭遇したことの驚きではない。
時事問題というものは……合理的などの問題とも同じように、答えではなくて、問いが主要な困難であるという運命を持っている。……問いは……時代の標語であり、その時代特有の精 神状態についてのきわめて実践的な宣言である。(2)
マルクスは問いを問いつづけ、「問いを分析」しつづけたのである。
この二つの驚きに対して、マルクスがどのように取り組んだのかも、「序言」で述べられている。そして、研究の対象を「市民社会」に設定し、実践的な共産主義運動に参加するなかで、プルードン批判である『哲学の貧困』を一八七年七月に書き上げた。この著書において初めて自分の見解の決定的な諸点が学問的に示された、とマルクスは言う。
したがって、『哲学の貧困』の時期(共産主義者同盟の時期)を、マルクスの思想の成立段階とし、その前後を初期(形成期)および後期(成熟期)とする。
ここで対象とするのは、マルクスが驚いたにもかかわらず、合理化して隠してしまったものである。「社会の土台」や「社会の外部」と呼ばれ、「直接的生産過程」や「労働過程」という経済学用語で示されはしたものの、剰余価値論において「社会」という語によって隠蔽されたものである。










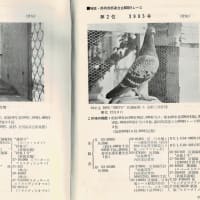

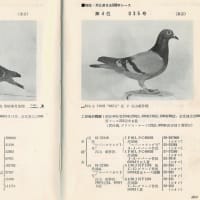







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます