マルクス剰余価値論批判序説 その2
社会の土台(外部)と出会い、経済学研究のはじめに、「国民経済学は、労働者(労働)と生産とのあいだの直接的関係を考察しない(3)」という問題を創出して、この問題に最後までこだわったマルクスであるが、労働と生産との「直接的関係」そのものの内実、あるいはそれらの区別と関連を、明確に認識しえたのだろうか。
たとえば、「土台」(労働活動、労働過程)は「社会」の内部にあるのか。マルクスの剰余価値論では、「土台」は「社会」の外部になければならない。等価交換の「社会」の内部において剰余価値は産まれない。直接的労働が「社会」の外部で行なわれるからこそ、外部を社会が取り込むことで剰余価値が産まれることになるのである。
マルクスは最初に、「土台」は「社会」の外部にあると見ていた。それは、常識的な観点であった(4)。しかしその後、「土台」こそが「社会」であると考えるようになる(5)。
マルクスの社会Gesellschaftの概念は、仏語や英語(société, society)との対峙において明確化され、「社会」と「社会の上部(幻的な外部)」とが、言葉の上でも区別される。しかし、「社会の下部(現実的な外部)」については、社会という語(6)の中に隠されつづけたのである。
そして、マルクスの剰余価値論は、社会の外部を隠薮することで、成り立っているのである。
マルクス剰余価値論批判の序説として、マルクスの社会観から剰余価値論を吟味したものが、以下の論稿である。
(1)「共産主義とアウグスプルク「アルゲマイネ・ツアイトウング」(大月版『マルクス・エンゲルス全集』--以下『全集』とのみ表示--第一巻、一二四頁)。
(2)「中央集権問題、それ自体についておよび『ライン新聞一』一八四二年五月一七日火曜日第一三七号付録〔へス論文〕について」(『全集』第四〇巻、二九七頁)。
(3)『経済学・哲学草稿』岩波文庫、九〇頁。
(4)「ただ特徴的なのは無産の状態と直接的労働、具体的労働の身分とは市民社会の一つの身分をなすよりはむしろ土台をなし、市民社会の諸サークルはその上にのっかり、その上で動くという点のみである。」(「へーゲル国法論批判」、『全集』第一巻、三二〇頁)。
(5)『独仏年誌」の二論文でマルクスは、世界がゲマインシャフト(あるいはゾツィエテート)とゲゼルシャフトとの二重的なものであることを指摘し、「ルーゲ論評」において「生活そのもの」としての労働者の共同体を「土台」に位置づけ、そこに「社会」を見ようとする。そして、『経・哲草稿』でゲゼルシャフトの概念規定をゲマインシャフトの批判の上に練り上げて、パウアー批判 (『聖家族』)やシュティルナー批判(『ドイツ・イデオロギー』(第一巻第三篇)をその社会概念によって行なった。マルクスの社会概念は、『哲学の貧困』や『賃労働と資本』で完成するが、剰余価値論の形成と併せて揺らいで行く。
(6)日本語の「社会」は、マルクスのゲゼルシャフトとは異なっている。「社会」という語は、明治維新以降に生じた新たな事態に対応するために使われた語(翻訳語)であるが、「世間」や「国」など明治維新以前の事態の意味をも抱摂して使われるようになった。それは、「社会」という語が支配イデオロギーに組み込まれる過程である。支配イデオロギーとしての「日本語」への批判は、それが天皇家の言語であるというところにではなく、語(例えば「社会」)の意味がどのように形成されているのか―語自体には、意味はないのだからーを追究することの方が、現実的である。










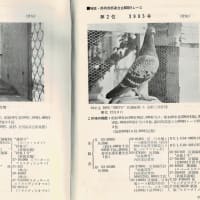

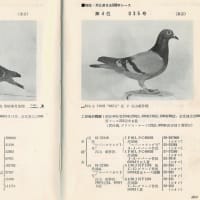







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます