そこで昆布衆をはじめ気比社の神人・僧兵ら三百人は、北の杣山城から援軍が押し寄せた風を謀るために、中黒の旗を何百本も夜のうちに山の木々に結び立て、夜明け間際に敵軍に飛び込み、「杣山よりの後攻めに仕る。城中の者ども出向いあれ。敵を討ち取るべし!」と大声で叫び回った。
寄せ集めの敵の軍勢はこれに驚き、我先にと近江・若狭へ逃げ帰った。敦賀の町には一人の敵兵もいなくなり、功を奏した自らの奸計に昆布衆たちは腹を抱えて笑い転げた。
何が起こったのか知らない義貞は、城を幾重にも取り巻いた敵が忽然と消えたのを怪しんだが、気比の大神の仕業であると話す神人の弁を真に受けて、これも天子様の威力と悦に入って喜んだ。
このようにして平穏になった初冬の晴れた日、敦賀の商人たちは義貞に船遊びの宴の挙行を申し入れた。これは時元の計画で、宴に酔う義貞から尊良と恒良を密かに連れ出し、身代わりを立てて刻をかせぎ、大船で逃がそうとするものである。
敦賀の船遊びは、京へも聞こえた優雅なもので、申し入れを受けた義貞は寸分も怪しまず、城を降りて宴の船に乗り込んだ。
船遊びの宴は十月の二十日(新暦の十二月四日)の事であり、野坂山の峰は早くも白く輝き、真っ青に抜けるような空の下、神妙に静まった波の上に百を超える船を浮かべ、船遊びの宴が始まった。義貞は上機嫌で横笛を吹き、恒良と尊良は琵琶、洞院實世は事を弾き、笙や打物も加わって、賑やかに騒ぎ遊んだ。
遊女たちも船で集まり、鮮やかに舞い、華やかに唄う。
近づいて来る小船に時元の姿を認めた尊良は、同船上の義貞の様子を窺った。義貞は恒良を側に置き、遊女に酒を注がせて笑っている。顔は赤く染まり、波にではなく酔いに揺れている。とろんとした目は今にも眠りに落ちそうだ。
「今だ!」と尊良は思った。
しかし恒良は逃げ出せそうにない。
「将軍様。一宮様には、あちらの船へお越し頂こうかと存じますが」
商人の一人が義貞に注進した。将軍と呼ばれて、義貞はますます有頂天になった。武士や公家たちも、次々と遊女の船に乗り移っていたから、大人の尊良がそうしても怪しくはない。
「構わぬぞ。一宮様はおなごの船へ参るが良い。しかし天子様は色事にはまだお早い。ここで一緒に嶋寺の袖の舞、もう一度ご覧なされ」
義貞が放そうとしない恒良の身が案じられるが、今は尊良だけでも先に動かなければならない。商人に目配せをして、尊良は遊女の船に乗り移った。
船に乗り座り込むと、着飾った女が何人も尊良に纏わりついてきた。その内の一人が着物の前を大きく広げ、尊良に覆い被さるように抱き着いてきた。女の着物が陽に透けるので華やかな色合いの薄明かりに覆われる。暗闇ではないが、素肌が尊良の顔に押し付けられる。
「待て、今はそのような‥‥」
尊良の制止に、その女が耳元で囁いた。
「お静かに願います。こうして着物にくるまったまま、向こうには見えぬように別の船にお移しします。この船の底には一宮様の身代わりの者が隠れておりますゆえ、ご安心を」
遊女とは違う凛とした女の声を聞いて、尊良はこれが義貞を欺く芝居の一幕であることを理解した。それでこのまま女に身を任せることにしたが、尊良を覆う着物は次々と増えているようで、赤や黄の華やいだ薄明かりが徐々に暗さを増してきて、ついに真っ暗闇となった。何枚もの着物でくるまれているようだ。
尊良に囁いた女も共にくるまれているらしく、尊良にしがみついたまま離れようとしない。
義貞に見つかればこの場で斬られるのだという恐怖感は、不思議と感じなかった。暗闇だからなのか、女の身体のぬくもりが熱く感じる。鼓動も強く響いてくる。女も怖いのだろう。自分のために危険を冒させてしまったと不憫に思い、尊良はきつい体勢のまま両腕を動かして、何とか女を抱きしめた。女は驚いたのか身体を硬くしたが、やがて力を抜いて身を任せた。
着物にくるまれて抱き合ったまま二人とも、ごろりと転がされた。どんと、少し落ちた。痛みはない。僅かな揺れを感じながら、そのまま暫くじっとしていた。
時元の声がした。










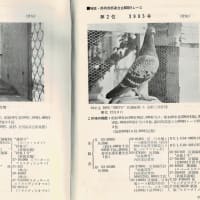

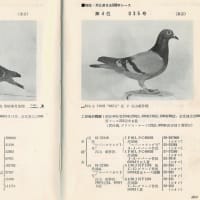







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます