現在の日本において家庭で利用される
衣料用洗剤にはリンが含まれていません。
無リン洗剤という言葉は広く知られています。
衣料用洗剤中に配合されていた
トリポリリン酸Naが
藻類やプランクトンの大発生と
関係していると疑われました。
1970年代に
藻類やプランクトンの大発生により
湖では悪臭が発生し、水道水が臭くなりました。
海では赤潮と呼ばれ大量の魚が死にました。
1980-1982年に
琵琶湖や霞ヶ浦で
トリポリリン酸Na入り洗剤が
条例により使用禁止となりました。
日本における衣料用洗剤は
無リン洗剤に置き換わりました。
しかしながらリンの
環境への流入は
衣料用洗剤から約18%です。
工場廃水、農畜産排出物、
し尿、降雨等が約82%です。
日本における衣料用洗剤は殆ど
無リン洗剤に置き換わりましたが、
湖や海の水質改善の効果は有りません。
衣料用洗剤の無リン化は
誤りだった可能性があります。
トリポリリン酸Naには
洗剤中で5種類の機能があります。
1.金属イオンを封鎖し、界面活性剤の沈殿を防ぎ、汚れを落ちやすくする。
2.汚れを洗剤液中に乳化、分散させる。
3.洗剤液をアルカリ性に保持し、汚れを落ちやすくする。
4.汚れが再び繊維に吸着しないようにする。
5.吸湿性の高い洗剤が固まることを防止する。
トリポリリン酸Naの代替として
P&G社、ヘンケル社が推奨したゼオライトを
日本の衣料用洗剤には配合されています。
ゼオライトはトリポリリン酸Naよりも
性能は劣り、ゼオライトに加え、
エチレンジアミン4酢酸Na(EDTA)、
高分子ポリマーが配合されています。
エチレンジアミン4酢酸Na(EDTA)、
高分子ポリマーは
生分解性が悪いです。
現在の日本の衣料用洗剤の課題です。
トリポリリン酸Naは
藻類やプランクトンに栄養素であり、
生分解性に優れています。
衣料用洗剤の無リン化は
誤りだった可能性があります。
日本の政府や関連機関は
良く考える必要があります。
もう1度トリポリリン酸Naを
衣料用洗剤への配合を
試してみる価値は有ると思います。
参考文献
1.みんなで考える洗剤の科学 井上勝也編 研成社(1987)
2.図説洗剤のすべて 三上美樹、藤原邦達、小林勇共著 合同出版(1983)
3.洗剤 from Wikipedia
衣料用洗剤にはリンが含まれていません。
無リン洗剤という言葉は広く知られています。
衣料用洗剤中に配合されていた
トリポリリン酸Naが
藻類やプランクトンの大発生と
関係していると疑われました。
1970年代に
藻類やプランクトンの大発生により
湖では悪臭が発生し、水道水が臭くなりました。
海では赤潮と呼ばれ大量の魚が死にました。
1980-1982年に
琵琶湖や霞ヶ浦で
トリポリリン酸Na入り洗剤が
条例により使用禁止となりました。
日本における衣料用洗剤は
無リン洗剤に置き換わりました。
しかしながらリンの
環境への流入は
衣料用洗剤から約18%です。
工場廃水、農畜産排出物、
し尿、降雨等が約82%です。
日本における衣料用洗剤は殆ど
無リン洗剤に置き換わりましたが、
湖や海の水質改善の効果は有りません。
衣料用洗剤の無リン化は
誤りだった可能性があります。
トリポリリン酸Naには
洗剤中で5種類の機能があります。
1.金属イオンを封鎖し、界面活性剤の沈殿を防ぎ、汚れを落ちやすくする。
2.汚れを洗剤液中に乳化、分散させる。
3.洗剤液をアルカリ性に保持し、汚れを落ちやすくする。
4.汚れが再び繊維に吸着しないようにする。
5.吸湿性の高い洗剤が固まることを防止する。
トリポリリン酸Naの代替として
P&G社、ヘンケル社が推奨したゼオライトを
日本の衣料用洗剤には配合されています。
ゼオライトはトリポリリン酸Naよりも
性能は劣り、ゼオライトに加え、
エチレンジアミン4酢酸Na(EDTA)、
高分子ポリマーが配合されています。
エチレンジアミン4酢酸Na(EDTA)、
高分子ポリマーは
生分解性が悪いです。
現在の日本の衣料用洗剤の課題です。
トリポリリン酸Naは
藻類やプランクトンに栄養素であり、
生分解性に優れています。
衣料用洗剤の無リン化は
誤りだった可能性があります。
日本の政府や関連機関は
良く考える必要があります。
もう1度トリポリリン酸Naを
衣料用洗剤への配合を
試してみる価値は有ると思います。
参考文献
1.みんなで考える洗剤の科学 井上勝也編 研成社(1987)
2.図説洗剤のすべて 三上美樹、藤原邦達、小林勇共著 合同出版(1983)
3.洗剤 from Wikipedia










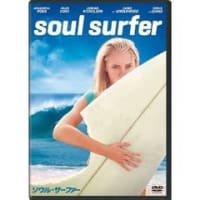









藻類に近い沈水植物です。
シャジクモ類が
日本の大部分の湖で消滅しています。
1960-1980年頃の
日本の高度成長時代において
様々な工業用化学品が生産され
シャジクモは減ったと思われます。
除草剤のみならず
大量に化学合成された化合物
公害等
様々な因子が絡み合い
シャジクモは減ったと思われます。
富栄養化により
トリポリリン酸Naを除いた
無リン化洗剤を疑っています。
必須栄養素であるリンを
洗剤を通じ供給し
シャジクモが増える可能性も
示唆されます。
あなたの活動は素晴らしいです。
シャジクモをあなたのWeblogにて
見出しました。
勉強になりました。
お互い頑張りましょう。
以下は
あなたのWeblog引用です。
水草は
浅いところから
抽水、浮葉、沈水と異なる
生息形態の植物が優占します。
シャジクモ類は沈水植物の中でも
ちょっと変わった植物です。
他の水草は維管束植物ですが
この仲間はむしろ藻類に近く
しっかりした根を持っていません。
1950年代以前の日本の深い湖では
植物帯の最も深いところは
シャジクモが優占していて
シャジクモ帯とよばれていました。
このシャジクモ類が
日本の大部分の湖で消滅しています。
ヨーロッパでも多くの湖沼で
他の沈水植物も含めて
衰退していたところが多かったです。
沈水植物
特にシャジクモ類を復活させることが
湖沼水質の回復につながるとされています
(水環境学会誌4月号)。
あまりに早くに
沈水植物が衰退してしまったためでしょうか?
抽水植物のヨシは
盛んに植栽されていますが
水質を回復させるために
シャジクモを増やそうという試みは
全く為されていません。
むしろ水質を悪化させる
浮葉植物のアサザを
増やそうという動きまであって
水環境の基本的な知識が
一般市民に伝わっていないと感じています。
何故シャジクモ類は減ってしまったのでしょうか?
従来は富栄養化
護岸
ソウギョの放流が原因とされていました。
除草剤の影響もあったのではないかと考え
学際的なチームを組んで
この課題に取り組んでいます。
Limnology 水から環境を考える
研究紹介2:シャジクモ類はなぜ減ったか?
http://d.hatena.ne.jp/Limnology/20070529