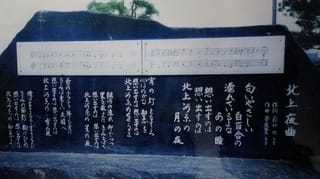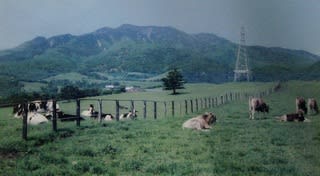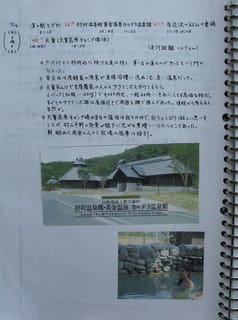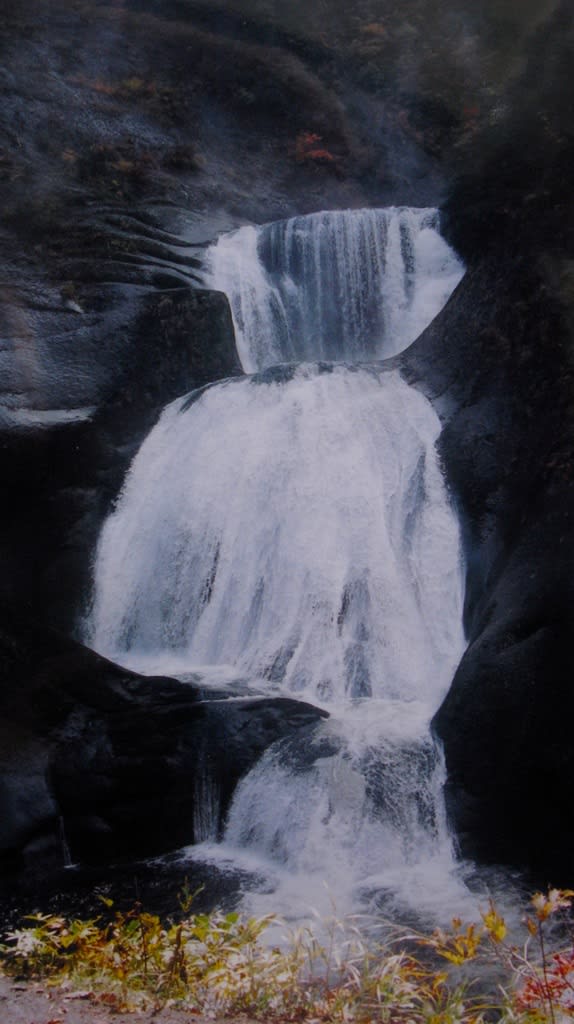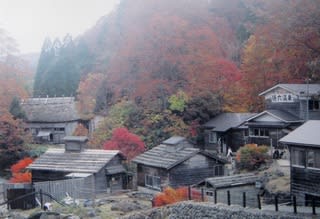生口島の耕三寺や平山郁夫美術館を訪れたとき、いつの日か「しまなみ街道」を、全て渡って見たいと思っていた。そんな時に目に飛び込んで来たのが、愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶ全行程80kmを舞台に開催される「瀬戸内しまなみ街道スリーデーマーチ」の案内でした。瀬戸内の島々を結ぶ12のコースの中から選んだのは、大島の「よしうみバラ公園」をスタートして来島海峡大橋を渡り今治城吹上公園をゴールとする20kmのコースです。(赤線の部分)健脚の人は尾道スタートは2日間で、今治スタートは3日間で80kmを歩かれます。すごいですね。
※瀬戸内しまなみ街道は今治から尾道までの有料道路の車道とは別に、歩行者やサイクリング専用道路が設けられています。


この記事は、当日配られた号外です。
3.000人もの参加者があったようです。


コースのポイント地点と残りの距離を記載したものをもらい、
出発地点の「よしうみバラ公園」までバスで移動します

大島の「よしうみバラ公園」をスタートます。
いよいよ20kmのウォーキングの幕開けです。

しばらくは海沿いの道を行きます。
吉海町椋名漁港を通過します。
まだ、余裕があります。


これから渡る来島海峡大橋が見えてきました。
この橋は第一・第二・第三と三つの橋で繋がっています。

橋の近くの休憩地点が近づいてきた。

スタートから6.1km地点の吉海町の道の駅「いきいき館」に到着。
ここで昼食です。

これから来島海峡大橋に入り、全長4.1kmの来島海峡大橋を渡ります。

来島海峡大橋からの眺めです。

来島海峡大橋の上では、強い向い風に悩まされたが
瀬戸内海の眺望が素晴らしかった。
かなりバテて来ています。


強い向い風に悩まされながら橋を渡りきった。
一般道路に下ります。

来島海峡大橋を下りたところで、
みかんやお茶などの接待があり
疲れた体にはありがたかった。
左側に海を見ながらトボトボと進みます。


今治の造船所の近くを通る。
ホテイアオイの花咲く池もあった。


今治の商店街を通り抜ける。
ゴールまで、あと一踏ん張りだ。


ついに20kmを歩ききった。作り笑顔でゴール地点に到着。
完歩証をもらう。くたびれた。
だが、これから駐車場まで歩かなければならない。


ゴール地点で提出したチェックカード。

翌日は伯方島の伯方SCパークから
生口島の瀬戸田市民会館までの20kmコース
参加を予定していましたが、初日に
予想以上に疲れたので断念しました。
しまなみ海道スリーデーマーチに参加した翌日に、
徳島県の祖谷かずら橋に向かいました。
大歩危と祖谷かずら橋。


祖谷かずら橋


祖谷かずら橋入口とかずら橋付近で
匂いに誘われて食べたイワナとアメゴ。


祖谷街道を進みます。
阿波池田町を経て「うだつの町並み」が残る
美馬市脇町に向かいます。


断崖絶壁に立つ小便小僧と祖谷渓の眺め。
目の眩むような深い谷底が見えます。


徳島県美馬市脇町のうだつの町並み






美馬市脇町から大鳴門橋で淡路島に渡り、
淡路島を縦断しました。
淡路島から明石淡路フェリー。
通称「たこフェリー」で明石へ渡り帰路につきます。

ここからは、
しまなみ海道スリーデーマーチに
参加する前日に立ち寄ったところです。
備中高松城址の説明と吉備津神社。
備中高松城跡では、豊臣秀吉が高松城
水攻めの際に築いた「蛙が鼻築堤跡」を見る。
一部が残っているだけだったが、
途轍もなく広い範囲の築堤に驚く。


備中国分寺跡と宝福寺。


雪舟
水墨画で有名な雪舟は
幼くして、この宝福寺に入り、
涙で絵を描いたという逸話を残す。 尾道の街角で。


尾道から向島へはフェリーで渡る。。


因島大橋記念館と因島大橋記念館から眺めた瀬戸内海。


この後生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋・来島海峡大橋を経由して
スタート地点の今治市へ入った。
3泊4日の日程で、走行距離は1,222.6kmでした。
※瀬戸内しまなみ街道は今治から尾道までの有料道路の車道とは別に、歩行者やサイクリング専用道路が設けられています。


この記事は、当日配られた号外です。
3.000人もの参加者があったようです。


コースのポイント地点と残りの距離を記載したものをもらい、
出発地点の「よしうみバラ公園」までバスで移動します

大島の「よしうみバラ公園」をスタートます。
いよいよ20kmのウォーキングの幕開けです。

しばらくは海沿いの道を行きます。
吉海町椋名漁港を通過します。
まだ、余裕があります。


これから渡る来島海峡大橋が見えてきました。
この橋は第一・第二・第三と三つの橋で繋がっています。

橋の近くの休憩地点が近づいてきた。

スタートから6.1km地点の吉海町の道の駅「いきいき館」に到着。
ここで昼食です。

これから来島海峡大橋に入り、全長4.1kmの来島海峡大橋を渡ります。

来島海峡大橋からの眺めです。

来島海峡大橋の上では、強い向い風に悩まされたが
瀬戸内海の眺望が素晴らしかった。
かなりバテて来ています。


強い向い風に悩まされながら橋を渡りきった。
一般道路に下ります。

来島海峡大橋を下りたところで、
みかんやお茶などの接待があり
疲れた体にはありがたかった。
左側に海を見ながらトボトボと進みます。


今治の造船所の近くを通る。
ホテイアオイの花咲く池もあった。


今治の商店街を通り抜ける。
ゴールまで、あと一踏ん張りだ。


ついに20kmを歩ききった。作り笑顔でゴール地点に到着。
完歩証をもらう。くたびれた。
だが、これから駐車場まで歩かなければならない。


ゴール地点で提出したチェックカード。

翌日は伯方島の伯方SCパークから
生口島の瀬戸田市民会館までの20kmコース
参加を予定していましたが、初日に
予想以上に疲れたので断念しました。
しまなみ海道スリーデーマーチに参加した翌日に、
徳島県の祖谷かずら橋に向かいました。
大歩危と祖谷かずら橋。


祖谷かずら橋


祖谷かずら橋入口とかずら橋付近で
匂いに誘われて食べたイワナとアメゴ。


祖谷街道を進みます。
阿波池田町を経て「うだつの町並み」が残る
美馬市脇町に向かいます。


断崖絶壁に立つ小便小僧と祖谷渓の眺め。
目の眩むような深い谷底が見えます。


徳島県美馬市脇町のうだつの町並み





美馬市脇町から大鳴門橋で淡路島に渡り、
淡路島を縦断しました。
淡路島から明石淡路フェリー。
通称「たこフェリー」で明石へ渡り帰路につきます。

ここからは、
しまなみ海道スリーデーマーチに
参加する前日に立ち寄ったところです。
備中高松城址の説明と吉備津神社。
備中高松城跡では、豊臣秀吉が高松城
水攻めの際に築いた「蛙が鼻築堤跡」を見る。
一部が残っているだけだったが、
途轍もなく広い範囲の築堤に驚く。


備中国分寺跡と宝福寺。


雪舟
水墨画で有名な雪舟は
幼くして、この宝福寺に入り、
涙で絵を描いたという逸話を残す。 尾道の街角で。


尾道から向島へはフェリーで渡る。。


因島大橋記念館と因島大橋記念館から眺めた瀬戸内海。


この後生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋・来島海峡大橋を経由して
スタート地点の今治市へ入った。
3泊4日の日程で、走行距離は1,222.6kmでした。