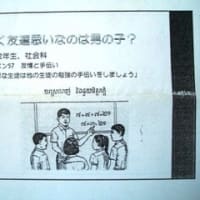こんにちは。甲斐田です。今、ベトナム国境の町、バベットにきています。明日は、国際子ども権利センターの活動地チャントリア郡の隣りのコンポンロー郡に行きます。ここはベトナムに出稼ぎに行く子どもがたくさんいるため、そこでも活動できないか検討するためです。今回はベトナムに出稼ぎに行った少女のことを報告してくださった幸田さんのスタディツアー報告をお届けします。
写真は今年1月に奨学金としての文房具を受け取った少女たちです。
奨学金受給の家庭訪問(チュレ)
「物乞いに行った少女」 幸田雅人
私はこのスタディーツアーがカンボジアの初めての訪問となりました。ベトナムへは何度か行ったことがありましたが、隣同士の国ながらどんな違いがあるのか興味のあるところでした。 3月20日にホーチミンからバスで1時間で国境に着き、ベトナムの出国手続きのあと、カンボジアの入国手続きをして、カンボジア入り。その日は国境の町に宿泊しました。
次の日の午前はプレイコキー中学校で、子ども達主体で行っている人身売買防止ネットワーク活動について話を聞きました。 そして、午後にはツアーメンバーは2つのグループに分かれ、奨学金を受けている家庭を訪問しました。
この奨学金制度とは、人身売買防止プロジェクトのひとつです。奨学金といっても現金を支給するのではなく、制服や米を支給し、学校へちゃんと通学できるようにして、貧しさから子どもが出稼ぎに出て人身売買に遭わないようにするものです。 支給するものは、制服(半袖、長袖ブラウス、スカート)、ノート、ボールペン、分度器、コンパスなどの文房具と、あとは米です。
私達が訪問した家庭の一軒目は、11歳の女の子の家庭で、奨学金を受けたのは1月からです。 この家は藁葺き屋根、土壁の家のようでしたが、最近の大雨で家が壊れてしまい、訪問したときにはその倒れた壁の残骸が残っていました。 今は木の枝と板で寝床と屋根をつくり、そこで寝泊りしています。 しかし見たところ本当に貧弱なつくりで強風が吹いたら倒れそうな、広さ畳2、3畳くらいの小屋です。中は狭いので昼は主に外で過ごして、夜はそこで眠るだけといった感じです。
子どもは学校へ行っている時以外は家の手伝いをします。 ご飯の支度、牛の糞集め、兄弟の面倒を見る、水牛の世話をする。 母親自身は小学校5年生までしか学校に行けず、子どもには是非ちゃんとした勉強をさせたいと言っていました。 仕事は稲作の他に水牛の糞を集めて売る仕事をしています。また、縫製工場で働くと収入になるので、自分達も行きたいと言っていました。
2軒目は10歳の女の子の家を訪問しました。 両親は6~7年前に離婚し、子どもは母親が引き取りました。しかし、5ヶ月前から母親はプノンペンの縫製工場へ出稼ぎに出ています。 現在は兄弟(男1、女2)とおばあちゃんと暮らしています。母親からの仕送りは1ヶ月前に1回あり、金額は10万リエル(約2500円)だそうです。仕送りはまだ1回しかありませんが、母親からは連絡が来るので、元気でいることは確認出来ているそうです。 家の中でおばあちゃんに奨学金で貰ったノートや文房具を見せてもらいました。
3軒目は、一番印象に残っている家で、14歳の女の子の家庭です。この少女は母親と一緒に、ベトナムへ物乞いの出稼ぎに出ていたそうです。 これには一同がちょっと驚きました。 土間の家の中に入れてもらい、甲斐田さんや私達が次々と質問をして、その物乞いの様子が分かっていきました。
動機はやはり米とお金の不足で、最初は物乞いの経験のある人についていったそうです。 1回の物乞いの期間は10日間くらい。初めて行ったのは13歳の時。それ以降7~9回ほど行きました。 稼ぎは10日間で6~7万リエル(約1500円~1800円)。
貧困農家ですので、当然パスポートなんて持っていません。 国境警察に賄賂を払い国境を越えます。 物乞いで滞在した街の名前は覚えておらず、人が多くバイクがたくさん走っている街だそうです。 物乞いをしているときにベトナム人に怒鳴られたり、まったく稼げない日もあったり、夜は林の中や店舗前の路上で眠り、現地の住民が自分達のことを警察に通報することを恐れて、目立たないように注意します。
奨学金をもらってから母親は、ベトナムへ行かせる必要はなくなったと言っています。 しかし、同時に今でも食べるのには十分ではないとも言っていました。父親は建設現場で働いており、1万~2万リエルを仕送りで送ってきます。 しかし、父親には愛人がいて、それが家庭内暴力の原因となっているそうです。 今の母親の仕事は肥料用に牛の糞を集めてベトナムへ売りに行くことです。
4軒目は13歳の女の子の家で、兄弟は姉と妹がいます。 父親は大工、母親はゴザを編んで売って収入を得ています。ゴザの売値は大きいサイズ(長さ1.5m)で2万リエル、小さいサイズで1.5万リエル。1枚編むのに約5日程度かかります。 家の中から作っている途中のゴザを出して見せてもらい、ついでにみんなで写真も撮りました。
今回の訪問で、一番印象に残ったのは、やはり3軒目の物乞いの話でした。そもそも物乞いが出稼ぎ仕事として成り立つとは知りませんでした。 この物乞いに行った少女は14歳の女の子ですが、ごく普通のまじめでおとなしい感じの少女です。
少女の話では、物乞いの出稼ぎへの勧誘に斡旋業者が村によく来ていたそうです。 そこで物乞いの出稼ぎの方法を覚えた村人は、後に自分達だけで行くようになったそうです。 この少女も、斡旋料金が1回につき2.5万リエル(約650円)と金額を知っていましたから、最初はこの斡旋業者について行ったのだろうと思います。
それと、物乞いの稼ぎについてですが、貧しい農民にとってはそれなりの現金になると感じました。例えば、4軒目の家はゴザを1枚編むのに5日程度かかり、売値は2万リエル(約520円)。そして物乞いは10日間で6、7万リエル稼いでいました。
交通費や賄賂にかかる費用もありますから、単純に比較は出来ませんが、7~9回も出かけていることからも、物乞いによって得られる収入は、村でちょっとした仕事で得られる現金に比べて遜色ない金額だろうと推測できます。
また、今回は幸いにも人身売買業者の偽の就職斡旋ではありませんでしたが、現金収入になると誘えば、遠方や国外へ子どもを連れて行くことは、いとも簡単であると感じました。 物乞いに行った少女の両親は奨学金を貰ってからは、出稼ぎには行かせないよう
にしたと言っていました。また、兄弟にも行かせないようにすると言っていました。一人の子どもに支給する制服や文房具、米などにかかる経費は、それほど高額ではありません。貧しさから学校へ行けなかったり出稼ぎに出たりして、人身売買の危険に遭う可能性をなくす方法としてすぐに効果がある方法です。 それに2軒目では、支給された文房具を大切にしていましたし、4軒目ではノートが一番うれしいと言っていました。こんな簡単なもので喜んでもらえて、チュレの人たちの素朴さを感じました。
農村を訪れたときは乾季で暑くて、藁葺き屋根と土壁の民家が点在していて、はだしで遊ぶ子ども達が訪れた日本人に興味津々で集まって来たりと、のどかな光景でした。 しかし、インタビューすると両親が離婚していたり、父親に愛人がいたり、ベトナムで屋外に寝泊りしながら物乞いしたりと、いろいろな苦労があるのが分かりました。 各家庭で食べる分の米が十分収穫できないことが分かりました。
この奨学金制度は、本当に貧しく学校へ行けない、また出稼ぎで行けない子ども達に、学校へ行ける機会を与えるすばらしい制度だと感じます。
子ども一人あたりの費用は、私達日本人から見れば僅かなお金ですが、本人にとっては毎日学校へ行って、ちゃんと勉強できたという経験はかけがえのないものになるでしょう。 そして大人になったときに良い仕事につけたり、親となったときに勉強の大切さを実感しているがゆえ、自分の子どもにできるだけ学校へ行かせるように工夫してくれると思います。
そして、一番望むことは、村で十分な収穫が得られ、商売がうまくいき、村が豊かになり、子ども全員が学校へ行けて、この奨学金制度が必要なくなる日が来ることだと思います。 HCCとシーライツの行っている牛銀行や貯蓄グループプロジェクトがこういった将来につなげてくれると思っています。
【編集より】
少女たちの危険な出稼ぎを防止するために会員になって支えてください。
http://www.c-rights.org/join/kaiin.html
写真は今年1月に奨学金としての文房具を受け取った少女たちです。
奨学金受給の家庭訪問(チュレ)
「物乞いに行った少女」 幸田雅人
私はこのスタディーツアーがカンボジアの初めての訪問となりました。ベトナムへは何度か行ったことがありましたが、隣同士の国ながらどんな違いがあるのか興味のあるところでした。 3月20日にホーチミンからバスで1時間で国境に着き、ベトナムの出国手続きのあと、カンボジアの入国手続きをして、カンボジア入り。その日は国境の町に宿泊しました。
次の日の午前はプレイコキー中学校で、子ども達主体で行っている人身売買防止ネットワーク活動について話を聞きました。 そして、午後にはツアーメンバーは2つのグループに分かれ、奨学金を受けている家庭を訪問しました。
この奨学金制度とは、人身売買防止プロジェクトのひとつです。奨学金といっても現金を支給するのではなく、制服や米を支給し、学校へちゃんと通学できるようにして、貧しさから子どもが出稼ぎに出て人身売買に遭わないようにするものです。 支給するものは、制服(半袖、長袖ブラウス、スカート)、ノート、ボールペン、分度器、コンパスなどの文房具と、あとは米です。
私達が訪問した家庭の一軒目は、11歳の女の子の家庭で、奨学金を受けたのは1月からです。 この家は藁葺き屋根、土壁の家のようでしたが、最近の大雨で家が壊れてしまい、訪問したときにはその倒れた壁の残骸が残っていました。 今は木の枝と板で寝床と屋根をつくり、そこで寝泊りしています。 しかし見たところ本当に貧弱なつくりで強風が吹いたら倒れそうな、広さ畳2、3畳くらいの小屋です。中は狭いので昼は主に外で過ごして、夜はそこで眠るだけといった感じです。
子どもは学校へ行っている時以外は家の手伝いをします。 ご飯の支度、牛の糞集め、兄弟の面倒を見る、水牛の世話をする。 母親自身は小学校5年生までしか学校に行けず、子どもには是非ちゃんとした勉強をさせたいと言っていました。 仕事は稲作の他に水牛の糞を集めて売る仕事をしています。また、縫製工場で働くと収入になるので、自分達も行きたいと言っていました。
2軒目は10歳の女の子の家を訪問しました。 両親は6~7年前に離婚し、子どもは母親が引き取りました。しかし、5ヶ月前から母親はプノンペンの縫製工場へ出稼ぎに出ています。 現在は兄弟(男1、女2)とおばあちゃんと暮らしています。母親からの仕送りは1ヶ月前に1回あり、金額は10万リエル(約2500円)だそうです。仕送りはまだ1回しかありませんが、母親からは連絡が来るので、元気でいることは確認出来ているそうです。 家の中でおばあちゃんに奨学金で貰ったノートや文房具を見せてもらいました。
3軒目は、一番印象に残っている家で、14歳の女の子の家庭です。この少女は母親と一緒に、ベトナムへ物乞いの出稼ぎに出ていたそうです。 これには一同がちょっと驚きました。 土間の家の中に入れてもらい、甲斐田さんや私達が次々と質問をして、その物乞いの様子が分かっていきました。
動機はやはり米とお金の不足で、最初は物乞いの経験のある人についていったそうです。 1回の物乞いの期間は10日間くらい。初めて行ったのは13歳の時。それ以降7~9回ほど行きました。 稼ぎは10日間で6~7万リエル(約1500円~1800円)。
貧困農家ですので、当然パスポートなんて持っていません。 国境警察に賄賂を払い国境を越えます。 物乞いで滞在した街の名前は覚えておらず、人が多くバイクがたくさん走っている街だそうです。 物乞いをしているときにベトナム人に怒鳴られたり、まったく稼げない日もあったり、夜は林の中や店舗前の路上で眠り、現地の住民が自分達のことを警察に通報することを恐れて、目立たないように注意します。
奨学金をもらってから母親は、ベトナムへ行かせる必要はなくなったと言っています。 しかし、同時に今でも食べるのには十分ではないとも言っていました。父親は建設現場で働いており、1万~2万リエルを仕送りで送ってきます。 しかし、父親には愛人がいて、それが家庭内暴力の原因となっているそうです。 今の母親の仕事は肥料用に牛の糞を集めてベトナムへ売りに行くことです。
4軒目は13歳の女の子の家で、兄弟は姉と妹がいます。 父親は大工、母親はゴザを編んで売って収入を得ています。ゴザの売値は大きいサイズ(長さ1.5m)で2万リエル、小さいサイズで1.5万リエル。1枚編むのに約5日程度かかります。 家の中から作っている途中のゴザを出して見せてもらい、ついでにみんなで写真も撮りました。
今回の訪問で、一番印象に残ったのは、やはり3軒目の物乞いの話でした。そもそも物乞いが出稼ぎ仕事として成り立つとは知りませんでした。 この物乞いに行った少女は14歳の女の子ですが、ごく普通のまじめでおとなしい感じの少女です。
少女の話では、物乞いの出稼ぎへの勧誘に斡旋業者が村によく来ていたそうです。 そこで物乞いの出稼ぎの方法を覚えた村人は、後に自分達だけで行くようになったそうです。 この少女も、斡旋料金が1回につき2.5万リエル(約650円)と金額を知っていましたから、最初はこの斡旋業者について行ったのだろうと思います。
それと、物乞いの稼ぎについてですが、貧しい農民にとってはそれなりの現金になると感じました。例えば、4軒目の家はゴザを1枚編むのに5日程度かかり、売値は2万リエル(約520円)。そして物乞いは10日間で6、7万リエル稼いでいました。
交通費や賄賂にかかる費用もありますから、単純に比較は出来ませんが、7~9回も出かけていることからも、物乞いによって得られる収入は、村でちょっとした仕事で得られる現金に比べて遜色ない金額だろうと推測できます。
また、今回は幸いにも人身売買業者の偽の就職斡旋ではありませんでしたが、現金収入になると誘えば、遠方や国外へ子どもを連れて行くことは、いとも簡単であると感じました。 物乞いに行った少女の両親は奨学金を貰ってからは、出稼ぎには行かせないよう
にしたと言っていました。また、兄弟にも行かせないようにすると言っていました。一人の子どもに支給する制服や文房具、米などにかかる経費は、それほど高額ではありません。貧しさから学校へ行けなかったり出稼ぎに出たりして、人身売買の危険に遭う可能性をなくす方法としてすぐに効果がある方法です。 それに2軒目では、支給された文房具を大切にしていましたし、4軒目ではノートが一番うれしいと言っていました。こんな簡単なもので喜んでもらえて、チュレの人たちの素朴さを感じました。
農村を訪れたときは乾季で暑くて、藁葺き屋根と土壁の民家が点在していて、はだしで遊ぶ子ども達が訪れた日本人に興味津々で集まって来たりと、のどかな光景でした。 しかし、インタビューすると両親が離婚していたり、父親に愛人がいたり、ベトナムで屋外に寝泊りしながら物乞いしたりと、いろいろな苦労があるのが分かりました。 各家庭で食べる分の米が十分収穫できないことが分かりました。
この奨学金制度は、本当に貧しく学校へ行けない、また出稼ぎで行けない子ども達に、学校へ行ける機会を与えるすばらしい制度だと感じます。
子ども一人あたりの費用は、私達日本人から見れば僅かなお金ですが、本人にとっては毎日学校へ行って、ちゃんと勉強できたという経験はかけがえのないものになるでしょう。 そして大人になったときに良い仕事につけたり、親となったときに勉強の大切さを実感しているがゆえ、自分の子どもにできるだけ学校へ行かせるように工夫してくれると思います。
そして、一番望むことは、村で十分な収穫が得られ、商売がうまくいき、村が豊かになり、子ども全員が学校へ行けて、この奨学金制度が必要なくなる日が来ることだと思います。 HCCとシーライツの行っている牛銀行や貯蓄グループプロジェクトがこういった将来につなげてくれると思っています。
【編集より】
少女たちの危険な出稼ぎを防止するために会員になって支えてください。
http://www.c-rights.org/join/kaiin.html