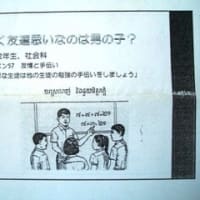みなさんこんにちは、平野です。
前回(昨日付けブログ)でお伝えしました通り、国際子ども権利センター支援によるHCCのプロジェクト地、プレイベン州コムチャイミア郡での収入向上プログラム(家畜銀行)の進捗報告を通じて、“最”貧困層への支援についてみなさんと考えたいと思います。今回は第2回目として、そもそもなぜ村人が豚よりも牛を欲しがるのかについてお話します。
【牛は相棒】
カンボジアの牛は、乳牛でも肉牛でもなく、農耕牛です。日本ではトラクターがやる「田起こし」の重要な任務を担うのが牛なのです。以下、牛を持つことの利点を列記します。
①田起こしができる
・自作農の場合・・・お金を払って牛を借りる必要がなくなる
・小作農(労務提供を生活の糧にしている人)の場合・・・自作農になれる
②牛糞が得られる(貴重な燃料になり、堆肥の材料にもなる)
③いざというときの保険になる(売ればまとまった現金になる)
その上で、牛は④特に餌を用意してやる必要がなく(そのへんの草を食む)、⑤豚や鶏のようにたやすく死なない、という利点を備えているわけです。また、水牛もよくみかけますが、牛のほうが好まれるようです。よりおとなしく、より暑さに強く、より働くからです。
【投資よりも節約と確実性】
鳥インフルエンザの例を出すまでもなく、鶏は簡単にバタバタと死ぬことがあります。また、くず米だの籾殻だのを与えなくてはいけません。また豚も、やはり流行り病などで死ぬ危険があります。死なせずに売れたとしても、それまでの餌代は馬鹿になりません。
一方、現金収入という観点からは、豚や鶏の方が、うまく育てることが出来れば食肉として売ることができ、収入につながります。基本的に牛自体は現金収入を産み出しません(上記のような節約にはつながります)。それでも、仔牛を選んだ家族は、それが水田で活躍するまでに2年間かかることを承知で、豚よりも牛を選びました。“最”貧困の家庭にとっては、豚という投資が必要でリスクを伴う家畜よりも、しばらく待つという条件付きでも、牛が持つ特性が魅力的ということなのでしょう。
【やはり稲作が大事】
カンボジア語では、日本語同様、食事をすることを「ごはんを食べる」と言います。日本では、そう言いつつピザを食べたりしますが、カンボジアの農村部においては文字通り「ごはん」です。牛に固執する彼らを見て、やはり稲作こそが第一であって、牛は欠かざるべき存在なのだ、ということも感じました。カンボジアの農民は“ネアック(人)・スラエ(水田)”=水田の人なのです。
(この項続く)
※写真は動物シリーズ第2弾で、水牛のアップです。かわいいですよ。
前回(昨日付けブログ)でお伝えしました通り、国際子ども権利センター支援によるHCCのプロジェクト地、プレイベン州コムチャイミア郡での収入向上プログラム(家畜銀行)の進捗報告を通じて、“最”貧困層への支援についてみなさんと考えたいと思います。今回は第2回目として、そもそもなぜ村人が豚よりも牛を欲しがるのかについてお話します。
【牛は相棒】
カンボジアの牛は、乳牛でも肉牛でもなく、農耕牛です。日本ではトラクターがやる「田起こし」の重要な任務を担うのが牛なのです。以下、牛を持つことの利点を列記します。
①田起こしができる
・自作農の場合・・・お金を払って牛を借りる必要がなくなる
・小作農(労務提供を生活の糧にしている人)の場合・・・自作農になれる
②牛糞が得られる(貴重な燃料になり、堆肥の材料にもなる)
③いざというときの保険になる(売ればまとまった現金になる)
その上で、牛は④特に餌を用意してやる必要がなく(そのへんの草を食む)、⑤豚や鶏のようにたやすく死なない、という利点を備えているわけです。また、水牛もよくみかけますが、牛のほうが好まれるようです。よりおとなしく、より暑さに強く、より働くからです。
【投資よりも節約と確実性】
鳥インフルエンザの例を出すまでもなく、鶏は簡単にバタバタと死ぬことがあります。また、くず米だの籾殻だのを与えなくてはいけません。また豚も、やはり流行り病などで死ぬ危険があります。死なせずに売れたとしても、それまでの餌代は馬鹿になりません。
一方、現金収入という観点からは、豚や鶏の方が、うまく育てることが出来れば食肉として売ることができ、収入につながります。基本的に牛自体は現金収入を産み出しません(上記のような節約にはつながります)。それでも、仔牛を選んだ家族は、それが水田で活躍するまでに2年間かかることを承知で、豚よりも牛を選びました。“最”貧困の家庭にとっては、豚という投資が必要でリスクを伴う家畜よりも、しばらく待つという条件付きでも、牛が持つ特性が魅力的ということなのでしょう。
【やはり稲作が大事】
カンボジア語では、日本語同様、食事をすることを「ごはんを食べる」と言います。日本では、そう言いつつピザを食べたりしますが、カンボジアの農村部においては文字通り「ごはん」です。牛に固執する彼らを見て、やはり稲作こそが第一であって、牛は欠かざるべき存在なのだ、ということも感じました。カンボジアの農民は“ネアック(人)・スラエ(水田)”=水田の人なのです。
(この項続く)
※写真は動物シリーズ第2弾で、水牛のアップです。かわいいですよ。