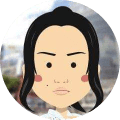冬期は紙の最盛期、いつも忙しくしているのですが、今年は更に忙しい。
でもそれはご注文をいただき、集中して紙を作ることが出来ているということでとても楽しくて嬉しいことなのです。
まず1月の末に岐阜のPRで東京でセミナーとワークショップをさせていただいたのは前回書きましたが、さらに次週紙を納品しに東京へ行ってきたのでした。
いえ、いつもそんなわざわざ直接納品しに行ったりしないのですよ。いつもは宅急便でお送りしています。
今回は紙が厚かったのと枚数があったので宅急便ではかなーーーり不安で、それなら直接行くか!と。
また、前の週忙しくて実家によるもゆっくり話せなかったので、この週でゆっくりしようかなと。
紙は楮に三椏をブレンドした厚めの紙。
厚めなので原料は結構使います。いつもの2倍は準備。2倍のちり取りはかなり大変です。
また三椏は細かいからちり取りに時間がかかります。
楮はアクの強い産地の楮を使用するので、紙を白くする為流水に晒してアクだしも丁寧に。

左側がアク抜き前で、右側はアク抜き後。
でも抜きすぎるとパサついてしまうので程々に。


アクを抜くと白くなりちり取りもしやすいです。綺麗な色になりました。

何日も何日もちり取り、永遠に終わらないんじゃないかと目の前が真っ暗になりお尻が平たくなってきた頃、ようやく終わりを迎えます。

何日も何日もちり取り、永遠に終わらないんじゃないかと目の前が真っ暗になりお尻が平たくなってきた頃、ようやく終わりを迎えます。
ちり取りして綺麗にさっぱりした原料は叩解へ。叩解とはその字の通り叩いて解すこと。

(この手は私の手✋ではなくレジェンドの手。)
なのですが、いまはほとんどビーターと呼ばれる解す機械を使っています。
手漉きのビーターには二種類あり、ホーレンダービーターは歯が横に付いていて、繊維をすり潰しながら解します。


なぎなたビーターはなぎなたの刃みたいなのがついています。日本刀みたいでなんだか凄く切れそうですよね。これを回転させるのですが、刃として研いでいないので切るのではなく、あくまで解しています。

これを掃除するときによく怪我をしてしまいます。やっぱり切れるんじゃん!と思ったでしょうか?違います!切れるのではなく、先端で突き刺してしまうのです、腕を(ノД`)
手漉きのビーターには二種類あり、ホーレンダービーターは歯が横に付いていて、繊維をすり潰しながら解します。


なぎなたビーターはなぎなたの刃みたいなのがついています。日本刀みたいでなんだか凄く切れそうですよね。これを回転させるのですが、刃として研いでいないので切るのではなく、あくまで解しています。

これを掃除するときによく怪我をしてしまいます。やっぱり切れるんじゃん!と思ったでしょうか?違います!切れるのではなく、先端で突き刺してしまうのです、腕を(ノД`)
スパッと切れたら治りは早いのですが、突き刺すと結構長引くし、痛い。。
そんな危険ゾーンを通ってやっと紙漉きです。

三椏や雁皮は水の抜けが悪いのと繊細なので
優しく漉きます。さらに厚くなりにくいから時間がかかります。

しかしこれだけてゅるんてゅるんの紙床が見れるので頑張りがいがあるってもんです。
(いつになく美味しそう)


今回は鉄板乾燥。
真冬に鉄板乾燥は湯気の量がとても多く独特の雰囲気。

こうして出来上がった紙をお届けしました。

こうして出来上がった紙をお届けしました。
その地は柴又。
そう、あの、柴又!寅さんの柴又です。
寅さんは母が好きでいつも一緒にテレビで見ていました。
ほんとお騒がせな寅さんと、ほっとけない周りの方々。これぞ下町という感じが良くてね。
今回納品させていただいたのは想彩工房さん。木に刺繍をする刺繍屋さんと組んで新しい商品を作られて、それに紙を使っていただけるとのこと。
それもご朱印帳に。
う、嬉しい。
書道用紙とかは漉いてないんですが、ご朱印帳用は特別。元々自分がご朱印をいただいていたのを、自分で紙漉けば良いんじゃ?となり作るようになりました。
奈良や滋賀などへ行き寺社仏閣へ参拝して書いて貰い、書き心地をしつこく聞いてみたり。
なので思い入れが違うのです。
沢山売れてくれると良いなあ。
(あ、ご朱印帳を入れる袋も作ってます!!!
マルシェルさんで販売中♪)


あ、帝釈天のこと書き切れない!次へ続く