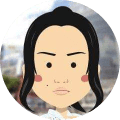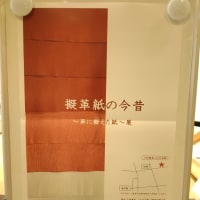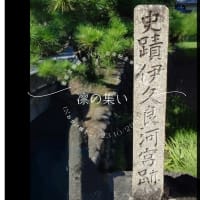私は昔から猫舌で熱いモノを触るのも苦手。
お食事でよく熱いうちにどうぞって言っていただくのですが、とんでもない、冷ましてからでないと食べられないのです。
時間がないときに急いで食べようものなら、その熱々が口中を暴れ回り喉を通り胃に入るまでは熱々の実況中継かのようです。更に数時間後にはヤケドした上顎の皮がめくれます。
更に更に、熱いお茶碗や湯飲みを持つのも苦手。何故こんなに熱が伝わるモノに入れているのだと腹立たしくなります。
洋食はお皿を持ち上げないので良いんです。持ち上げるモノには持ち手が付いているし。和食は器を手に取っていただくので、磁器や陶器に入った熱々にいつも悩まされていたのです。(熱いの触るとかなんの罰ゲームや💢)
そんな時に、漆芸家の三田村先生から、お茶碗の話を聞きました。
何故飯椀をお茶碗と言うのか?何故お茶碗は今の形なのか?
庶民の暮らし方、ものづくりの進化、インフラ、輸送コストなど様々な要因が重なり、少しずつ今の形になっていったのではないか?
本来は漆器であったのではないか?と。
ご飯を漆器でいただくと、手が熱くない、口当たりも柔らかい、保温性もあると良いことづくし。
その話を聞いたとき、目から鱗が落ちたと同時に、自分にガッカリしました。何故不具合があったにもかかわらず、目をつむり常識を疑わずにいたのか。とても自分らしくないことでした。
何故?どうして?と疑問を持ち考えることを怠ってはいけないですね。
専門家のように深い知識まではいかなくても、それを知ることは、とても楽しく、自分を作っていくものだから、色んなコトに目を向けていきたい。
漆器にご飯をよそい並べてみると、何だか背筋が伸びます。漆器というだけで、食事の場が特別な場になったよう。ちゃんと食事に向き合っていただかなくてはという、
とても有り難い気持ちになりました。
食材を作ってくれた人、料理をしてくれた人、器を作ってくれた人、箸を作ってくれた人、ガス、水道、電気、家まで。
食事一つ、色んな方々が関わっているからいただける。
ちゃんと感謝して「いただきます」
忘れていたことを思い出させてくれた飯まりの日でした。