 「癒される」
「癒される」 「しあわせな気持ちになれる」と
「しあわせな気持ちになれる」と世界各国で人気のラウル・デュフィ。
1900-1950年代に活躍した、フランスの画家だ。

「クロード・ドビュッシーへのオマージュ」1952年。
彼の画業が集大成した時期の作品。
最晩年には、関節の持病のため色彩がシンプルになるなど、
もしかしたら本人には不本意な、作風の変化が見られたが、
パリ万博が開かれた1930年代をピークとして、広く世界に評価され、
勲章を受けたりもして、
非常に順風満帆なアーティスト人生のように、私の目には映る。
1900年ごろ
パリ国立美術学校の生徒だったデュフィは、最初こそ、
やや明度の低い、北ヨーロッパっぽい風景画を、典型的な印象派の技法で
描いていたが、

1903年に地中海を訪れてから一気に、デュフィらしい明るい色彩が
キャンバスに花開く。
左上から時計回りに、シニャック、ゴーギャン、ブラック、セザンヌ。

そしてなんといってもマティス。
これら実力派の画家たちの作風に、次々と影響を受け、
“すくすくと育った” そんな印象を、展示の序盤では受けた。
デュフィが大成したもう一つの要因と私が考えるのは、
その「デザイン力」だ。
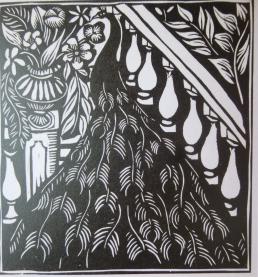
1920年ごろから、版画や、テキスタイルのデザインに携わるようになるのだが、
とにかく、センスがいい。というか、
「人気の出る構図」がわかっている人、という印象。
(この点ではアルフォンス・ミュシャと共通しているかも)
引きあいに出して申し訳ないけれど、同じパリの画家でも、
この間観たヴァロットンには、上の木版のようなデザイン性は、ない。
(でも、ヴァロットンの木版には別の魅力があることは確かだ)
デュフィの人柄はわからないけれど、
当時のアートシーンにおいて、何が人を惹きつけるか、
直截的に言えば何が売れるか、が、自然とわかっていた人だったのではないだろうか。
なにしろ、歴史的には二度の世界大戦を、直接間接の別はともあれ
経験しているはずなのに、“その影”が少なくとも今回の展示では
見当たらなかった。
デュフィが自身のスタイルを確立し、
イマ風にいえばスターダムを駆け上らんとした1920-30年代。
かたやドイツでは。

左がゲオルゲ・グロッス「扇動者」(1928年)。
風刺の対象はもちろん、ナチスだ。
グロッスは33年、ヒトラーから逃れて米国へ渡る。
(タッチの差で、殺されずにすんだらしい)
右は、カンディンスキー「下部構造」(1933年)。
ダイレクトに体制を批判した絵ではないが、
1910-20年代に象徴的だった、構図の深みがない。
キャンバスの浅いところですべて、構成されており、色彩も暗い。
ご存知の人もいるかも知れないが、1932年にはデッサウのバウハウスが閉鎖に
追い込まれ、
カンディンスキーも翌年、ドイツを去る。
そんな中、デュフィは
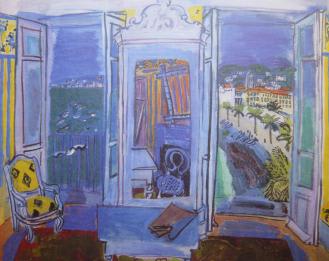
「ニースの窓辺」(1928年)
青く穏やかな海と空……。
「青」は色調が変わっても、その個性をあらわす唯一の色、と
デュフィは言ったそう。
グロッスはダダイズムだし、カンディンスキーは構成主義、
それぞれ哲学や立ち位置が違うとはいえ、
どうしてこんなに違うのか。
きっと、1930年代の世界を天気図で例えると、
パリのあたりだけ晴れていたんだろうなぁ、なんて、
およそアカデミックでない推論をめぐらす。
今の日本だって、いろんなことがあるけれど、世界を天気図で例えれば
まだまだ、晴れている方なのだろう。
今回の展示で、私がイチバン「これ、好き!」と気に入った絵は

「ヘンリーのレガッタ」(1933年ごろ)
小さ目の作品だし、何がどういいのか、上手く説明できないけれど、
デザイン性も色彩も、筆の勢いも、とても好きだ。
何も考えず、第一印象で選んだのだが、
1933年ごろの作品、というのが……。
近代絵画に関して、今まで、大戦とその影響という視点で観てきた自分には
これ以上の皮肉はない、と、
思わず苦笑いしてしまった。
※ラウル・デュフィ展の会期は終了しています。


 早々に恐縮です、ありがとうございます。
早々に恐縮です、ありがとうございます。















