
「あだたらの宿 扇や」をチェックアウトした小生、向かったのは二本松城だ。前日、成駒で知ったが、二本松藩は10万石余。



福島県で見れば、郡山と福島の中間にあり、かつ会津にも近い。奥州街道の要所ということで、古くからいろいろな大名が、この地を巡って争ってきた。
伊達正宗の時代は会津の芦名氏と伊達氏の間に挟まれ、いろいろな駆け引きがあったことが大河ドラマなどでも描かれていた。
そんな二本松の中心が二本松城なんだが、歴史的には同じ場所でずっと城があり、少しずつ拡張されたりしながら幕末まで存在したという点で、レアな存在。
そして到着したところ、その巨大な佇まいに圧倒された。「なんだ、この大きなお城は!」って。その雰囲気が伝わるか・・・というのがトップ写真。

ちなみに、入り口の処にある像は、戊辰戦争で頑張った少年隊。会津若松の白虎隊が有名だが、地元では彼らの戦いぶりも有名だそうだ。
さらにいうと、大坂の陣以来、城を枕に討ち死にしたのは二本松だけという。それだけ幕府への忠誠も厚かったことになる。
さて、城郭について話を進めよう。巨大な入り口の両側には急勾配で高い石垣がそびえている。箕輪門と呼ばれる正門は復元されたものだが、ここから歩みを進めると広い処に出る。ここが三の丸で、かつて御殿のあった処。ここが二段ある。
ここまで来ると、二の丸以降の施設が小高い丘の上にあることがわかる。


せっかくなので、しこしこ進む。かなり登ったところで井戸があった。この井戸、日本三井に数えられているという。そして今でも水が湧いているのだ。
さらに勾配がきつくなってきたところで、かつての工法を活かして復元された本丸の石垣が見えてきた。


左写真の二つの石垣のうち右側が穴太(あのう)積みと呼ばれる石垣。歴史好きな方ならご案内だろうが、安土城などでも活躍した穴太衆を、蒲生氏郷が会津城主だったときに呼び寄せ、会津の支城のこちらでも石垣作成に取り組ませたという。
そして左側が、野面積みだ。彦根城や秀吉の大坂城などと同じ時期の工法だ。


さらに本丸の最上部は江戸城などと同じ工法で作られている。この三種の工法を一度に見られるのがこのお城の魅力だという。
本丸最上部には戊辰戦争のときに城代が自刃した処に石碑がある。そしてそこから安達太良山がキレイに見える(右写真)。
本丸からの眺めは素晴らしく、なるほどここをお城のてっぺんにしたくなるわけだ・・・と。成駒のご主人が二本松藩を誇りに思うのも、このお城の風格と戊辰戦争の潔さを見ればむべなるかなと・・・
歴史に興味あるなしに関わらず、一度はこちらにお越しになることをオススメしたい。

























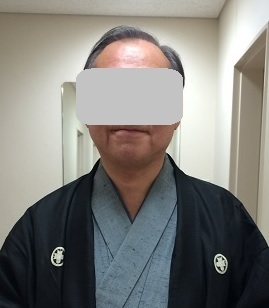

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます