会社とか仕事では、人が動くこと、組織で動くこともあり、どうしても“上下関係”が生じる。
しかし、その“下”の人(部下、後輩などなど)も、一社員であり、一社会人であり、その存在、働きは尊重されないといけないし評価されないといけない。
問題はその“上”の人。
以前も書いたことがあるけど、その“上”の人(上司、先輩など)がカン違いしてると、ただ威張ったり自分がラクをしたいがために下の人を使うことになる。
その上司はそれで優越感や自己満足を得ているのかもしれないが、部下の心境はどうだろう、「そんな言い方はないだろ」、「そんなん、自分でやれよ、その方が早いだろう」と思うこともあるかもしれない。
上司、部下それぞれが同じ行動、同じミスをしても、上司と部下に対する扱いが違うとか、上司からお願いすることがあってもそういう時でも上司の方が態度がやたらデカイとか、部下が「おまえは何様だ」と思うような上司もいるかもしれない。
上司はエライもんかもしれない、でも人への敬意や気持ちは周りから言われて出るもんでもなく肩書きで持てるもんでもない。どういう上司像で部下に接するかで部下の敬意も変わってくるだろう。
部下をわざわざ呼びつけてしょーもない用を頼んだり、上司から頼む仕事なのにわざわざ部下を来させて書類などを受け取りに来させたり、そういうのも実は部下は自分の仕事の手を止めて上司に振り回されてやってることもあり、それが会社のコストになる。
状況によってそれもアリだろう、でもその当の上司は動かずラクだけしてるという状況だと、部下も進んでやろうと思えない。上司も事業主も忙しくて、それで便宜上部下をそのように使うなら、俺が部下なら「使ってください、俺、行きます」とも思える。でも自分がラクしたいがために呼びつけて仕事を押し付ける上司ならそういう上司に魅力を感じないだろう。
そういう部下の心境、状況をわかってない上司や事業主自身、会社や事業所にとってマイナスになってる。
そのために、雑用のために部下とか事務員の人を雇ってるものかもしれない、それもアリだろう。でも自分の給料をなんとか自分であげたいとか、もっと深い仕事をやりたいと思ってる人がずっとそういう扱いなら、会社にとってマイナスだ。それで何年もきてると、職場でも「雑用=その部下」となり、その当初はやる気あふれてた部下も新しい人が入ってこないかぎりはずっと雑用をすることになり、モチベーションもあがらない。
上司が部下を見下していることも、カン違いしている上司にはよくあることで、わざわざ部下に手数や手間をかけて頼む、というか、押し付けることもあり、部下個人の仕事、状況をまったく考えてない、自分の都合だけで部下を使う上司もいる。
社会人同士で働いてて、効率も優先されるべきオトナの職場でも、そういうのがまかり通ってたりもする。
機嫌次第で周りを振り回す上司もいるだろうし、部下をそうやって扱って使って当たり前ともともと思ってる上司もいるだろう。
それはそういう上司とか事業主が、部下を「いいように使えるもの」としてみなしてるからそういう態度になるんだと思う。普通なら、社会生活を営むうえで、いくらかは相手に配慮するのが当然でもある。それが職場で、上司か部下かというだけでなくなるものか。上司、部下以前に、同じ「人」としてお互いに敬意持って尊重し合ってやってかないといけない。
まあ、これを読んでる人も、心当たりがあったり、逆に「そんな甘いこと言ってたら現実はやってけないよ」と言う人もいるかもしれない。
自分が下っ端の時にそうされたから自分が上司になったら部下にそうする、といった、学生の部活のような意識もあるかもしれない。
部下を怒るのはいい、怒鳴ることもあるだろう、でもそこで「俺が若いころはな・・・」と言う上司はそこまで。ただの思い出話やエピソードで言うならまだしも、説教の時までそうやって言うのは部下の心には届かない。その上司も自分で自分に言い続けて自己満足のまま延々とやっていくことだろう。
上司と部下とで同じ目線で指示なり指導なりしないと部下もなかなか共感して聞けない。それをわかってる上司が今求められてもいる。
それで上から押さえられてストレスをためる部下が多いことで、社労士分野でいう「メンタルヘルス」的な影響も職場で出てくることもある。
または、「こんな職場いつかやめてやる」と、結局その部下や後輩に逆に“利用される”だけの会社になってしまう。
上司は、その時は部下をいいように使えていいかもしれない、でもその上司自身はそういう会社にずっといて、むしろ、他に行くとこもないだろうし、そのまま年をとっていくことになるだろう。
たとえば、同じ「45歳」とかになったとき、そういう上司の45歳と、そういう部下の45歳とではどちらが強く、前向きで、よりよくしようという気持ちが強いか。その意識の持ち方で「50歳」を迎える時の状況、個人的な充実度も変わってくると思う。
そして、部下についても2パターンあると思う。
ひとつは、将来、自分がついた、威張ってる上司と同じような上司に自分もなる、というパターン。それはまさしく体育会系の、部活のようなかんじ。「自分がかつてそうされたから、自分も部下にそうする」というパターン。
もうひとつは、自分がイヤな思いや理不尽な思いをして、それを自分がその会社でも他の会社に行っても、その当時のことを教訓、反面教師にしていい上司像を描いて実践していくパターン。
その2パターンでは、後者の部下の方が賢いとも思う。
前者の部下では悪循環を生むだけ、結局「自分さえよければいい」となり会社にとってコストやらデメリットになるだけだ。
後者の部下は、そうやって前向きに、冷静に上司や職場を見るからこそ、自分はそうなるまいと思うだろうし、実質的に“上司より上”の仕事への意識や考え方が(なかなかオモテには出せなくても)できることもある。
上司をナメる、というと表現は悪いけど、結局威張ってばかりの上司は部下からの敬意も人望もないし、部下の方が仕事においても人生においてもより高い意識で上司の知らない次元で伸びていく。
部下を伸ばす、新人を育て戦力にする、ということは、その部下の存在や気持ちに配慮して、同じ仕事を頼むにもクッションとしてひとつコトバをかけてあげることも大事。
上司の都合だけで「おい、これやっとけ」とエラそうに言うのではなく、部下自身も仕事をしてるんだから、「今いけるかな?これ、やっといてほしいんだけど」と同じ目線で仕事をする“仲間”として見ることが大事。
別に部下に媚びるわけではなく、仕事をしている“仲間”に配慮する、ということ。
それはある意味当然だし、そしてもちろん、上司にでもできる雑用を部下にさせて上司自身はラクしている、というのもどうかと思う。上司自身も同じ部署にいて、別にその部下に直接給料を払ってるトップでもないんだから、別に手が空いてる人がやったっていいことをわざわざ別の仕事をしてる部下に押し付けることもない。
そういう上司の姿を見て部下も冷めるだろうし、上司が部下を見て評価してるように、部下も上司を見て評価している。
そういう上司がいたりそういう体質のとこは、部下とか新人が育たない。
それもその職場にとってはデメリットだ。
そういう事業主とか上司にとっては自業自得でもあるけど、せっかく部下や後輩に時間を割いていろいろ教えたってすぐにやめられては無意味になる。
仕事の合う、合わないは人それぞれあるけど、仕事が難しいとかではなく「気持ち」でやる気を失わせては元も子もない。それを伸ばしてあげるのも周りの上司や先輩の配慮次第だ。
部下や新人も「俺、こんなとこで何やってるんだろう」と思うように扱われては、今後会社のためにと日々前向きに働けない。
業界問わず、そういう上司やそういう風潮はあるし、体育会系の会社は特にそうだろう。
特に古い体質だったり、極端にワンマンな社長や上司が仕切ってる会社はそうだろう。
そういうとこは人の出入りが激しかったりもする。
上下関係が厳しいのが悪いんではない、でも、部下自身が将来上司になったり会社内で幹部になったりする基本を育てるのもその時の上司でもあり、それで「こういう上司を見習おう」と思わせるか、「こんなふうにはなりたくない」と思わせるか、は、会社全体のモチベーションにも影響する。
ある不動産会社の社長が、若い社員を「下っ端」とか「兵隊」と呼んでいたことがあったそう。
自分がその「下っ端」にちょっとでも支えられている自覚を持ってたら社長もそういうコトバは言えないだろう。
大したことない「下っ端」なら、なんでその「下っ端」にも給料を払ってるのか。
自分が社長で自分が稼いで会社を回してるのはわかる、そのカネの一部でその部下も生活させてもらってるのも現実だろう。
でも、そこまで虐げられるような言い方でその部下が伸びるかどうか、モチベーションを高めて続けていけるかどうかは疑問だ。


















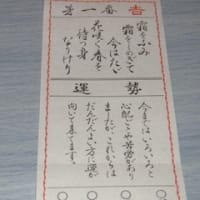

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます