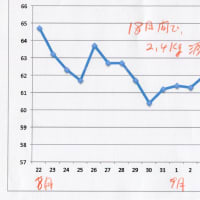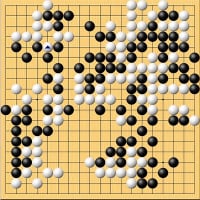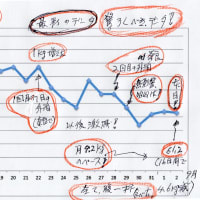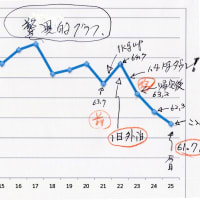かっては、古代中国より伝わった旧暦を使っていた。
旧暦は、月の満ち欠けを1カ月とする太陰暦だった。
しかし、月の満ち欠けの周期は、29日なので季節の変化とズレを生じる。
そこで、太陽の1年を24等分する「24節気」が出来た。
加えて「雑節」も取り入れられた。
旧暦は、立春を新年としたため、現在の暦とは、約1カ月のズレを生じた。
明治5年に、改暦され、翌年から世界共通の新暦に変わった。
これにより、暦日が約1カ月早められたため、従来の季節感に矛盾を生じた。
そこで、季節感を合わせるために、旧暦の7月15日であったお盆を、ひと月遅らせて調整した。
この改暦をテーマにストーリー化したのが、冲方 丁の「天地明察」という映画だ。
旧暦は、月の満ち欠けを1カ月とする太陰暦だった。
しかし、月の満ち欠けの周期は、29日なので季節の変化とズレを生じる。
そこで、太陽の1年を24等分する「24節気」が出来た。
加えて「雑節」も取り入れられた。
旧暦は、立春を新年としたため、現在の暦とは、約1カ月のズレを生じた。
明治5年に、改暦され、翌年から世界共通の新暦に変わった。
これにより、暦日が約1カ月早められたため、従来の季節感に矛盾を生じた。
そこで、季節感を合わせるために、旧暦の7月15日であったお盆を、ひと月遅らせて調整した。
この改暦をテーマにストーリー化したのが、冲方 丁の「天地明察」という映画だ。