
*
新規入院した患者のカルテをチェックしているとまた咆哮のような長い叫び声が聞こえてきて、智子は顔を上げた。
あの夜から何度目だろう。
検温に行くと由紀生は必ずこの声に対する考察を話そうとする。もちろんボイラーの音ではなく霊安室からというものだ。
智子がここに来てから霊安室は使用されたことがなく、過去にもほとんどないとかおるに聞いたことがある。死に直面するような重篤な患者はいないのだから当然と言えば当然だ。
だから、霊安室からという説はないときっぱり由紀生にも言ったが、まだ納得していない。というより、智子を怖がらせて楽しんでいるようにも思え、どう反撃してやろうかと、自分もちょっとだけ楽しくなっていた。
だが、声のようなものは確かに聞こえてくる。
ボイラーの音だと思うものの、正体はいったい何なのかはっきりさせたくもあった。
なぜなら、今は巡回中でここにいないが、あの声がするたびにかおるの顔を窺っても聞こえている様子がないからだ。
自分にしか聞こえていないなら、あれはボイラーの音ではないのではないか。
毎回その考えに行きつくと智子はぶるっと身を震わせた。
「見て見て。山尾君におごらせてやった」
戻って来たかおるが汗の浮いた缶コーヒーを二本、机の上に置いた。
「患者さんに? いいんですか?」
「いいの、いいの。
一階から戻って来たところ捕まえて、一本おごれっていったらなんて言ったと思う?
智ちゃんにならおごるけど、だよ。
で、わたしの分と二本おごらせてやったのさ」
そう言って笑って、かこっとプルトップを開けるとおいしそうに飲み始める。
「あ、いいな」
松橋が眠そうな顔で入ってきた。
「あ、よければどうぞ。先輩いいですか?」
「別にいいけど。山尾君泣くよぉ」
「わたしコーヒーだめなんで。山尾さんにはちゃんとお礼言っときます」
コーヒーを差し出すと松橋は喜んで飲み始めた。
突然、地の底から響くようなあの咆哮がはっきりと聞こえた。
松橋の上下に動いていた喉の動きが止まり、かおるの笑顔が強張る。それはほんの一瞬ですぐに動きは再開したが智子は見逃さなかった。
かおるもあの声が聞こえているのだ。知っていて知らんふりをしている。
それは松橋にも同じことが言えた。
なぜ二人はあの声について何も触れないのか、それはきっと触れてはいけない何かがあるからだ。
これでボイラーの発する音でないことが、智子にははっきりとわかった。










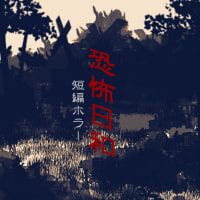
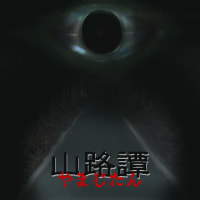

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます