「イラク水滸伝」を読み終わった感想。
イラクと言えば、湾岸戦争、サダム・フセイン、イスラム教?
水滸伝と言えば、なんか英雄譚?みたいな??ピカレスクもの??
くらいのイメージしかなくて、つまりは正直に言ってしまうとどちらもそんなに興味がなかったのに、この本を手に取ったのは「イラク」と「水滸伝」という2つの単語がアンビバレントな感じがしておもしろそうに聞こえたから。
イラクは中学生の時に社会科で習った「ティグリス・ユーフラテス川流域に生まれたメソポタミア文明」の地だから、考えてみれば水場があるのが当たり前なんだけど、なんとなく乾燥してずっと砂漠が続くイメージを持っていた。
この本はノンフィクション作家の筆者と林業専門家兼環境活動家兼冒険家の山田隊長がイラクの湿地帯に昔ながらのタラーデ(舟)を浮かべようとする物語(端折りすぎなので、気になったら読んでください)。
読んだ結論としてはめちゃくちゃ勉強になった。
①イスラムのスンニー派とシーア派について
イスラム全体としてはスンニー派が多数派で9:1くらいの割合だけど、イラクではシーア派が多数派。
これは絶対に大学で「イスラム世界の歴史」的な講義をとったときに耳にしているんじゃないかと思うけど、正直さっぱり頭のメモに残っていなかった。
イスラムの歴史、オスマントルコに憧れて軽い気持ちで選択して、脳みそが混乱したままギリギリ及第の成績で終えてしまった渋い思い出がある。
勝手に勢力が拮抗しているイメージだったから、こんなに割合が違ったんだと衝撃。
これでもう忘れない!
②イラクは一応は民主主義国家となっているけれど、実際はイスラム原理主義の考え方が強い。
イランは原理主義国家のような風体をしているけど、実際は本音と建て前を使い分けていて世俗的な部分も多い。
なるほどー。
③湿地帯で放牧(?)されている水牛は3000年も前から家畜化されていたかもしれない。
DNA配列を調べるとそういう結論が予想できるらしい。
ロマンがある。
④グノーシスという思想。
哲学系かなにかの講義で聞いて、なんかハリーポッターにいそうな響きだと思っていた‥
グノーシスは「この世界は間違った神によって創られた間違った世界だ」「人間の魂の本来の居場所は真の神のいる光の世界」というような思想のことらしい。
アフワール(この本で出てくる湿地帯)にいるマンダ教徒はグノーシス的な考え方をするそう。
④イラクは世界屈指の産油国なのに、自分の国で十分に火力発電を行えないため、イランから電気を買っている。
なんかせっかくのポテンシャルがもったいない。
⑤湿地帯伝統の舟(タラーデ)は三日月型でめちゃくちゃ素敵。
月明かりの下、夜の湖に浮かべたいと思ってしまったけど、水に落ちたら危険すぎるのできっと無理。
そしてイラクの情勢的に女性が旅にいけるようなときが当分来るような気がしないので、残念だけど私が直接見る機会は訪れなそう(この本の旅は男性2人だけどそれでも大変だし危険なこともあっただろうなという感じがする)。
しかもタラーデは実際にはもうあまり使われていなよう。
まぁどう考えてもモーターボートのほうがずっと便利だろうなーとは思う。
残念だと思うけれど、それはきっと自分がそれで生活するわけでもない第三者のお気楽な意見なんだろうな。
⑥ノコギリには押すときに切れる「押しノコ」と引くときに切れる「引きノコ」がある。
イラクは地理的にはヨーロッパ(押しノコ派)に近いのに、日本や中国と同じ引きノコ派。
ちょっとした親近感。
⑦ブリコラージュという言葉。
「あり合わせの材料を用いて自分でものをつくること」「その場しのぎの仕事」の意。
文明社会の「エンジニアリング」とは対照をなすそう。
イラクの人々の行動はブリコラージュ的。
私はどちらかというと色々なことを逆算して計画しちゃう派だから、多分近くにいたらイライラしてしまうだろうけど、楽しそうなことは確か。
⑧イラクの「治安部隊」は軍なのか警察なのか民兵なのか判然としていない。
イラクのニュースを聞いても状況がよくわからないことがあることの一因のような気がする。
「治安部隊」と聞いて、勝手に自衛隊的な統制がとれた組織を思い浮かべていた。
⑨湿地帯に住む人々は読み書きができない人が普通にいて、自分の名前を書けないこともあるけど、それでもFacebookは普通に浸透している。
すごいな、Facebook。
⑩イラク料理は意外とすごく美味しそう。
ご飯が美味しい土地は山と海がある所と思っていたから、まったくそんなイメージはなかったけど、イラク料理は美味しいらしい。
特にゲーマル(水牛の乳でつくるチーズかクリームのようなもの)はこの本の中で絶賛されている。
職場の珍味好きに話したら興味を示して、水牛の乳が入手できないか調べたけど無理だったそう。
レシピはこの本に書いてあったので、2人でなんとか作って食べられないかと色々ググった結果、水牛の乳のほうが牛乳より脂肪分が高くて、それがポイントではないかという話になり、同じくらいの脂肪率の羊の乳が入手できないかと調べたけど、それもなくて断念。
(全然関係ないけど、アザラシの乳の脂肪率の高さとサイの乳の脂肪率の低さにビックリ。ほぼクリームとほぼ水。)
イラク料理のお店はググっても日本地図上には1件も出てこないし、ゲーマルを味わうのはあきらめるしかなさそう。
だれか水牛を飼っている方、チーズ(ゲーマル)屋さんをやってくれないかなぁ。
などなど。
そこそこのページ数があるので読むのに時間がかかってしまったけど、期待以上におもしろかった。
イラクに対して政治とか宗教の対立ばかり思い描いていたけど、湿地帯で暮らす人々はわりと宗教観もゆるやかで政治とは距離を置くノンポリって感じだった。
そんな人々もいるんだなと思った。想像したこともなかった。
宗教激戦区の中東でそういった生き方ができるのは、湿地からの恵みでほぼ自給自足の生活ができるからだと思う。
ただやっぱり乳児や高齢者は町で暮らしているようなので、みんながみんなそんな暮らしをするのは無理で、人生の弱い時期を支える社会システム(政治や宗教)がないと安心して生きていくのは難しいよなとも思った。
それが対立の原因になって、人の命を奪うこともあるから皮肉だけど。


















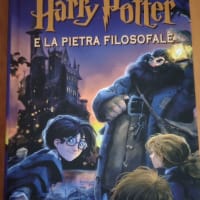

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます