
~エピローグ 竜の死~~
北半球の半分をおおうユーラシア大陸の東端で、今、一頭の竜が死にかけていた。
玉を追う形で大きく身をうねらせ、尾を跳ね上げた体のいたるところから火と煙を噴出し、その全身は内部よりこみ上げてくる痙攣によって、絶え間なく打ち震え、かつて、巍然(ぎぜん)と聳え立つ棘の間に、緑の木々を生い繁らせていたかたい背は、網の目のようにずたずたに切り裂かれ、その傷口からは、熱い血が脈打って流れだしていた。
その柔らかい下腹を太古よりやさしく愛撫しつづけてきた暖かな黒潮の底から、今は冷たい死の顎(あぎと)が姿をあらわし、獰猛な鱶(ふか)の群れのように、身を翻しては、傷ついた竜の腹の肉のひとひら、またひとひらを食いちぎり、果て知れぬ深海の底の胃袋へと呑み込んでいった。
1 あご。おとがい。
「毒竜の―に噛まれるもの」〈芥川・地獄変〉
2 (鰓)魚のえら。
房総半島の先端は数十mも沈下し、陸中海岸は、太平洋側に斜めに突っ込みながら、20m以上も動いていた。
北海道は苫小牧、小樽が海水に浸水し、根室、知床が本土から切れて水没した。
南西諸島や沖縄のいくつかの島は、すでに姿を消していた。
4億年前、幼い竜の種が、古い大陸の縁辺に蒔かれたとき、地の底にあって竜をゆっくり大洋に向けて押し続けた。
母なる大陸を離れて、波荒い大洋へ泳ぎだすにつれて、竜は大きく育ち、体は次第に高く聳え、
その姿も雄渾溌剌(ゆうこんはつらつ)として堂々たる成年の威容を備えてきた。
だが、今、その竜を押す巨人の盲目の力は、突如として竜の背骨をへし折り、その体をくつがえし、
大洋へ突き落とそうとする凶暴なものに変わってきた。
日本海側から押す力は、とくに本州中央部において強く。。。
泡立つ濁った海水は、南、中央アルプス山麓を直接洗い。。。
関東平野は一面の浅海となり、高崎、館林、古河のあたりまで、三千トン級、喫水5mの船が航行できるようになった。
そして福岡と久留米、大牟田は一面の水でつながってしまった。
仙台平野も、仙台湾の水がはるか北方の一関、平泉のあたりまで浸水し、
北海道では、太平洋の水が帯広まで、また釧路平野の標茶(しべちゃ)まで押し寄せ、
根釧(こんせん)大地は、ずたずたに裂けたリアス式海岸の様相を呈していた。
やがてその冷たい死の手が、灼熱の心臓と出会うとき、竜の体はばらばらに引き裂かれ、
無数の断片となって虚空に四散するだろう。
竜の咆哮、痙攣、天に向かって吐く火と煙の息遣いは、すでに断末魔のそれを思わせた。
悶え、もたうち、毒を吐きつつ死んでゆく竜を、かつておのれの体の一片をもって生み出した年老いた母なる大陸は、
いたましげな眼つきで見守っているようだった。
陸より古く、陸よりもはるかに巨大な大洋は、その底にとりこもうとする犠牲(いけにえ)に対して、
冷ややかで、超然とした態度をとり続けているようだった。
伝説のアトランティスもムウもこの果てしない歴史の間、海中より生まれ、また沈んだ陸の数々にくらべれば、ものの数ではない。
遊弋(ゆうよく)
動態地球学
この地球の惑星進化の長い歴史の中で、。。。
アトランティスの急激な破壊と沈没が。。。
インドやオーストラリアの学会の一部では、アトランティス伝説よりはるかに荒唐無稽とされているあのチャーチワードの「ムウ大陸神話」され、考えなおしてみるべきだ、という風潮が起こりかけていた。
日本国内で使用できる国際空港は、千歳だけになってしまい、その閉鎖も時間の問題だった。
あとは、たとえば青森などのように比較的高い土地にあるローカル空港の一部や。。。
航空輸送に使うより仕方がなかった。
ソ連陸軍の大型輸送機の性能は、眼をみはらせるものだあった。
速度などの点はともかく、とにかく着陸装置が頑丈で、帰投燃料まで積んだかなりの重量で、
相当深い草原や凹凸の土地に、らくらくと着陸してくるのだった。
変動開始後の死者、行方不明者の数字は、第二次関東大震災を含めると、すでに千二百万人を越えていた。
茨城県水戸市木葉下(あほっけ)
東海村の原子力発電所、すでに海面下数十mに沈んでしまっていたが、
高放射能の核分裂生成物(フィッションプロダクツ)、つまり核燃料の「灰」にあたるものが流出して。。。
那須火山帯の、男体山(なんたいさん)や釈迦ヶ岳が噴火してる音だろう・・・
「すると、筑波山が鹿島灘へ突っ込んでるってわけですか?」
そう、と口の中でつぶやいた。そして、日本海溝へ、だ。
例年より6℃近くも気温の低い冷たい夏が、列島の上を分厚く覆う灰の雲の下に、死の影のように忍び寄っていた。
成層圏近くに吹き上げられた何万トンという細かい灰は、やがて北半球の上をぐるりとめぐり、
2年あと、3ねんあと、全世界は冷たい夏と大凶作に見舞われることだろう。
残った2000万人の菜中には、救出の順番を他に譲って、自らすすんで残った人たちもかなり含まれていた。
その中では、七十歳以上の高齢者が圧倒的に多かった。
この美しい、慣れ親しんだ国土が永遠に失われては、もはや生きている甲斐もない、というので、
夜半書き置きして自ら家族を離れ、集結地から姿を消すものが少なくなかった。
これまた圧倒的に男性が多かった。
「なぜ、死になさる・・・」
「わかりません。悲しい・・・からでしょうね。」
「悲しいから・・・ほう・・・」
「科学というものは、直感だけでは、受け付けてくれませんからね。証明がいるのです」
「隠しておきたかったのです。そうして・・・準備が遅れて・・・もっとたくさんの人に、日本と・・・
この島といっしょに・・・死んでもらいたかったのです・・・」
「日本人はみんな、おれたちの愛するこの島といっしょに死んでくれ。
今でも、そうやったらよかった、と思うことがあります。
なぜといって・・・海外に逃れて、これから日本人が、味わわねばならない、辛酸のことを考えると・・・」
「なるほどな。それでわかった。あんた・・・この、日本列島に恋をしていたのじゃな・・・」
「そのとおりです。ええ・・・惚れるというより、純粋に恋をしていました」
「その限りなく愛し、いとおしんできた恋人の体の中に、不治の癌の兆候を見つけた。
それで、悲しみのあまり・・・」
「わたしは、あれを見つけたときから、・・・この島が死ぬとき、いっしょに死ぬ決心をしていた・・・」
「つまり心中だな・・・」
「日本人というものは、この四つの島、この自然、この山や川、この森や草や生き物、
町や村や、先人の住み残した遺跡と一体なんです。
このデリケートな自然が、島が、破壊され、消え失せてしまえば、もう、日本人というものはなくなるのです。」
明治21年の、磐梯山噴火のときに、両親をいっぺんに失い。。。
その女性がまた、明治27年の庄内大地震で死んでもうた。
わしは、奇妙に、地震や噴火に関係がある。
「日本人はな・・・これから苦労するよ・・・。
だが、世界の中には、こんな幸福な、温かい家を持ち続けた国民は、そう多くない」
中九州の阿蘇と、雲仙の一部が、辛うじて水面から出て、爆発を続けていた。
西日本は、琵琶湖のところで、竜の首が千切れるように、東端が南へ、西端が北へ回転するように動き、
ずたずたに切れた断片となって、なお沈下を続けていた。
東北も北上山地は、もう数百mの海面下にすべり、
奥羽山脈は、これまた四分五裂して、爆発を続けていた。
北海道は、大雪山だけがひょっとすると海面上に残るのではないか、と言われていた。
この作品を書くにあたって、
地震学の権威、坪井忠二先生
また地球物理学の竹内均先生のご著作から、数多くの啓発をうけ、
参考にさせていただいた。巻末を借りて、お礼を申し上げたい。
なお、この作品は完全なるフィクションであって、いかなる実在の人物、事件をも、モデルにしていない。
北半球の半分をおおうユーラシア大陸の東端で、今、一頭の竜が死にかけていた。
玉を追う形で大きく身をうねらせ、尾を跳ね上げた体のいたるところから火と煙を噴出し、その全身は内部よりこみ上げてくる痙攣によって、絶え間なく打ち震え、かつて、巍然(ぎぜん)と聳え立つ棘の間に、緑の木々を生い繁らせていたかたい背は、網の目のようにずたずたに切り裂かれ、その傷口からは、熱い血が脈打って流れだしていた。
その柔らかい下腹を太古よりやさしく愛撫しつづけてきた暖かな黒潮の底から、今は冷たい死の顎(あぎと)が姿をあらわし、獰猛な鱶(ふか)の群れのように、身を翻しては、傷ついた竜の腹の肉のひとひら、またひとひらを食いちぎり、果て知れぬ深海の底の胃袋へと呑み込んでいった。
1 あご。おとがい。
「毒竜の―に噛まれるもの」〈芥川・地獄変〉
2 (鰓)魚のえら。
房総半島の先端は数十mも沈下し、陸中海岸は、太平洋側に斜めに突っ込みながら、20m以上も動いていた。
北海道は苫小牧、小樽が海水に浸水し、根室、知床が本土から切れて水没した。
南西諸島や沖縄のいくつかの島は、すでに姿を消していた。
4億年前、幼い竜の種が、古い大陸の縁辺に蒔かれたとき、地の底にあって竜をゆっくり大洋に向けて押し続けた。
母なる大陸を離れて、波荒い大洋へ泳ぎだすにつれて、竜は大きく育ち、体は次第に高く聳え、
その姿も雄渾溌剌(ゆうこんはつらつ)として堂々たる成年の威容を備えてきた。
だが、今、その竜を押す巨人の盲目の力は、突如として竜の背骨をへし折り、その体をくつがえし、
大洋へ突き落とそうとする凶暴なものに変わってきた。
日本海側から押す力は、とくに本州中央部において強く。。。
泡立つ濁った海水は、南、中央アルプス山麓を直接洗い。。。
関東平野は一面の浅海となり、高崎、館林、古河のあたりまで、三千トン級、喫水5mの船が航行できるようになった。
そして福岡と久留米、大牟田は一面の水でつながってしまった。
仙台平野も、仙台湾の水がはるか北方の一関、平泉のあたりまで浸水し、
北海道では、太平洋の水が帯広まで、また釧路平野の標茶(しべちゃ)まで押し寄せ、
根釧(こんせん)大地は、ずたずたに裂けたリアス式海岸の様相を呈していた。
やがてその冷たい死の手が、灼熱の心臓と出会うとき、竜の体はばらばらに引き裂かれ、
無数の断片となって虚空に四散するだろう。
竜の咆哮、痙攣、天に向かって吐く火と煙の息遣いは、すでに断末魔のそれを思わせた。
悶え、もたうち、毒を吐きつつ死んでゆく竜を、かつておのれの体の一片をもって生み出した年老いた母なる大陸は、
いたましげな眼つきで見守っているようだった。
陸より古く、陸よりもはるかに巨大な大洋は、その底にとりこもうとする犠牲(いけにえ)に対して、
冷ややかで、超然とした態度をとり続けているようだった。
伝説のアトランティスもムウもこの果てしない歴史の間、海中より生まれ、また沈んだ陸の数々にくらべれば、ものの数ではない。
遊弋(ゆうよく)
動態地球学
この地球の惑星進化の長い歴史の中で、。。。
アトランティスの急激な破壊と沈没が。。。
インドやオーストラリアの学会の一部では、アトランティス伝説よりはるかに荒唐無稽とされているあのチャーチワードの「ムウ大陸神話」され、考えなおしてみるべきだ、という風潮が起こりかけていた。
日本国内で使用できる国際空港は、千歳だけになってしまい、その閉鎖も時間の問題だった。
あとは、たとえば青森などのように比較的高い土地にあるローカル空港の一部や。。。
航空輸送に使うより仕方がなかった。
ソ連陸軍の大型輸送機の性能は、眼をみはらせるものだあった。
速度などの点はともかく、とにかく着陸装置が頑丈で、帰投燃料まで積んだかなりの重量で、
相当深い草原や凹凸の土地に、らくらくと着陸してくるのだった。
変動開始後の死者、行方不明者の数字は、第二次関東大震災を含めると、すでに千二百万人を越えていた。
茨城県水戸市木葉下(あほっけ)
東海村の原子力発電所、すでに海面下数十mに沈んでしまっていたが、
高放射能の核分裂生成物(フィッションプロダクツ)、つまり核燃料の「灰」にあたるものが流出して。。。
那須火山帯の、男体山(なんたいさん)や釈迦ヶ岳が噴火してる音だろう・・・
「すると、筑波山が鹿島灘へ突っ込んでるってわけですか?」
そう、と口の中でつぶやいた。そして、日本海溝へ、だ。
例年より6℃近くも気温の低い冷たい夏が、列島の上を分厚く覆う灰の雲の下に、死の影のように忍び寄っていた。
成層圏近くに吹き上げられた何万トンという細かい灰は、やがて北半球の上をぐるりとめぐり、
2年あと、3ねんあと、全世界は冷たい夏と大凶作に見舞われることだろう。
残った2000万人の菜中には、救出の順番を他に譲って、自らすすんで残った人たちもかなり含まれていた。
その中では、七十歳以上の高齢者が圧倒的に多かった。
この美しい、慣れ親しんだ国土が永遠に失われては、もはや生きている甲斐もない、というので、
夜半書き置きして自ら家族を離れ、集結地から姿を消すものが少なくなかった。
これまた圧倒的に男性が多かった。
「なぜ、死になさる・・・」
「わかりません。悲しい・・・からでしょうね。」
「悲しいから・・・ほう・・・」
「科学というものは、直感だけでは、受け付けてくれませんからね。証明がいるのです」
「隠しておきたかったのです。そうして・・・準備が遅れて・・・もっとたくさんの人に、日本と・・・
この島といっしょに・・・死んでもらいたかったのです・・・」
「日本人はみんな、おれたちの愛するこの島といっしょに死んでくれ。
今でも、そうやったらよかった、と思うことがあります。
なぜといって・・・海外に逃れて、これから日本人が、味わわねばならない、辛酸のことを考えると・・・」
「なるほどな。それでわかった。あんた・・・この、日本列島に恋をしていたのじゃな・・・」
「そのとおりです。ええ・・・惚れるというより、純粋に恋をしていました」
「その限りなく愛し、いとおしんできた恋人の体の中に、不治の癌の兆候を見つけた。
それで、悲しみのあまり・・・」
「わたしは、あれを見つけたときから、・・・この島が死ぬとき、いっしょに死ぬ決心をしていた・・・」
「つまり心中だな・・・」
「日本人というものは、この四つの島、この自然、この山や川、この森や草や生き物、
町や村や、先人の住み残した遺跡と一体なんです。
このデリケートな自然が、島が、破壊され、消え失せてしまえば、もう、日本人というものはなくなるのです。」
明治21年の、磐梯山噴火のときに、両親をいっぺんに失い。。。
その女性がまた、明治27年の庄内大地震で死んでもうた。
わしは、奇妙に、地震や噴火に関係がある。
「日本人はな・・・これから苦労するよ・・・。
だが、世界の中には、こんな幸福な、温かい家を持ち続けた国民は、そう多くない」
中九州の阿蘇と、雲仙の一部が、辛うじて水面から出て、爆発を続けていた。
西日本は、琵琶湖のところで、竜の首が千切れるように、東端が南へ、西端が北へ回転するように動き、
ずたずたに切れた断片となって、なお沈下を続けていた。
東北も北上山地は、もう数百mの海面下にすべり、
奥羽山脈は、これまた四分五裂して、爆発を続けていた。
北海道は、大雪山だけがひょっとすると海面上に残るのではないか、と言われていた。
この作品を書くにあたって、
地震学の権威、坪井忠二先生
また地球物理学の竹内均先生のご著作から、数多くの啓発をうけ、
参考にさせていただいた。巻末を借りて、お礼を申し上げたい。
なお、この作品は完全なるフィクションであって、いかなる実在の人物、事件をも、モデルにしていない。










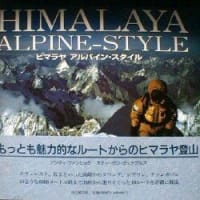
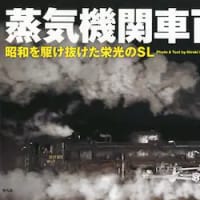
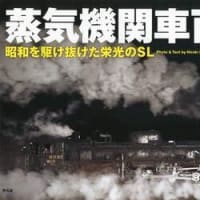
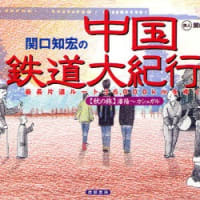
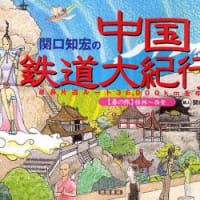
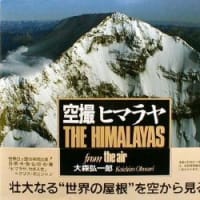

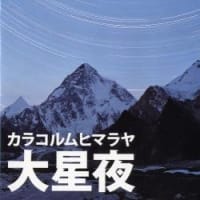
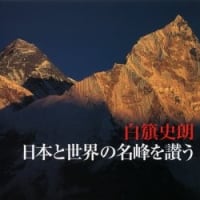
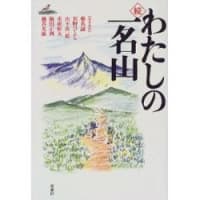
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます