1936年は日本の登山史上に輝かしい一頁を記録した忘れられない年である。
それは日本から初めてのヒマラヤ遠征隊が立教大学山岳部からガルワール・ヒマラヤのナンダ・コットに派遣され、見事に初登頂に成功したからである。
ナンダ;「多幸の、祝福された」
コート;「要塞」
すでに6400m。
西北の空にはナンダ・デヴィの2尖峰が眉に迫るほど近い。
手前が東峰、うしろは主峰だ。
この主峰が1ヶ月前に英米隊のティルマンとオーデルによって登頂されたかと思うと、猛然とファイトが沸きあがってくる。
ピラミッド型のカメットや、バドリナート山群が朝焼けに映えている。
ロングスタッフのコル;峠
斜面の細い筋は「ヒマラヤ筋」といって、新雪雪崩の跡である。
見上げると、頂上を形づくるピラミッドは凄く急峻で、ことにシャールン谷側は文字通りの絶壁となり、雪もはりついていない。またナンダ・コット氷河に面している正面壁は、45度の急角度で一気に二千数百mも落ちている。
風と雪がますます猛威をふるって、ナンダ・コットは生あるもののように、われらの登高を徹底的に拒否する。
寒気が刻々とつのる夕暮れの行動には、死の危険が待ち構えている。
せっかくここまで登ってきたのだ、突っ込んでいきたい。
アイモ撮影機
シャールン谷から吹き上げる烈風は身体をなぎ倒すほどひどい。
2坪あるかどうかと思われるほど狭い頂上の雪の上に6人も立っている・・・
チベット高原が謎の姿を横たえ、中ほどに山帽子のような山がある。
あれが聖山と仰がれるカイラス山か。
なるほどうわさ通りの、リンガ;男根そっくりである。
カイラスのはるか北にたなびく雲のように東西に走っているのが、スウェイン・ヘディンが発見したというトランス・ヒマラヤであろう。ナンダ・デヴィ主峰の左はるか遠くに岩と雪のガッチリとした山はバドリナート山魂であろうし、その右手に三角水晶のように印象的に輝いているのがカメット;7757mである。
グルラマンダータ
グルン族;グルカ兵
インドやイギリスに雇われているが、非常に質実で、強いので有名である。
次男三男はインドに出て傭兵となる。
インパールやビルマで日本兵をさんざんやっつけたグルカ兵は、グルン族やマガール族の出身なのである。
低地の民族は非常に早婚で、こんなのがとビックリするような小娘が赤ん坊を抱いているのを多く見かけた。ポカラの町で娘たちの成人式を見たことがある。8歳から13歳ぐらいまでの小娘2、30名が、インド教祠に集まって、頭や手足に真っ赤な粉を塗って身を清めてもらっていた。もうその翌日にでも婚約ができるのだと聞かされてあきれてしまった。
ラマ教徒になると、一妻多夫、一夫多妻いりまじって、何がなんだか判らなくなる。
霊魂不滅を信じるインド教徒の墓所はガンガ:ガンジス川であるから、
地上には墓がないのである。
タルチョと呼ばれる布のぼりは、ボンきょう;シャーマン教のシンボルともいわれる。
チベットにラマ教が布教される前にボン教が普及していた。
ヒマラヤの山中の住民は、神が住む山と悪魔が住む山があると思い込んでいる。
カイラスはインド教、仏教両教徒から最も神聖な山として巡礼の跡を絶たない。
※ボン教、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の聖地なので、登頂はできない。
またガルワール・ヒマラヤのバドリナート;Badrinath
※シャンカラが訪れたとされる4つの巡礼地のひとつであり、ヒンドゥー教の聖地とされる
とケダルナート;Kedarnath Templeはインド教の二大神であるシヴァとビシュヌを祀っているために、キリスト教のエルサレムに相当する聖地とされている。
ラマ教徒の聖山マナスル別名;カンブンギェン:氷の肩の意
ラマ教徒は生まれ落ちたときにラマによって運命判断をされ名前をつけてもらう。
カトマンズを一歩離れると、正規の勉強をした医者など1人もいない。
草ね木皮を煎じて飲ませるか、加持祈祷に頼るのである。
だから日本隊のドクターは、まるで救世主のように有難がれ、遠いところから泊まりがけで病人を背負って診てもらいにくる。チベット人は軽い病気ならば、日光浴でなおす。
重病人は部屋に入れて看病するが、昏睡状態になると、水滴を顔に落として眠らぬようにする。眠ると悪魔に魂をさらわれると信じているのだ。
チベット人の習慣では、家で息を引き取らせることをせず、いよいよ命脈が切れたとみると、瀕死の病人を河原に連れて行って置き去るとの話である。
さて死んでしまうと、頭に温かみがあれば、天上界に生まれ変わる証拠であり、足元に温かみがあれば、地獄落ちする印であるといわれる。
死体は汚いボロ布に包まれ、両膝のあいだに頭を挟んで固くしばって丸くする。
そして日を選んで死体運搬人に渡す。
死体はもう魂の去った石ころと同じものとされ、親兄弟も付き添わない。
死体は川岸か岩の上に運ばれて、死体解剖者によって、肉と骨をはなされ、肉ダンゴと骨ダンゴを作ってハゲタカやカラスに与えられる。
早く食べられると、後生が良かったと喜ぶ。
死刑になった者とか、疫病の死体は埋葬される。なぜ火葬にしないかと聞くと、焼いた煙が天を汚すと、時ならぬ嵐になり、ヒョウが降ってきて作物を荒らすからだとの答えだった。
腸チブスが蔓延していて、ペニシリンの注射をしたら
「日本のお医者さんは死人を生きかえらせた」
ラジオも電話もないこの山中で、ビックリするほど早く、谷から谷へと風のように伝わっていった。
ヒマラヤ山中には井戸がない。
泉や谷川の濁った水に頼っている。
彼らの住む高地は不毛に近く、大麦、ソバ、ジャガイモをわずかに収穫する。
モロコシ、ヒエ、米などは下界からあおがなければならない。
大麦粉を炒って、ヤクの乳とかバターを混ぜて水かお湯でこねたツァンバを主食とする。野菜といえばトウガラシ、ニンニク、ジャガイモである。
チベット人はバターを入れた茶を一日20杯も飲むそうで、実に栄養がよく、近づくとプーンと乳の匂いがする。
ヒマラヤ山中の住民はタバコ亡者である。
男女とも5歳ぐらいから吸い出す。
タバコはすべてインドから輸入される。
多くの者は自家製のタバコを吸っている。
これには大麻そのほかの麻薬が入っている。
これを大小のキセルで吸う。
ヒマラヤ山中では、「タバコ屋へ7日」である。
マナスルの麓サマ村の人が、タバコを吸いたくなると、ブリ・ガンダキの渓谷をかれらの早足で7日下ってアルガト・バザールまで出なければならないのだ。タバコに限らず日用品などの雑貨を売る店も同様に低地のバザールにしかないのである。
ネパールの首都カトマンズからマナスルの麓までの190kmを、18日かかっての徒歩旅行に同行したポーターの数は、
1952年に75人
53年に300人
54年に450人
56年に400人となった。
ネパール米は小粒で、赤いもの、どす黒いもの、緑のものなど多彩であるが、煮るとなんともいえない臭気が鼻をつく。これにはみんな閉口してハシをつけたがらない。それよりも困ったことには、小石がいっぱい混じっていることだ。
アタ;小麦粉はよく買ってチャパティ;センベイをつくり、ギー;羊油で揚げて食べた。
精選されていないので、フスマが多く混じっていて色の黒い粉であった。野菜はニンニク、トウガラシのほかはほとんど見当たらなかった。
シェルパは火を神聖視して、肉でも魚でも直接火にあてて焼くことをしない。
「神聖な火に獣の肉を直接あてて、罰があたりますぞ」
富士山より90m高いマナスルのベース・キャンプに到着すると、誰からともなく時ならぬ放屁の轟音を発するようになった。しかも時と所を選ばずに発するのだから、誰も困った。
帰路3000m付近に下りると、申し合わせたように、ピッタリと止まった。
日中と日没後の温度差の激しさは、ちょっと想像もできない。
日中の最高温度は摂氏20~30℃になり、いったん陽が沈むと、急激に下がってたちまち零下になり、夜明けごろにはー20℃にもなる。マナスルでの最低温度は零下35℃だった。
長く滞在すると次第に衰弱を増して、精神状態も普通でなくなる。
ゴザインクンデの山中にあるイョルモなどは、ネパール一の美人の産地。
いよいよ氷雪の中の生活に入ると、酷寒、酸素欠乏などの悪条件が重なって、とても性欲など起こるものではないと、私自身の経験から他人をも律していた。
っところがそうではなかった。
7100mの第八キャンプで自慰行為を敢行した超馬力の2人の山男があった。
映画「マナスルに立つ」
で、落差2000mの大雪崩のシーンがあるが、ヒマラヤでは雪崩の危険はつきものである。
エヴェレストで7名のシャルパがさらわれたり、ナンガ・パルバットでドイツ人7人、シェルパ9人が一瞬に呑みこまれたり、その他雪崩に呑まれた登山家が多い。
ヒマラヤの雪崩は時と場所をまったく予測できない。
なにしろ山のスケールが桁外れに大きいので、登山家の目はコロリとだまされ、意外なときに遭難事件を起こす。
ラルキャ氷河からマナスルのプラトウ方面をのぞいていた隊員の1人は、ワーッ、と大声あげたので、「なんだ、なんだ」と寄っていくと、彼は顔をゆがめて、マナスルを指している。
プラトウから幾筋もの雪崩跡が見える。その一筋はまさしく、第七キャンプのあった跡を通っている。もし数日私たちのスケジュールがずれていたら、あの雪崩の下敷きになっていた。
日本とは「反物が安い国」という噂を聞きかじっている程度だった。
マナスルはグルカ県にある。
グルカ県は例の勇猛で知られるグルカ兵の故郷なのである。
至るところでグルカ兵の帰郷者や傷痍者に出会った。
ある村で、右腕と左足を失った人に会った。
「インパールで受けた傷だ。あれたちグルカ兵はイギリスに雇われて戦ったんだから、日本に恨みなんぞ持っていない」
チベットからは岩塩、羊毛、染料、毛皮などがヤクや羊の背に乗って下ってきて、この貿易路で交換される。取引量の最も多いのは岩塩であるから、この道を「塩街道」とも呼ぶ。
東西をつなぐ街道のなかで最も重要視される1本は、カトマンズと西210kmにあるポカラをつなぐ街道。
数年前に開通した空路によれば30分で行けるのに、街道そのものは千年前と少しも変わりなく、自転車はおろか、馬さえ通わない。そこで旅人はテクテクと15~18日も歩く。
我々は「ウンコ街道」と命名した。
ネパール人の置き忘れたウンコは、どれもこれも物凄く太くて長い。
彼らは、ヒエ、モロコシなどの主食以外からは栄養を摂らないので、大食いとなり、その結果「おおグソ」をたれるようになる。
ヤクは暑さに弱い動物で、標高3000m以下では役にたたない。
モロコシの育つところにはヤクは住めないといわれる。
ヤクは年中放牧されていて、屋内で眠ることを知らないし、人から餌をもらうことも知らない。草を求めて次第に高地に登っていく習性がある。
ヤクの眼はちょっと凄みがあるので、恐ろしくて近寄れない。
ヤク追い人が後ろから追いたてると歩くが、さもないと道草ばかりくっている。
そしてすぐに一列横隊になる習性をもっている。
ヤクの毛は冬になると、地面すれすれになるまで伸び、膝の毛は袴をはいたような格好になる。これを刈り取ってナワや織物にする。
ヤクとコブ牛の雑種を「ゾー」という。
この乳からとったバター、チーズ、ヨーグルトはチベット人にとって欠くことのできない栄養となる。
マナスル隊は犬に縁が深いようだ。
53年の第一次隊には「ロン」
第二次隊には「ラト」「ハク」
第三次隊には「ビリー」がそれぞれ同行した。
ネパール三大仏塔の随一といわれる「ボーダーラマ寺院」
カトマンズ郊外、カカニの丘;
ニルカンタ公園
スインブー寺院
早く起きて練兵場広場からヒマラヤの雪峰を望んだ。
ゴザインタン、ランタン・ヒマール、ガネッシュ・ヒマールが前山から顔をのぞかせている。
こんな美しい山の町は世界のどこにもあるまい。
夕食に柿がでた。ネパール産だという。
小粒だが、まさしく柿である。
ネパールでもカキと呼ぶのだそうだ。
「ほんとうに大丈夫ですか」と念を押すと、顎をグッと後ろへひいた。
この身振りがOKの印なのである。
カトマンズ郊外、カカニの丘の眺望は世にも素晴らしいものだった。
2200mの丘の上に立つと、北の空にエヴェレストをはじめネパール・ヒマラヤの巨峰群が指呼の間にあり、その山肌をおおう氷雪の冷たさ、吹きまくる寒風のいたさがじかに身にしみるほどである。
エヴェレストの右にマカルー、さらに右の端にカンチェンジュンガが霞んでいる。
こうして、ボクの目にはいっているヒマラヤの巨人峰は実に8座を数えるのだ。
8000mの巨人峰が世界で13座ある中で、8座を一目で見渡せるという雄大な展望台は、ここをおいて他にあるまい。
チベットの山湖でとれる岩塩は沙羅双樹(サル・トリー)の広い葉に包まれている。
山国ネパールはチベットの塩に頼っている。
塩は米とともに物価の標準になる。
米2対塩1という割合。
ネパールの旅人は自分の寝具や炊具を持って歩き、薪は途中で拾っていくので、宿屋では泊まり賃だけでよいのだ。人夫などは大木の下か岩穴を常宿にするのだという。
なるほど、街道の至る所に岩穴があり、煙で真っ黒にくすぶっている。
トリズリ・バザールはチベット街道とポカラ街道の交差点にあたる大きなバザールである。
ポカラ;国際山岳記念館
チョーターラは熱い国の街道のオアシスだ。
村の娘たちはパパイヤ、バナナ、キウリを並べていたり、モロコシかヒエからつくった地酒「ロキシー」を一杯5、6円で売っている。
ネパールの田舎には便所がない。
家の裏か道端にしゃがんでたれ流すのが普通である。
用を済ますと小さな水鉢から左手ですくってチャブチャブと尻にかける。
紙などは使わない。水鉢はそのまま炊具となるのだ。
苦力クラスになると水鉢は使わず、左指でぬぐって、近くの石や木にこすりつけるのが普通である。左手は不浄とし、右手の指を箸の代用としている。
2000m余に及ぶ大斜面が実によく耕され、段畑が天にも届くばかりである。
アンナプルナの北部にあるインド教徒の聖地;ムクチナート
待望していたマルシャンディ川
この河はガンジスの支流であるから、インド教徒にとっては母なる河となり、骨は河へ投げこまれるのである。こうして焼くのはまだよいほうで、そのまま流すのが多い。
カトマンズから一歩出ると、紙幣はほとんど通用しない。
字を読めないために受け取らないためばかりでもないらしい。
タルクガード・バザールから2里ほど登ると、道は二股になる。
左はポカラの町、
右はマルシャンディ渓谷を遡ってチベットへ行く塩街道である。
この谷に入ってから目につくのは、首に大コブをぶら下げた男女が多いことだ。
中には12,3の少女で、もうコブをつくっている者もある。
ヨウド不足からおかされるバセドー氏病だそうだ。
40歳過ぎの村の顔役らしのが、懐中から紙幣を取り出して見せた。
それは戦争中に日本政府がビルマで発行した百ルピーだった。
パゴダの絵があり、大日本帝国政府発行と印刷してある。
「トラ(バーグー)もクマ(バルー)もいる」
なるほど左手の中指、クスリ指、小指の3本とも根元からない。
行く手の雲の中からヒマリチュリやマナスルの尾根筋がちょいちょい見える。
谷幅もグッと狭まり、細道はその断崖絶壁の中腹を通っている。
大ヒマラヤを北から南へ断ち切って奔下する、いわゆる地球の石帯を断ち切る水の激しさには驚嘆すべきものがある。この相迫る岩壁に、即ち大自然が絶対に幅を利かせている場所に、どのいうにして作ったのかと目を見張らせるような道が、例えようもないほど大胆に斜面にはい登って曲がり、深く切れこんだ谷間の嶮しい岩壁を逆さ落しに下っていく。これがチベットに通じる塩街道なのである。
あんなところに住んで一生を終わる人もあるのだと思うと、その斜面にうごめく人影をも不注意に見落とせなかった。
やっとトンジェに着いた。
ここはマナスルの西麓で海抜1,800m、アンナプルナの分岐点ともなっている。
カトマンズから2週間、休みなしに登ってきた。
10頭20頭と隊を組んでドゥット・コーラの谷をチベットへ塩運びに出掛けるのだ。
「彼女らはクルミを拾っているんです」
この実を持ち帰って自宅の庭に蒔いたところ、1本だけ芽を出して成長したので、天皇陛下に献上したが、目下、皇居内でスクスクと育っている。
マナスル・クルミと名付けられたそうである。
ドクターにいわせると、高山病からくる症状であるという。
この汚物の清掃係りはサマの谷から毎日定期便のようにやってくるハシブトカラスたちであった。
この雪洞はなかなかうまく掘ってあって、暖かそうである。
このC6は現在8つあるキャンプのうちでいちばん雪崩の多い危険区域で、そこから1,000m頭上にそそり立つ北峰から、氷塔が「1つでも崩れ落ちたら、それこそ風の中の羽のように遥か真下のマナスル氷河へ吹き飛ばされてしまうこと請け合いといった、文字通りの地獄の宿である。
ラルキャ氷河の向こうに国境のギア・ラ(5700m)が見える。
このギア・ラ峠はチベットから塩や羊毛を、ネパールから雑貨や穀物をヤクの背で運ばれる重要な交易路なのである。
ゾーパ(ヤクとインド牛の雑種)
不思議なことに小便がちょっぴりしか出ない。
「酸素が少ないために腎臓が酷使されるためと、乾燥しているために、汗は蒸発してしまうのだ」
この高さに住まうと、動くこと自体が息苦しいし、神経も麻痺するためか、物事をつきつめて考えることなどとてもできない。ただただぼんやりとふ抜けのようになっているのが一番いいらしい。
アメリカ映画「失われた地平線」
桃源郷「シャンリ・ラ」
そこは文字通り花咲き乱れ鳥歌う桃源郷で、100歳を超えた女性でさえ娘のように若々しかった。この映画はアメリカで受けたのか、シャンリ・ラという空母まで現れ、日本近海を荒らし回った。
「日本人の祖先はヒマラヤ山中に住むレプチャ族である」
安田徳太郎博士
シッキム・ヒマラヤの主峰カンチェンジュンガの東南の谷に住む少数民族レプチャ人の言葉の中から、日本語の祖形がたくさん発見される。
河口彗海
明治36年6月、32歳で神戸を出発、500円の旅費をふところにしていた。
まずチベット語を学ぶためにダージリンに行き、2年間必死に勉強した。
カトマンズのボーダー寺院;ネパールの三大寺院の1つ
『西蔵旅行記』にダイラギリを仰いだ時の感想を次のように述べている。
また1910年に青木文教
マナスルの総経費は1億400万円
シェルパび中には生まれた日の名をとってつけた者が多い。
月曜;ダワ
火曜;ミンマ
水曜;ラクバ
木曜;プルブ
金曜;パサン
土曜;ペンバ
日曜;ニマ
食事の知らせはフライパンの底をドラのように叩く。
シェルパはそのザーヴ(旦那様)に対しては涙ぐましいほど献身的に努める。
万一死亡した場合は、独身者で300円、妻帯者で400円隊が支払うことになっていた。
終戦後は1ルピー;75円
山で負傷した場合は指一本につき150ルピー
一目で300
両眼で500
死亡;独身者500
;妻帯者1,000ルピー
そして一日にタバコ5本を与えなければならない。
1954年の第二次マナスル隊にアンツェリンという18歳の美少年が参加した。
それは日本から初めてのヒマラヤ遠征隊が立教大学山岳部からガルワール・ヒマラヤのナンダ・コットに派遣され、見事に初登頂に成功したからである。
ナンダ;「多幸の、祝福された」
コート;「要塞」
すでに6400m。
西北の空にはナンダ・デヴィの2尖峰が眉に迫るほど近い。
手前が東峰、うしろは主峰だ。
この主峰が1ヶ月前に英米隊のティルマンとオーデルによって登頂されたかと思うと、猛然とファイトが沸きあがってくる。
ピラミッド型のカメットや、バドリナート山群が朝焼けに映えている。
ロングスタッフのコル;峠
斜面の細い筋は「ヒマラヤ筋」といって、新雪雪崩の跡である。
見上げると、頂上を形づくるピラミッドは凄く急峻で、ことにシャールン谷側は文字通りの絶壁となり、雪もはりついていない。またナンダ・コット氷河に面している正面壁は、45度の急角度で一気に二千数百mも落ちている。
風と雪がますます猛威をふるって、ナンダ・コットは生あるもののように、われらの登高を徹底的に拒否する。
寒気が刻々とつのる夕暮れの行動には、死の危険が待ち構えている。
せっかくここまで登ってきたのだ、突っ込んでいきたい。
アイモ撮影機
シャールン谷から吹き上げる烈風は身体をなぎ倒すほどひどい。
2坪あるかどうかと思われるほど狭い頂上の雪の上に6人も立っている・・・
チベット高原が謎の姿を横たえ、中ほどに山帽子のような山がある。
あれが聖山と仰がれるカイラス山か。
なるほどうわさ通りの、リンガ;男根そっくりである。
カイラスのはるか北にたなびく雲のように東西に走っているのが、スウェイン・ヘディンが発見したというトランス・ヒマラヤであろう。ナンダ・デヴィ主峰の左はるか遠くに岩と雪のガッチリとした山はバドリナート山魂であろうし、その右手に三角水晶のように印象的に輝いているのがカメット;7757mである。
グルラマンダータ
グルン族;グルカ兵
インドやイギリスに雇われているが、非常に質実で、強いので有名である。
次男三男はインドに出て傭兵となる。
インパールやビルマで日本兵をさんざんやっつけたグルカ兵は、グルン族やマガール族の出身なのである。
低地の民族は非常に早婚で、こんなのがとビックリするような小娘が赤ん坊を抱いているのを多く見かけた。ポカラの町で娘たちの成人式を見たことがある。8歳から13歳ぐらいまでの小娘2、30名が、インド教祠に集まって、頭や手足に真っ赤な粉を塗って身を清めてもらっていた。もうその翌日にでも婚約ができるのだと聞かされてあきれてしまった。
ラマ教徒になると、一妻多夫、一夫多妻いりまじって、何がなんだか判らなくなる。
霊魂不滅を信じるインド教徒の墓所はガンガ:ガンジス川であるから、
地上には墓がないのである。
タルチョと呼ばれる布のぼりは、ボンきょう;シャーマン教のシンボルともいわれる。
チベットにラマ教が布教される前にボン教が普及していた。
ヒマラヤの山中の住民は、神が住む山と悪魔が住む山があると思い込んでいる。
カイラスはインド教、仏教両教徒から最も神聖な山として巡礼の跡を絶たない。
※ボン教、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の聖地なので、登頂はできない。
またガルワール・ヒマラヤのバドリナート;Badrinath
※シャンカラが訪れたとされる4つの巡礼地のひとつであり、ヒンドゥー教の聖地とされる
とケダルナート;Kedarnath Templeはインド教の二大神であるシヴァとビシュヌを祀っているために、キリスト教のエルサレムに相当する聖地とされている。
ラマ教徒の聖山マナスル別名;カンブンギェン:氷の肩の意
ラマ教徒は生まれ落ちたときにラマによって運命判断をされ名前をつけてもらう。
カトマンズを一歩離れると、正規の勉強をした医者など1人もいない。
草ね木皮を煎じて飲ませるか、加持祈祷に頼るのである。
だから日本隊のドクターは、まるで救世主のように有難がれ、遠いところから泊まりがけで病人を背負って診てもらいにくる。チベット人は軽い病気ならば、日光浴でなおす。
重病人は部屋に入れて看病するが、昏睡状態になると、水滴を顔に落として眠らぬようにする。眠ると悪魔に魂をさらわれると信じているのだ。
チベット人の習慣では、家で息を引き取らせることをせず、いよいよ命脈が切れたとみると、瀕死の病人を河原に連れて行って置き去るとの話である。
さて死んでしまうと、頭に温かみがあれば、天上界に生まれ変わる証拠であり、足元に温かみがあれば、地獄落ちする印であるといわれる。
死体は汚いボロ布に包まれ、両膝のあいだに頭を挟んで固くしばって丸くする。
そして日を選んで死体運搬人に渡す。
死体はもう魂の去った石ころと同じものとされ、親兄弟も付き添わない。
死体は川岸か岩の上に運ばれて、死体解剖者によって、肉と骨をはなされ、肉ダンゴと骨ダンゴを作ってハゲタカやカラスに与えられる。
早く食べられると、後生が良かったと喜ぶ。
死刑になった者とか、疫病の死体は埋葬される。なぜ火葬にしないかと聞くと、焼いた煙が天を汚すと、時ならぬ嵐になり、ヒョウが降ってきて作物を荒らすからだとの答えだった。
腸チブスが蔓延していて、ペニシリンの注射をしたら
「日本のお医者さんは死人を生きかえらせた」
ラジオも電話もないこの山中で、ビックリするほど早く、谷から谷へと風のように伝わっていった。
ヒマラヤ山中には井戸がない。
泉や谷川の濁った水に頼っている。
彼らの住む高地は不毛に近く、大麦、ソバ、ジャガイモをわずかに収穫する。
モロコシ、ヒエ、米などは下界からあおがなければならない。
大麦粉を炒って、ヤクの乳とかバターを混ぜて水かお湯でこねたツァンバを主食とする。野菜といえばトウガラシ、ニンニク、ジャガイモである。
チベット人はバターを入れた茶を一日20杯も飲むそうで、実に栄養がよく、近づくとプーンと乳の匂いがする。
ヒマラヤ山中の住民はタバコ亡者である。
男女とも5歳ぐらいから吸い出す。
タバコはすべてインドから輸入される。
多くの者は自家製のタバコを吸っている。
これには大麻そのほかの麻薬が入っている。
これを大小のキセルで吸う。
ヒマラヤ山中では、「タバコ屋へ7日」である。
マナスルの麓サマ村の人が、タバコを吸いたくなると、ブリ・ガンダキの渓谷をかれらの早足で7日下ってアルガト・バザールまで出なければならないのだ。タバコに限らず日用品などの雑貨を売る店も同様に低地のバザールにしかないのである。
ネパールの首都カトマンズからマナスルの麓までの190kmを、18日かかっての徒歩旅行に同行したポーターの数は、
1952年に75人
53年に300人
54年に450人
56年に400人となった。
ネパール米は小粒で、赤いもの、どす黒いもの、緑のものなど多彩であるが、煮るとなんともいえない臭気が鼻をつく。これにはみんな閉口してハシをつけたがらない。それよりも困ったことには、小石がいっぱい混じっていることだ。
アタ;小麦粉はよく買ってチャパティ;センベイをつくり、ギー;羊油で揚げて食べた。
精選されていないので、フスマが多く混じっていて色の黒い粉であった。野菜はニンニク、トウガラシのほかはほとんど見当たらなかった。
シェルパは火を神聖視して、肉でも魚でも直接火にあてて焼くことをしない。
「神聖な火に獣の肉を直接あてて、罰があたりますぞ」
富士山より90m高いマナスルのベース・キャンプに到着すると、誰からともなく時ならぬ放屁の轟音を発するようになった。しかも時と所を選ばずに発するのだから、誰も困った。
帰路3000m付近に下りると、申し合わせたように、ピッタリと止まった。
日中と日没後の温度差の激しさは、ちょっと想像もできない。
日中の最高温度は摂氏20~30℃になり、いったん陽が沈むと、急激に下がってたちまち零下になり、夜明けごろにはー20℃にもなる。マナスルでの最低温度は零下35℃だった。
長く滞在すると次第に衰弱を増して、精神状態も普通でなくなる。
ゴザインクンデの山中にあるイョルモなどは、ネパール一の美人の産地。
いよいよ氷雪の中の生活に入ると、酷寒、酸素欠乏などの悪条件が重なって、とても性欲など起こるものではないと、私自身の経験から他人をも律していた。
っところがそうではなかった。
7100mの第八キャンプで自慰行為を敢行した超馬力の2人の山男があった。
映画「マナスルに立つ」
で、落差2000mの大雪崩のシーンがあるが、ヒマラヤでは雪崩の危険はつきものである。
エヴェレストで7名のシャルパがさらわれたり、ナンガ・パルバットでドイツ人7人、シェルパ9人が一瞬に呑みこまれたり、その他雪崩に呑まれた登山家が多い。
ヒマラヤの雪崩は時と場所をまったく予測できない。
なにしろ山のスケールが桁外れに大きいので、登山家の目はコロリとだまされ、意外なときに遭難事件を起こす。
ラルキャ氷河からマナスルのプラトウ方面をのぞいていた隊員の1人は、ワーッ、と大声あげたので、「なんだ、なんだ」と寄っていくと、彼は顔をゆがめて、マナスルを指している。
プラトウから幾筋もの雪崩跡が見える。その一筋はまさしく、第七キャンプのあった跡を通っている。もし数日私たちのスケジュールがずれていたら、あの雪崩の下敷きになっていた。
日本とは「反物が安い国」という噂を聞きかじっている程度だった。
マナスルはグルカ県にある。
グルカ県は例の勇猛で知られるグルカ兵の故郷なのである。
至るところでグルカ兵の帰郷者や傷痍者に出会った。
ある村で、右腕と左足を失った人に会った。
「インパールで受けた傷だ。あれたちグルカ兵はイギリスに雇われて戦ったんだから、日本に恨みなんぞ持っていない」
チベットからは岩塩、羊毛、染料、毛皮などがヤクや羊の背に乗って下ってきて、この貿易路で交換される。取引量の最も多いのは岩塩であるから、この道を「塩街道」とも呼ぶ。
東西をつなぐ街道のなかで最も重要視される1本は、カトマンズと西210kmにあるポカラをつなぐ街道。
数年前に開通した空路によれば30分で行けるのに、街道そのものは千年前と少しも変わりなく、自転車はおろか、馬さえ通わない。そこで旅人はテクテクと15~18日も歩く。
我々は「ウンコ街道」と命名した。
ネパール人の置き忘れたウンコは、どれもこれも物凄く太くて長い。
彼らは、ヒエ、モロコシなどの主食以外からは栄養を摂らないので、大食いとなり、その結果「おおグソ」をたれるようになる。
ヤクは暑さに弱い動物で、標高3000m以下では役にたたない。
モロコシの育つところにはヤクは住めないといわれる。
ヤクは年中放牧されていて、屋内で眠ることを知らないし、人から餌をもらうことも知らない。草を求めて次第に高地に登っていく習性がある。
ヤクの眼はちょっと凄みがあるので、恐ろしくて近寄れない。
ヤク追い人が後ろから追いたてると歩くが、さもないと道草ばかりくっている。
そしてすぐに一列横隊になる習性をもっている。
ヤクの毛は冬になると、地面すれすれになるまで伸び、膝の毛は袴をはいたような格好になる。これを刈り取ってナワや織物にする。
ヤクとコブ牛の雑種を「ゾー」という。
この乳からとったバター、チーズ、ヨーグルトはチベット人にとって欠くことのできない栄養となる。
マナスル隊は犬に縁が深いようだ。
53年の第一次隊には「ロン」
第二次隊には「ラト」「ハク」
第三次隊には「ビリー」がそれぞれ同行した。
ネパール三大仏塔の随一といわれる「ボーダーラマ寺院」
カトマンズ郊外、カカニの丘;
ニルカンタ公園
スインブー寺院
早く起きて練兵場広場からヒマラヤの雪峰を望んだ。
ゴザインタン、ランタン・ヒマール、ガネッシュ・ヒマールが前山から顔をのぞかせている。
こんな美しい山の町は世界のどこにもあるまい。
夕食に柿がでた。ネパール産だという。
小粒だが、まさしく柿である。
ネパールでもカキと呼ぶのだそうだ。
「ほんとうに大丈夫ですか」と念を押すと、顎をグッと後ろへひいた。
この身振りがOKの印なのである。
カトマンズ郊外、カカニの丘の眺望は世にも素晴らしいものだった。
2200mの丘の上に立つと、北の空にエヴェレストをはじめネパール・ヒマラヤの巨峰群が指呼の間にあり、その山肌をおおう氷雪の冷たさ、吹きまくる寒風のいたさがじかに身にしみるほどである。
エヴェレストの右にマカルー、さらに右の端にカンチェンジュンガが霞んでいる。
こうして、ボクの目にはいっているヒマラヤの巨人峰は実に8座を数えるのだ。
8000mの巨人峰が世界で13座ある中で、8座を一目で見渡せるという雄大な展望台は、ここをおいて他にあるまい。
チベットの山湖でとれる岩塩は沙羅双樹(サル・トリー)の広い葉に包まれている。
山国ネパールはチベットの塩に頼っている。
塩は米とともに物価の標準になる。
米2対塩1という割合。
ネパールの旅人は自分の寝具や炊具を持って歩き、薪は途中で拾っていくので、宿屋では泊まり賃だけでよいのだ。人夫などは大木の下か岩穴を常宿にするのだという。
なるほど、街道の至る所に岩穴があり、煙で真っ黒にくすぶっている。
トリズリ・バザールはチベット街道とポカラ街道の交差点にあたる大きなバザールである。
ポカラ;国際山岳記念館
チョーターラは熱い国の街道のオアシスだ。
村の娘たちはパパイヤ、バナナ、キウリを並べていたり、モロコシかヒエからつくった地酒「ロキシー」を一杯5、6円で売っている。
ネパールの田舎には便所がない。
家の裏か道端にしゃがんでたれ流すのが普通である。
用を済ますと小さな水鉢から左手ですくってチャブチャブと尻にかける。
紙などは使わない。水鉢はそのまま炊具となるのだ。
苦力クラスになると水鉢は使わず、左指でぬぐって、近くの石や木にこすりつけるのが普通である。左手は不浄とし、右手の指を箸の代用としている。
2000m余に及ぶ大斜面が実によく耕され、段畑が天にも届くばかりである。
アンナプルナの北部にあるインド教徒の聖地;ムクチナート
待望していたマルシャンディ川
この河はガンジスの支流であるから、インド教徒にとっては母なる河となり、骨は河へ投げこまれるのである。こうして焼くのはまだよいほうで、そのまま流すのが多い。
カトマンズから一歩出ると、紙幣はほとんど通用しない。
字を読めないために受け取らないためばかりでもないらしい。
タルクガード・バザールから2里ほど登ると、道は二股になる。
左はポカラの町、
右はマルシャンディ渓谷を遡ってチベットへ行く塩街道である。
この谷に入ってから目につくのは、首に大コブをぶら下げた男女が多いことだ。
中には12,3の少女で、もうコブをつくっている者もある。
ヨウド不足からおかされるバセドー氏病だそうだ。
40歳過ぎの村の顔役らしのが、懐中から紙幣を取り出して見せた。
それは戦争中に日本政府がビルマで発行した百ルピーだった。
パゴダの絵があり、大日本帝国政府発行と印刷してある。
「トラ(バーグー)もクマ(バルー)もいる」
なるほど左手の中指、クスリ指、小指の3本とも根元からない。
行く手の雲の中からヒマリチュリやマナスルの尾根筋がちょいちょい見える。
谷幅もグッと狭まり、細道はその断崖絶壁の中腹を通っている。
大ヒマラヤを北から南へ断ち切って奔下する、いわゆる地球の石帯を断ち切る水の激しさには驚嘆すべきものがある。この相迫る岩壁に、即ち大自然が絶対に幅を利かせている場所に、どのいうにして作ったのかと目を見張らせるような道が、例えようもないほど大胆に斜面にはい登って曲がり、深く切れこんだ谷間の嶮しい岩壁を逆さ落しに下っていく。これがチベットに通じる塩街道なのである。
あんなところに住んで一生を終わる人もあるのだと思うと、その斜面にうごめく人影をも不注意に見落とせなかった。
やっとトンジェに着いた。
ここはマナスルの西麓で海抜1,800m、アンナプルナの分岐点ともなっている。
カトマンズから2週間、休みなしに登ってきた。
10頭20頭と隊を組んでドゥット・コーラの谷をチベットへ塩運びに出掛けるのだ。
「彼女らはクルミを拾っているんです」
この実を持ち帰って自宅の庭に蒔いたところ、1本だけ芽を出して成長したので、天皇陛下に献上したが、目下、皇居内でスクスクと育っている。
マナスル・クルミと名付けられたそうである。
ドクターにいわせると、高山病からくる症状であるという。
この汚物の清掃係りはサマの谷から毎日定期便のようにやってくるハシブトカラスたちであった。
この雪洞はなかなかうまく掘ってあって、暖かそうである。
このC6は現在8つあるキャンプのうちでいちばん雪崩の多い危険区域で、そこから1,000m頭上にそそり立つ北峰から、氷塔が「1つでも崩れ落ちたら、それこそ風の中の羽のように遥か真下のマナスル氷河へ吹き飛ばされてしまうこと請け合いといった、文字通りの地獄の宿である。
ラルキャ氷河の向こうに国境のギア・ラ(5700m)が見える。
このギア・ラ峠はチベットから塩や羊毛を、ネパールから雑貨や穀物をヤクの背で運ばれる重要な交易路なのである。
ゾーパ(ヤクとインド牛の雑種)
不思議なことに小便がちょっぴりしか出ない。
「酸素が少ないために腎臓が酷使されるためと、乾燥しているために、汗は蒸発してしまうのだ」
この高さに住まうと、動くこと自体が息苦しいし、神経も麻痺するためか、物事をつきつめて考えることなどとてもできない。ただただぼんやりとふ抜けのようになっているのが一番いいらしい。
アメリカ映画「失われた地平線」
桃源郷「シャンリ・ラ」
そこは文字通り花咲き乱れ鳥歌う桃源郷で、100歳を超えた女性でさえ娘のように若々しかった。この映画はアメリカで受けたのか、シャンリ・ラという空母まで現れ、日本近海を荒らし回った。
「日本人の祖先はヒマラヤ山中に住むレプチャ族である」
安田徳太郎博士
シッキム・ヒマラヤの主峰カンチェンジュンガの東南の谷に住む少数民族レプチャ人の言葉の中から、日本語の祖形がたくさん発見される。
河口彗海
明治36年6月、32歳で神戸を出発、500円の旅費をふところにしていた。
まずチベット語を学ぶためにダージリンに行き、2年間必死に勉強した。
カトマンズのボーダー寺院;ネパールの三大寺院の1つ
『西蔵旅行記』にダイラギリを仰いだ時の感想を次のように述べている。
また1910年に青木文教
マナスルの総経費は1億400万円
シェルパび中には生まれた日の名をとってつけた者が多い。
月曜;ダワ
火曜;ミンマ
水曜;ラクバ
木曜;プルブ
金曜;パサン
土曜;ペンバ
日曜;ニマ
食事の知らせはフライパンの底をドラのように叩く。
シェルパはそのザーヴ(旦那様)に対しては涙ぐましいほど献身的に努める。
万一死亡した場合は、独身者で300円、妻帯者で400円隊が支払うことになっていた。
終戦後は1ルピー;75円
山で負傷した場合は指一本につき150ルピー
一目で300
両眼で500
死亡;独身者500
;妻帯者1,000ルピー
そして一日にタバコ5本を与えなければならない。
1954年の第二次マナスル隊にアンツェリンという18歳の美少年が参加した。










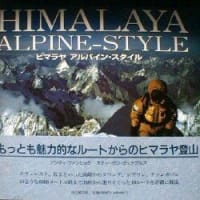
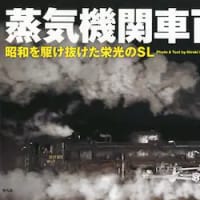
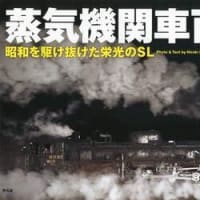
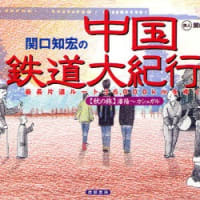
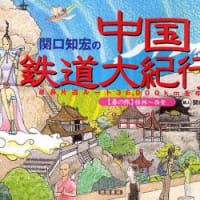
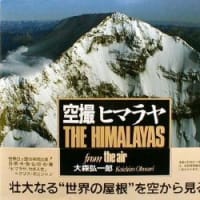

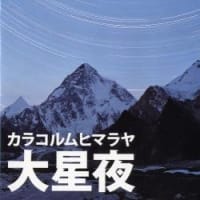
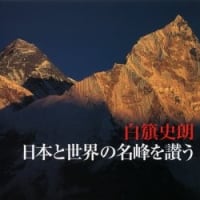
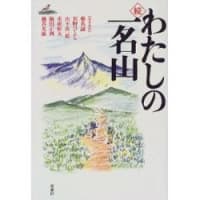
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます