幼児はよく、こんな「おひさま」を描いたりする。
でも、絵の教室に通ったり、小学校に上がったりすると、
どうも、こんな絵を描いてはいけないような気がしてくる。
「なんか、幼稚だな」と。
ひとつは、クレヨンという筆記具に限界があって、
基本的に線しか描けない。色を混ぜたり重ねたりできない。
色数も決まっている。
線は力加減である程度太くしたり細くしたりできるが、
大きな面を塗りつぶすことはできない。
クレヨンの先を斜めに大きく削ったり、持ち手に巻き付けてある紙を
はがしたりすれば、面を塗りつぶすことは出来るが、
なんか、親とか先生に叱られそうな気がする。
で、結局、おかあさんの顔とかおひさまの丸い部分とかは、ぐしゃぐしゃと
でも、この「赤〇チョンチョンで、おひさま」「にこにこしたおかあさん」が
幼稚に見えるのは、そんな、クレヨンの限界からばかりじゃない。
「絵というより記号」だから、じゃないかなと、現在の私は思う。
記号は、形や色ばかりじゃなくて音とか立体とかも記号になり得るけれど、
絵とは関係ないから、ここでは、そちらはちょっと脇に置いてしまおう。
記号(シンボル)は、「意味を与えられたもの」「対応する〈何か〉を指し示すもの」
漢字は典型的な記号だ。漢字の「木」は樹木一般を指し示す。つまり樹木一般という「意味」を与えられている。
「木」は明朝体で「木」と書こうがゴシックで「木」と書こうか゛
その指し示す意味に変わりはない。木は木である。
で、これと同じことが「赤〇ちょんちょんでおひさま」「ニコニコ顔でおかあさん」
には起きてしまう。これらは記号なので、赤丸が少々いびつになっても、ちょんちょんの数が
多くても少なくてもその指し示す処は揺るぎないのだ。

どれも、おひさま。
で、これの何がいけないんだろう。
いや、べつにいけなくはないんだけど、気になることはある。
幼児の描いた絵を見て、お兄さんや大人たちが、
「これ何の絵?」「なにを描いたの?」と聞いたりはしていないか、と。
こう聞かれるとこどもは「そうか、絵は『何を描いたか分かる』ことが大事なんだ」
そう思い込んでしまうんじゃないか。
ピカソの絵を見たり、現代絵画を見たりして大人はよく「この絵は分からない」
と言う。ピカソだって色々な絵を描いているから、
その「わからない」絵が、どの時代のどの作品を指しているのか知らないが。
絵はわからなければいけないものなんだろうか。
「わからない」というのは「何を描いているものなのかわからない」のか、
「こんな絵を描く意図が分からない」のか。
「分かることが大事」なら「赤〇ちょんちょんでおひさま」式でいいじゃないか。
つまり絵は記号の集積で事足りることになる。
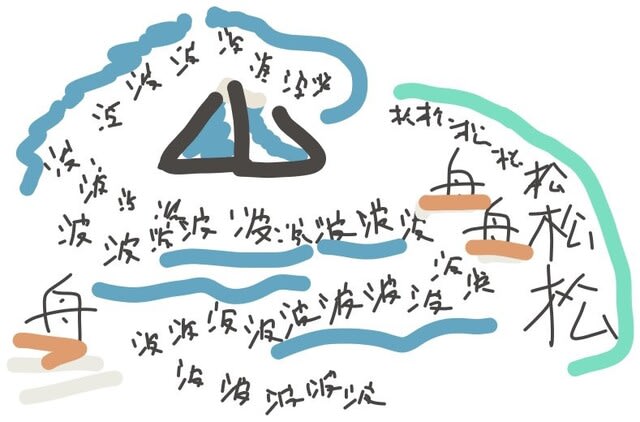
ちょっといたずら心を起こして、こんな絵を描いてみました。
絵は「何を描いたか分かれば良い」と言う なら、これでいいじゃない。
どう? わかりやすいでしょう? 昔、銭湯によくあった「白波に松原、
帆掛け船、富士山」です。
う~ん、お絵描きタブレットではどうもうまく描けないな。これが限界。
もう少し真面目に(笑)紙に描いてみようかな。意外と面白いぞ、これ。











